「いい人をやめたい」本音を言えずにつらい人が“自分を出せるようになる”ための心理的ステップ
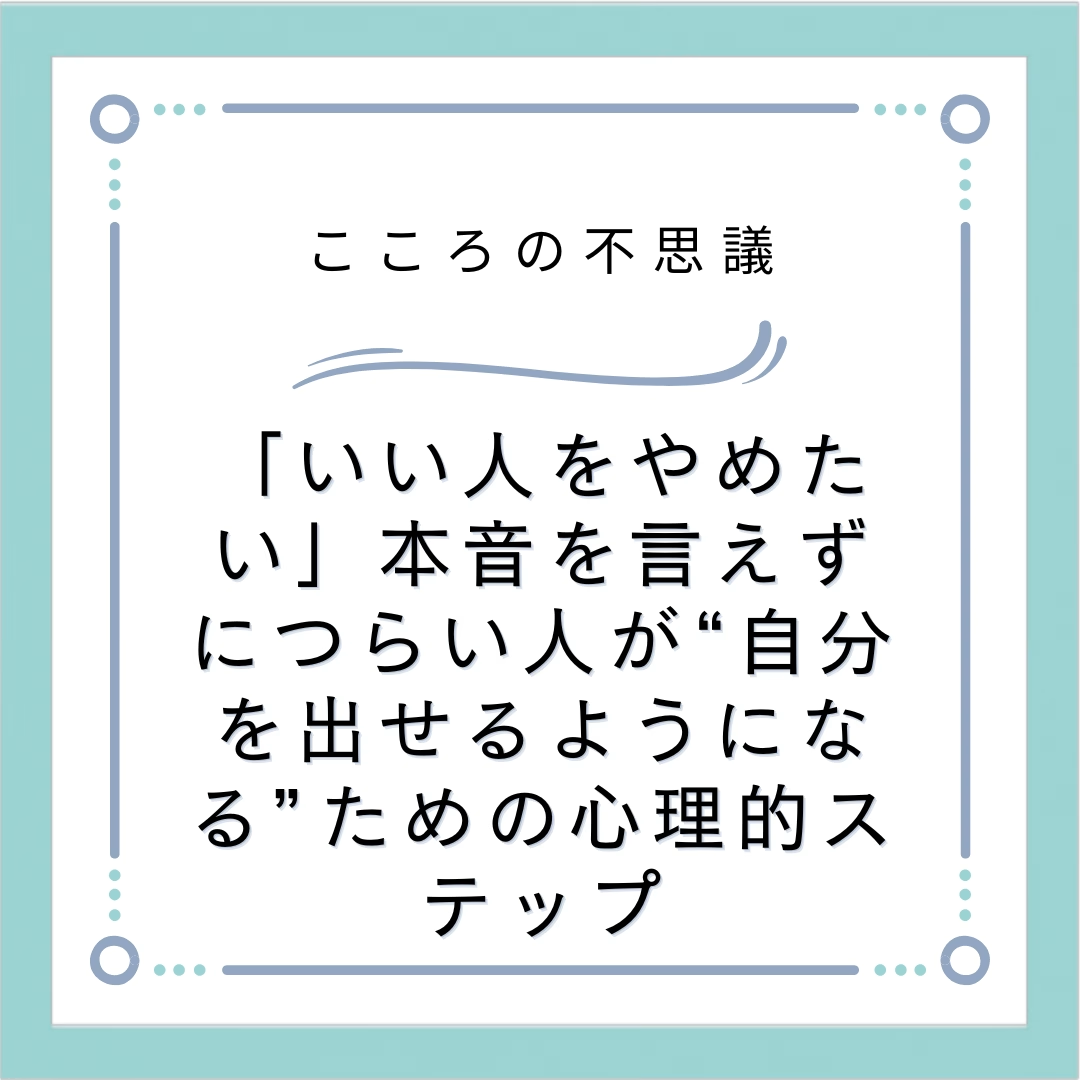
「いい人だよね」と言われると、うれしいような、どこか息苦しいような気持ちになる。
人に気を使うのは自然なこと。場の空気を読んで穏やかに振る舞うのも、優しさのひとつです。けれど、その優しさがいつの間にか“演技”のように感じられたとしたら、それは心が疲れているサインかもしれません。
「断るのが怖い」「嫌われたくない」「波風を立てたくない」。そんな思いから、自分の意見を飲み込み、周囲に合わせることを繰り返していくうちに、ふと気づくと「自分が何を感じているのかわからない」と戸惑う瞬間が訪れます。人間関係はうまくいっているはずなのに、心の奥ではぽっかりとした孤独を抱えてしまうことも少なくありません。
実は、“いい人”でいようとする裏には、「自分には価値がないのでは」という不安が隠れていることがあります。他人に認められることで安心しようとするうちに、本音を隠すクセがついてしまうのです。ですが、そのままでは本当の意味で人とつながることが難しくなり、どんな関係の中でも息苦しさが残ってしまいます。
この記事では、「いい人を演じるのがつらい」「本音を出せない自分を変えたい」と感じているあなたに向けて、
なぜ本音を出せなくなるのか、その心理的な背景と、少しずつ“自分を取り戻す”ための方法をお伝えします。無理に変わる必要はありません。ほんの少し、自分の感情に正直になるところから始めてみませんか。
この記事でつかめる心のヒント
- いい人を演じると心が疲れる理由: 自分に自信がなく不安だからこそ、相手に認められようとしすぎてしまい、その結果心が疲れてしまうことが多いです。
- 自分の気持ちを抑える原因: 断るのが怖い、嫌われたくない、波風を立てたくないといった不安が、自分の本音や気持ちを押し殺す原因になっています。
- 本音を出せるようになるには: 少しずつ自分の感情に正直になり、小さなことから自己表現を始めることで、自然と本音を出せるようになっていきます。
- 『いい人』でいる裏の心の問題: 自分には価値がないのではないかという不安や認められたい気持ちが、『いい人』を続ける裏側に隠れており、それが自己防衛になっています。
- 自分らしさを取り戻すためのコツ: 自分の感情に素直になり、少しずつ自己表現や自己理解を深めることで、無理なく自分らしさを取り戻すことができます。
電話カウンセリングのリ・ハートに訪れる方の主な検索キーワード
投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー
-
【経歴】
・キャリアカウンセラー15年
・心理カウンセラー10年
※相談件数10,000件以上
【主な相談内容】
1.ストレス管理とメンタルケア
・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。
・仕事や家庭でのストレス解消法。
2.自己理解と自己成長
・自己肯定感を高めたい。
・自分の強みや価値観を明確にしたい。
3.人間関係の悩み
・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。
・対人関係における不安や緊張感への対処法。
4.不安や恐怖の克服
・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。
・パニック障害や全般性不安障害のケア。
5.うつ症状や気分の浮き沈み
・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。
・抑うつ状態から抜け出したい。
6.人生の転機や変化への対応
・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。
・新しい環境への不安や戸惑い。
7.恋愛や夫婦関係の悩み
・パートナーシップの問題解決。
・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。
8.自己批判やネガティブ思考の改善
・自分を責めすぎる傾向を変えたい。
・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。
9.家族関係や親子間の問題
・子育ての悩み。
・親や家族との関係性の見直し。
10.生きる意味や自己実現の探求
・人生の目的を再確認したい。
・自分らしい生き方を見つけるサポート。
【アプローチ方法】
1.傾聴を重視したカウンセリング
・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。
・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。
2.クライアント中心療法
・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。
・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。
3.認知行動療法(CBT)
・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。
・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。
4.ナラティブセラピー
・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。
・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。
5.対話を通じた柔軟なサポート
・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。
・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。
目次
- ○ なぜ「いい人」を演じ続けるとつらくなるのか?
- ・「嫌われたくない」気持ちが、心の自由を奪う
- ・「いい人でいなければ価値がない」という思い込み
- ・「我慢が当たり前」になると、感情が麻痺してしまう
- ○ 「本音を出せない自分」ができあがる心理的な背景
- ・幼少期の「期待に応えたい」気持ちが大人になっても続く
- ・「他人の評価」で自分の価値を決めてしまう癖
- ・「争いを避けたい」気持ちが、沈黙を生む
- ○ 少しずつ“本音を出す練習”を始めてみる
- ・小さな「NO」を伝えるところから始める
- ・感情を言葉にして伝える習慣をつける
- ・「いい人をやめる」ではなく「誠実な人でいる」と考える
- ○ 本音を出せる自分になるために ― “いい人”から“自分を生きる人”へ
- ・“自分の感情”を信じることから始めよう
- ・“我慢の優しさ”より“誠実な優しさ”を選ぶ
- ・“本音を出す=関係を壊す”という思い込みを手放す
- ○ 「いい人を演じるのをやめたい」――本音を出せる自分に変わるための小さな一歩
なぜ「いい人」を演じ続けるとつらくなるのか?

「いい人でいたい」と思う気持ちは、決して悪いことではありません。むしろ人間関係を大切にする誠実さの表れでもあります。
ただ、その優しさが“我慢”や“気づかれない努力”の上に成り立っているとしたら、少し注意が必要です。
たとえば、友人の頼みを断れずに無理をしてしまう。職場で嫌なことを言われても笑って受け流す。家族の意見に反対したいのに「そうだね」と合わせてしまう――そんなことを重ねていくうちに、だんだんと心が疲弊していきます。
「いい人」であるほど、自分の感情を抑えるクセが強くなり、相手にとって都合の良い存在を演じてしまう。
最初は“思いやり”だった行動も、次第に“義務”や“役割”に変わり、いつの間にか「自分が何を感じているのか分からない」という状態に陥ります。
ここでは、“いい人”でいることがなぜ心の負担になるのかを、3つの側面から見ていきましょう。
「嫌われたくない」気持ちが、心の自由を奪う
多くの人が「いい人」でいようとする一番の理由は、「人から嫌われたくない」という恐れです。
この気持ちはごく自然なもので、人間関係を円滑に保つうえではある程度必要な感情でもあります。
けれど、それが強くなりすぎると、自分の意見や感情を押し殺すようになります。
「怒らせたらどうしよう」「場の空気を壊したくない」と考えるあまり、本心を封じ込める。
その結果、表面上は平和でも、内側では“自分を否定し続けるストレス”が積み重なっていくのです。
本音を出さないまま過ごしていると、他人からの評価ばかりが気になるようになり、自分の気持ちよりも“どう思われるか”を基準に判断してしまいます。
この「他人基準の生き方」が、心の自由を少しずつ奪っていくのです。
「いい人でいなければ価値がない」という思い込み
「いい人」を続ける人の中には、“他人に優しくする=自分の存在価値”だと信じている人もいます。
たとえば、子どものころに「周りに合わせる子がいい子だね」と言われ続けてきた経験があると、知らず知らずのうちに「自分を出すと嫌われる」と思い込んでしまうのです。
この思い込みが強いと、自分の感情を優先することに強い罪悪感を感じます。
休みたいときに休むこと、嫌なことを断ること、助けを求めること――本来は誰にでも必要な行動なのに、「わがまま」「自分勝手」と感じてしまう。
その結果、常に誰かのために頑張りすぎて、自分の気持ちを後回しにしてしまいます。
「いい人」をやめることは“自己否定”ではなく、“自分を取り戻す選択”であることに、少しずつ気づいていくことが大切です。
「我慢が当たり前」になると、感情が麻痺してしまう
“いい人”として生きていると、無意識に「我慢するのが普通」と思い込んでしまいます。
多少の不満があっても「みんなそうだし」と自分を納得させ、感情を抑え込むクセがつく。
けれど、人の心は無限に我慢できるものではありません。
小さなストレスを溜め続けると、ある日突然、理由もなく涙が出たり、誰にも会いたくなくなったりします。
それは、抑え込んできた感情が限界を迎えたサインです。
感情を我慢し続けると、嬉しいことや楽しいことにも鈍感になります。
「本音を出さない=自分を守る手段」だったはずが、いつの間にか“心の麻痺”を引き起こしてしまうのです。
「本音を出せない自分」ができあがる心理的な背景

「本音を言いたいのに、言えない」。
そう感じるとき、多くの人は「自分の性格だから仕方ない」と思いがちです。
けれど、実は“本音を出せなくなる”には、きちんとした理由があります。
それは、過去の経験や人間関係の中で培われた“心のクセ”のようなもの。
誰かを傷つけたくない、嫌われたくない、安心していたい──そうした気持ちが積み重なって、「自分より他人を優先する」という行動パターンを作っていくのです。
特に、幼いころから「空気を読める子」「優しい子」と言われて育った人ほど、その傾向が強くなります。
小さな頃の“期待に応える”という成功体験が、「自分は我慢してこそ価値がある」という誤解につながってしまうことも。
ここでは、そんな“本音を隠してしまう”心理の背景を、3つの角度から見ていきましょう。
幼少期の「期待に応えたい」気持ちが大人になっても続く
子どもの頃、親や先生から「いい子でいなさい」と言われてきた経験はありませんか?
その言葉自体に悪意はなくても、子どもにとっては「いい子=怒られない」「褒められる」「愛される」という意味として刷り込まれやすいのです。
やがてその感覚が、「人に合わせることで安心を得る」という生き方に変わっていきます。
たとえ大人になっても、無意識に“人の期待を読んで行動する”ようになり、自分の感情を後回しにする癖が抜けません。
本音を伝えるよりも、相手がどう思うかを優先してしまう。
その積み重ねが、次第に「本音を言う=関係が壊れる」という誤った連想を強化してしまうのです。
だからこそ、まずは「本音を言うことは危険ではない」と、少しずつ自分の中の安全感を取り戻していくことが大切です。
「他人の評価」で自分の価値を決めてしまう癖
本音を出せない人の多くは、無意識のうちに“他人の評価”を自分の基準にしてしまっています。
「嫌われたらどうしよう」「失望されたくない」という思いが強いと、どうしても他人の期待に合わせる行動が増えてしまう。
しかし、他人の評価はいつも変わるものです。
どれだけ努力しても、誰かの基準には合わないことがある。
それでもなお「評価されていない=自分に価値がない」と感じてしまうと、心はどんどん疲弊していきます。
この状態では、“自分がどうしたいか”という感覚が鈍くなり、他人の反応にばかり敏感になります。
本音を出す余裕もなくなり、常に「どう思われるか」を軸に生きてしまう。
少し勇気を出して、自分の中の「小さな喜び」や「納得できる選択」を基準にしてみると、他人の視線に支配されない感覚を取り戻せます。
「争いを避けたい」気持ちが、沈黙を生む
人と意見がぶつかるのが苦手で、つい黙ってしまう。
そんなとき、「穏やかでいたい」「平和に過ごしたい」という気持ちが働いています。
一見やさしさのようですが、実は“衝突=怖いもの”と感じている状態です。
過去に、怒られたり否定されたりした経験が強く残っていると、「意見を言うと攻撃されるかもしれない」という不安が生まれます。
その結果、言いたいことを飲み込み、関係を壊さないために“沈黙”を選ぶようになるのです。
けれど、沈黙を続けることで本当の意味での信頼関係は築けません。
意見を伝えることは、相手を否定することではなく、「自分もここにいる」と伝える行為。
衝突を恐れるよりも、「違ってもいい」と受け止め合う関係のほうが、心はずっと楽になります。
少しずつ“本音を出す練習”を始めてみる

本音を言うことに慣れていない人ほど、「いきなり自分を変えなきゃ」と思いがちです。
でも、人間関係の中で“いい人”を長く演じてきた人が、急に本音をさらけ出すのは難しいもの。
大切なのは、「正直に話すこと=衝突すること」ではないと理解することです。
本音を出すことは、相手に自分の気持ちを押しつけることではなく、「自分も一人の人間として存在している」と伝える行為です。
最初は小さな一歩で十分。たとえば、「今日は疲れているから後にしてもいい?」とか、「それはちょっと考えたいな」と、軽く自分の気持ちを表現するところから始めてみる。
そんな小さな言葉の積み重ねが、“本音を出す勇気”を育てていきます。
ここからは、実際にどのようにして本音を少しずつ出せるようになるのか、その3つのステップを見ていきましょう。
小さな「NO」を伝えるところから始める
本音を出す練習として、一番やりやすいのが“軽い断り”です。
たとえば、誘いを受けたときに「行けたら行く」ではなく、「今日はやめとくね」と伝えてみる。
最初は勇気がいりますが、自分の気持ちを優先する感覚を体で覚えることが大切です。
このとき意識したいのは、“言い方”です。
断る=冷たい、ではありません。
「今は疲れてて、また元気なときに行こう」など、柔らかい言葉を添えるだけで、相手も傷つかずにあなたの気持ちを理解しやすくなります。
何より、自分の「やりたくない」を尊重できたとき、心の中に小さな解放感が生まれます。
それが“自分を大切にする感覚”の第一歩になります。
感情を言葉にして伝える習慣をつける
「本音を言う」と聞くと、意見や主張をはっきり言うことを想像する人が多いですが、実はもっとシンプルです。
それは、「今どう感じているか」を言葉にすること。
たとえば、「ちょっと緊張してる」「少し不安なんだ」と素直に伝えるだけでも、自分の内側を認める行為になります。
感情を表現することで、心が整理され、相手にも自分の状態が伝わりやすくなる。
結果として、すれ違いや誤解も減っていくのです。
特に、普段「平気」「大丈夫」と言ってしまう人ほど、感情を言葉にする練習は効果的です。
誰かに理解してもらう前に、まず自分自身が“感じていることを許す”ことから始めてみましょう。
「いい人をやめる」ではなく「誠実な人でいる」と考える
“いい人をやめよう”とすると、つい極端に振れてしまいます。
「もう我慢しない」「自分のことだけ考える」といった反動が出ると、人間関係がギクシャクしてしまうことも。
大事なのは、“他人に合わせすぎるいい人”から、“自分にも誠実な人”になること。
つまり、「自分の気持ちを尊重しながらも、相手も大切にできる」というバランスを目指すのです。
たとえば、「それは違うと思うけど、あなたの考えも理解できる」と伝えるような柔らかい主張の仕方。
これは、衝突を避けつつ本音を表現できる方法です。
誠実さは、相手に媚びることでも、我を通すことでもなく、自分の言葉で丁寧に伝える姿勢にあります。
本音を出せる自分になるために ― “いい人”から“自分を生きる人”へ
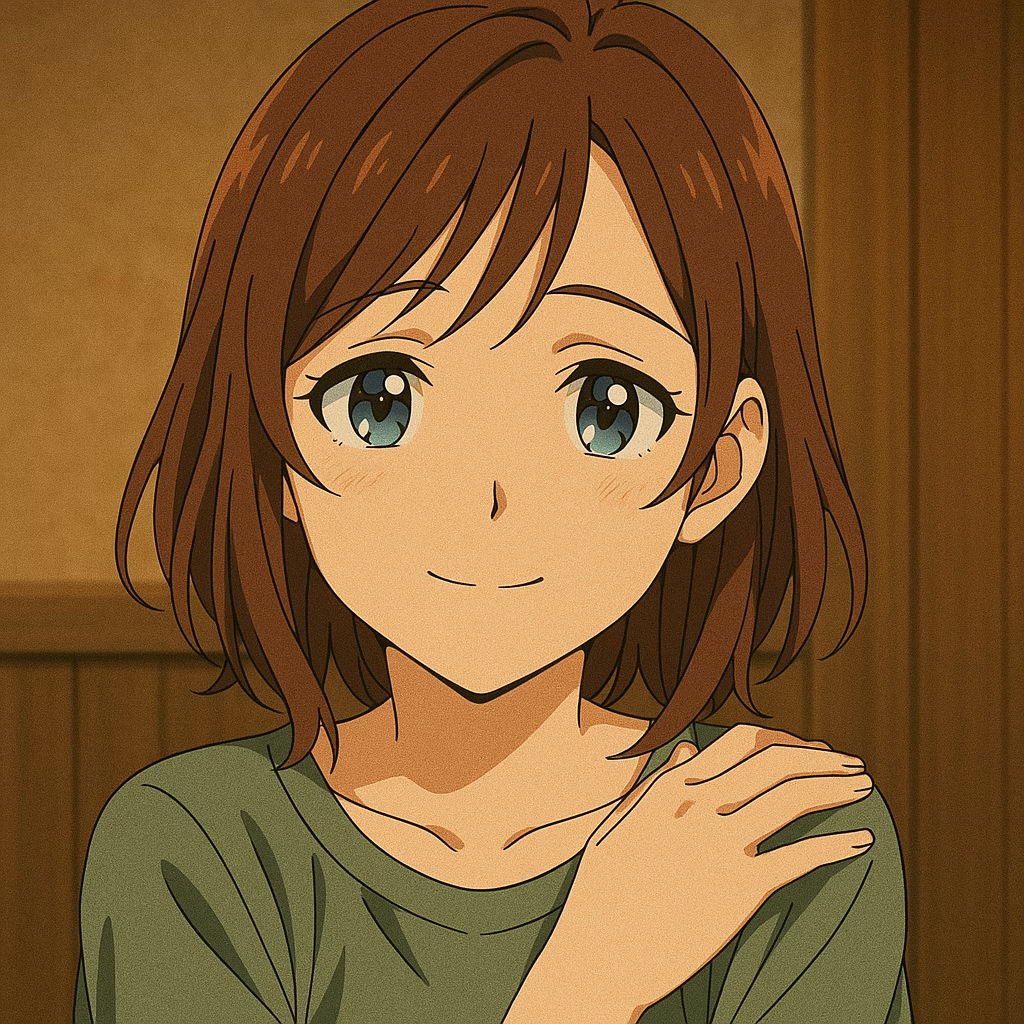
本音を出すことに罪悪感を持ってきた人ほど、いざ「自分を出していい」と言われても、どうすればいいのか戸惑うものです。
長いあいだ“いい人”として生きてきた人は、無意識のうちに「人に合わせる=正しい」と信じてきました。
でも、本音を隠してまで誰かの期待に応える生き方は、あなたの優しさをすり減らしてしまいます。
本音を出すことは、決してわがままでも反抗でもありません。
それは、自分の気持ちを大切に扱うという“自分への誠実さ”の表れです。
人との関係の中で自分を守るために必要なことでもあります。
ここでは、“いい人”を手放しても人間関係が壊れないどころか、むしろ深まっていく3つの考え方を紹介します。
無理をせず、少しずつ「自分を生きる」方向へ歩き出しましょう。
“自分の感情”を信じることから始めよう
他人を気にしてばかりいると、自分の感情が何を伝えようとしているのか分からなくなります。
でも、感情はあなたの本音を知らせてくれる大切なサインです。
「嫌だ」「寂しい」「楽しい」「ホッとする」――そのどれもが、あなたの“心の現在地”を教えてくれています。
本音を出すための第一歩は、自分の感情を無視しないこと。
たとえば、何かを頼まれて違和感があったら、「本当はやりたくないかも」と心の声を拾う。
その気づきを責めずに受け止めるだけでも、少しずつ自分の感覚が戻ってきます。
「自分の気持ちを感じる力」が回復すると、他人の言葉に流されにくくなり、自然と自分軸が育っていきます。
“我慢の優しさ”より“誠実な優しさ”を選ぶ
「相手を傷つけないように」と思うあまり、我慢を続けてしまう人は多いものです。
けれど、我慢の上に成り立つ優しさは、長続きしません。
やがて疲れが限界に達し、心のどこかで「自分ばかり損をしている」と感じてしまう。
本当に優しい人とは、“自分の気持ちも相手の気持ちも大切にできる人”です。
たとえば、「今は手伝えないけど、応援してるね」と伝えるように、自分を犠牲にせず関わる方法もある。
その方が、相手との信頼関係も長く安定して続きます。
優しさは“我慢”ではなく、“誠実さ”から生まれる。
そう思えたとき、あなたの中の「いい人でいなければ」という縛りは、自然とゆるんでいきます。
“本音を出す=関係を壊す”という思い込みを手放す
多くの人が、本音を言うと人間関係が壊れるのではないかと不安になります。
でも、実際には“本音を出せない関係”こそが、ゆっくりと距離を生んでいくのです。
相手に合わせ続けることで、どちらも本当の気持ちを分かち合えなくなり、表面的なつながりだけが残ってしまう。
本音を伝えることは、むしろ信頼の証です。
「この人なら受け止めてくれる」と感じるからこそ、素直な気持ちを話す勇気が出る。
それに、もし本音を出して関係が少し変わったとしても、それは“壊れた”のではなく“正直な形に整った”だけのこと。
人とのつながりは、本音のやりとりを通してこそ深まります。
あなたが自分の心に誠実でいようとするとき、きっとその誠実さは周りにも伝わっていきます。
「いい人を演じるのをやめたい」――本音を出せる自分に変わるための小さな一歩
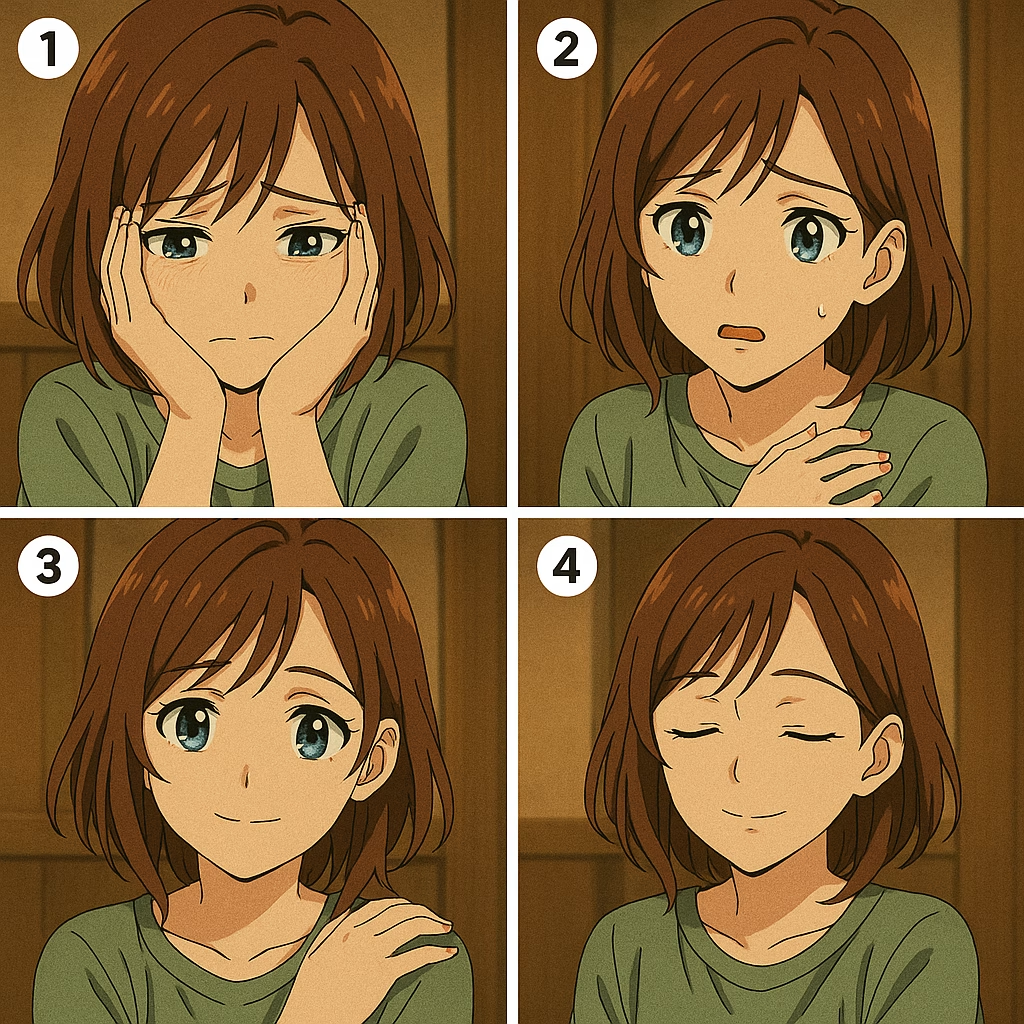
「いい人」をやめることは、今までの自分を否定することではありません。
むしろ、“誰かのために頑張ってきた自分”を、やっと休ませてあげることです。
人に合わせすぎて疲れてしまうのは、それだけあなたが相手を思いやってきた証。
でも、その優しさが自分を苦しめる形になっているなら、そろそろ方向を少しだけ変えてみてもいいのかもしれません。
本音を出すことは、衝突を生むものではなく、「自分もここにいる」と伝える行為。
ただ、その勇気を一人で出そうとするのは簡単ではありません。
長年身についた“我慢のクセ”は、少しずつほどいていく必要があります。
カウンセリングは、その“ほどく作業”を安心して行える場所です。
誰かに話すことで、自分の中の感情が整理され、思考が整い、無理のないペースで変化が始まります。
「どうすればいい人をやめられるか」ではなく、「どうすれば自分を大切にできるか」。
その視点を一緒に見つけていくことが、心を軽くしていく第一歩です。
もし今、「本音を出すのが怖い」「自分の気持ちがわからない」と感じているなら、
その思いを抱えたままでも大丈夫。
話すことで少しずつ、自分の中のやさしさを“自分にも向ける方法”が見えてきます。
焦らず、誰かと一緒に心のペースを取り戻していきましょう。


を軽くする方法-150x150.avif)


