回避型愛着と自己肯定感の低さ:安心できる関係を築くためにできること
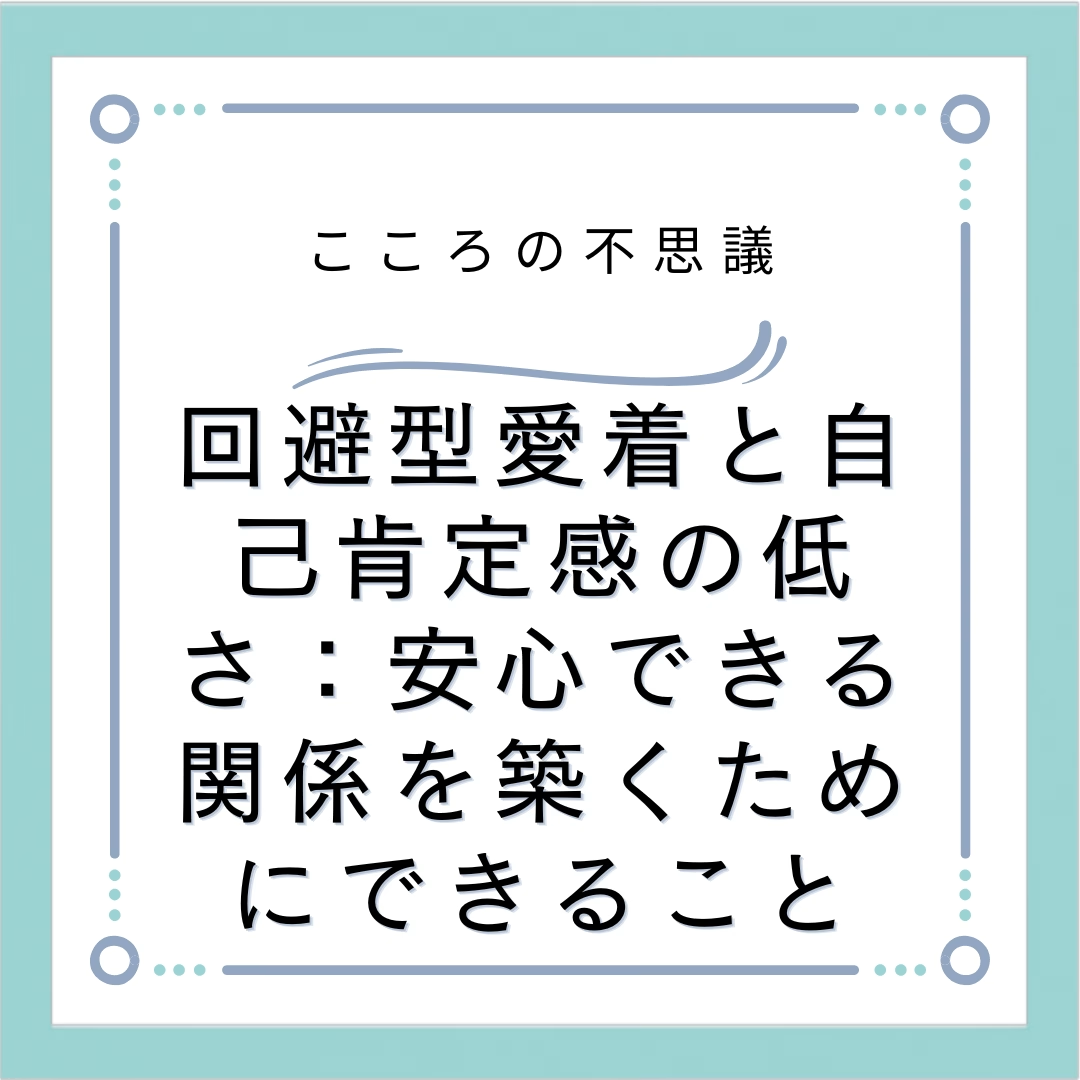
人との関係で「近づきすぎると息苦しい」「距離を置くと安心する」という感覚を持つ方は少なくありません。これは心理学でいう「回避型愛着」の特徴のひとつです。相手に心を開きたい気持ちはあるのに、実際には「拒絶されたらどうしよう」「弱みを見せると嫌われるかも」といった不安が先に立ち、結果として距離をとってしまうことがあります。
さらに、その背景には「自分には価値がないのでは」「愛される自信がない」といった自己肯定感の低さが関係していることも多く見られます。こうした思い込みは、安心できる関係を築きたいという願いとは裏腹に、孤独感や不安を強めてしまう原因になりがちです。
しかし、愛着のパターンや自己肯定感は生まれつき決まっているわけではなく、後からでも見直していける柔軟なものです。日常の小さな意識の変化や、安心できる体験を積み重ねることで、少しずつ「信頼できるつながり」を育むことは可能です。ここでは、回避型愛着と自己肯定感の低さに向き合いながら、安心できる関係を築くためにできる工夫について考えていきましょう。
一人で悩まないで:回避型愛着に向き合った5人の電話カウンセリング事例
回避型愛着について教えてください。
回避型愛着は、人間関係において近づきすぎると息苦しさを感じ、距離を置くことで安心感を得る傾向がある心理的特徴です。これは、相手に心を開きたい気持ちと不安との間で揺れる状態を指します。
なぜ自己肯定感が低いと、回避型愛着になりやすいのですか?
自己肯定感が低いと、自分には価値がないと感じたり愛される自信が持てなくなったりします。このような思い込みが原因で、安心できる関係を築くことが難しくなり、回避的な態度をとることにつながることがあります。
回避型愛着や自己肯定感は変えることができますか?
はい、回避型愛着や自己肯定感は後からでも見直すことができる柔軟なものであり、意識的な努力や安心できる経験を積み重ねることで、信頼できる人間関係を育むことが可能です。
安心できる関係を築くためにはどのような工夫が必要ですか?
日常の小さな意識の変化や、安心できる体験を通じて、自分自身の感情や不安に向き合い、段階的に信頼関係を築いていくことが効果的です。
回避型愛着や自己肯定感の低さに悩む場合、どうしたらよいですか?
専門のカウンセリングや心理サポートを受けたり、自分自身の内面に向き合う時間を持ったりすることが助けになります。特に、一人で悩まず、相談できる環境を見つけることが重要です。
投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー
-
【経歴】
・キャリアカウンセラー15年
・心理カウンセラー10年
※相談件数10,000件以上
【主な相談内容】
1.ストレス管理とメンタルケア
・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。
・仕事や家庭でのストレス解消法。
2.自己理解と自己成長
・自己肯定感を高めたい。
・自分の強みや価値観を明確にしたい。
3.人間関係の悩み
・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。
・対人関係における不安や緊張感への対処法。
4.不安や恐怖の克服
・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。
・パニック障害や全般性不安障害のケア。
5.うつ症状や気分の浮き沈み
・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。
・抑うつ状態から抜け出したい。
6.人生の転機や変化への対応
・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。
・新しい環境への不安や戸惑い。
7.恋愛や夫婦関係の悩み
・パートナーシップの問題解決。
・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。
8.自己批判やネガティブ思考の改善
・自分を責めすぎる傾向を変えたい。
・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。
9.家族関係や親子間の問題
・子育ての悩み。
・親や家族との関係性の見直し。
10.生きる意味や自己実現の探求
・人生の目的を再確認したい。
・自分らしい生き方を見つけるサポート。
【アプローチ方法】
1.傾聴を重視したカウンセリング
・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。
・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。
2.クライアント中心療法
・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。
・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。
3.認知行動療法(CBT)
・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。
・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。
4.ナラティブセラピー
・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。
・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。
5.対話を通じた柔軟なサポート
・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。
・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。
最新の投稿
目次
- ○ 回避型愛着と自己肯定感の低さが人間関係に与える影響
- ・親密さが怖くて距離をとってしまう心理
- ・自己肯定感の低さが人間関係を不安定にする
- ・「つながりたい」と「避けたい」が同時に存在する矛盾
- ○ なぜ回避型愛着と自己肯定感の低さが生まれるのか?原因と背景
- ・幼少期の親子関係が与える影響
- ・成功体験よりも失敗体験が心に残りやすい
- ・過去の人間関係や恋愛経験の影響
- ○ 回避型愛着と自己肯定感を改善するための具体的なステップ
- ・自分のパターンを理解する
- ・小さな成功体験を積み重ねる
- ・信頼できる人に気持ちを伝える練習
- ○ 安心できる関係を築くために大切な心の習慣
- ・自己否定に気づいたらやさしい言葉をかける
- ・小さな喜びや感謝を見つける習慣
- ・信頼できる人との関係を大切にする
- ○ 回避型愛着と自己肯定感の改善にはカウンセリングが効果的です
回避型愛着と自己肯定感の低さが人間関係に与える影響

人との関係で「なぜか心の距離を感じる」「うまく甘えられない」と悩む人は少なくありません。回避型愛着を持つ人は、相手と親密になると安心よりも不安を感じやすく、「これ以上踏み込まれると息苦しい」と感じてしまうことがあります。そのため、せっかく信頼関係を築きたいのに、自分から距離をとってしまい、結果として孤独感や疎外感を強めてしまうのです。
さらに、この背景には「自分には価値がないのでは」「どうせ愛されない」といった自己肯定感の低さが関係していることがよくあります。自分に自信がないと、相手の何気ない態度も「拒絶されたのかもしれない」と不安に感じ、関係を深めることが怖くなってしまうのです。
このように、回避型愛着と自己肯定感の低さは、人間関係に悪循環を生みやすい組み合わせといえます。しかし、これは性格の欠点ではなく、これまでの経験によって身についた「心の癖」のようなもの。気づきと工夫次第で、少しずつ安心できるつながりを育むことは可能です。ここからは、この問題がどのように日常の人間関係に表れるのかを、具体的に見ていきましょう。
親密さが怖くて距離をとってしまう心理
回避型愛着の人は、親しい関係を持つこと自体は望んでいます。けれども、いざ相手が近づいてくると「自分の弱さを知られるのでは」「期待に応えられなかったら嫌われるかも」といった不安が頭をよぎります。その結果、表面的には平気そうに振る舞いながらも、心の奥では緊張していて、無意識に距離を取る行動を選んでしまうのです。
例えば、恋人や友人が「もっと一緒に過ごしたい」と伝えてくれたとき、本当はうれしいのに「そんなに求められても困る」と感じてしまう。あるいは、仕事仲間や家族が「頼っていいよ」と言ってくれても、「迷惑をかけるのでは」と思って断ってしまう。こうした行動は相手からすると「拒絶された」と受け止められやすく、誤解を生んでしまいます。
この心理の裏には「親密さ=傷つきのリスク」という結びつきが隠れています。心を開いたら拒絶されるかもしれない、その不安が強いからこそ、安全策として「距離を置く」という選択をしてしまうのです。
自己肯定感の低さが人間関係を不安定にする
自己肯定感が低い人は、他人との関わりを通しても安心感を得にくい傾向があります。「自分は愛されるに値しない」という思い込みがあるため、相手のちょっとした反応を過敏に解釈してしまうのです。たとえば、返事が遅いだけで「嫌われたのかも」と感じたり、忙しいと言われただけで「必要とされていない」と落ち込んでしまうこともあります。
本来であれば相手の都合や状況に過ぎないことも、自分への否定として受け取ってしまうと、人間関係はどんどん不安定になります。相手を信じられずに疑ってしまい、さらに自分を責める…そんな悪循環が繰り返されてしまうのです。
ただし、これは「心が弱いから」ではなく、これまでの経験から身についた「思考の癖」にすぎません。自分にダメ出しをする癖に気づき、少しずつ「大丈夫だ」と思える感覚を育てていくことが、関係を安定させる第一歩になります。
「つながりたい」と「避けたい」が同時に存在する矛盾
回避型愛着と自己肯定感の低さを抱えている人の心の中には、「人とつながりたい気持ち」と「傷つきたくない気持ち」が同時に存在しています。だからこそ、親密になると嬉しさと不安が入り混じり、気持ちが揺れやすくなるのです。
この矛盾は、自分でも「どうしてこんなに面倒なんだろう」と感じるかもしれません。しかし、実際にはとても自然な心理反応です。人は誰しも孤独を避けたい一方で、過去の経験から「近づくと危ない」と学んでしまうことがあります。その二つの気持ちがぶつかり合うことで、結果的に人間関係がぎこちなくなってしまうのです。
重要なのは、この矛盾を否定せずに「自分の中には両方の気持ちがあるんだな」と受け止めること。白黒つけるのではなく、どちらの気持ちも認めることで、少しずつ「安心してつながるためのバランス」が見つけやすくなります。
なぜ回避型愛着と自己肯定感の低さが生まれるのか?原因と背景

回避型愛着と自己肯定感の低さは、決して「性格の欠陥」ではありません。多くの場合、幼少期からの経験や人間関係の積み重ねによって形づくられていきます。特に、親や養育者との関わりは大きな影響を与えます。たとえば「自分の気持ちを素直に伝えても受け止めてもらえなかった」「頑張らないと認めてもらえなかった」といった経験があると、人は心の奥で「自分は大切にされない」「愛されるには条件が必要だ」と思い込むようになります。
こうした思い込みは、大人になってからも人間関係の基盤となり、親密さを避ける行動や自己否定的な考えにつながります。また、学校や社会での人間関係、過去の恋愛や友人とのやりとりなども少なからず影響します。つまり、今の状態は「あなたが悪いから」ではなく、これまでの環境や体験が積み重なってできた「心の癖」なのです。
ここでは、その背景をもう少し具体的に見ていきましょう。
幼少期の親子関係が与える影響
愛着スタイルの土台は、子ども時代の親子関係に強く影響を受けます。親が常に温かく受け止め、安心感を与えてくれた場合、子どもは「自分は大切にされている」という感覚を自然に育むことができます。逆に、親が忙しすぎたり、感情表現が乏しかったりすると、「自分が求めても応えてもらえない」と感じやすくなります。
この「求めても無駄」という感覚が積み重なると、心の中に「人に頼るより、自分だけで何とかした方が安全だ」という信念が生まれます。それが回避型愛着の基盤です。つまり、相手と親密になること自体が「危険」だと学習してしまうのです。
もちろん、これは親が悪かったという単純な話ではありません。当時の状況や親自身の余裕のなさも関係します。大切なのは「過去の体験が今の自分の人間関係に影響している」と気づくこと。そうした理解が、安心できる関係を築くための第一歩になります。
成功体験よりも失敗体験が心に残りやすい
自己肯定感が低くなる背景には、「失敗体験が強く記憶に残りやすい」という人間の心理があります。たとえば、テストで良い点を取って褒められたとしても、次に失敗して叱られた経験の方が強烈に残ってしまうことがあります。こうした積み重ねが「自分はダメだ」という思い込みを強めてしまうのです。
また、周囲と比べられる環境も自己肯定感を下げる要因になります。兄弟や同級生と比較されることで「自分は劣っている」と感じたり、「もっと頑張らないと認められない」というプレッシャーを背負うことになります。その結果、人に認めてもらうために無理をしたり、本音を隠したりするようになりがちです。
こうした体験は一見小さなことに思えるかもしれませんが、積み重なることで「自分には価値がない」という深い思い込みにつながっていきます。
過去の人間関係や恋愛経験の影響
大人になってからの人間関係や恋愛経験も、回避型愛着や自己肯定感に影響を与えます。たとえば、信頼していた相手に裏切られた経験があると、「どうせまた傷つく」と思い込み、心を閉ざしてしまいやすくなります。また、恋愛で「重いと言われた」「距離を置かれた」などの経験があると、「自分の気持ちは迷惑なんだ」と学習してしまうこともあります。
さらに、職場や友人関係でのトラブルも「人に頼ると面倒になる」「自分の意見は言わない方が安全」といった回避的な態度を強めるきっかけになります。これらの経験は一度で大きく変えてしまうものではなく、小さな出来事が積み重なって「人と距離を取るのが普通」という感覚を作り出すのです。
重要なのは、過去の経験が今の自分の行動や考え方を形づくっていると理解すること。過去を責めたり否定するのではなく、「そうした背景があったから今こうなっているんだ」と気づくことで、少しずつ変化のきっかけをつかむことができます。
回避型愛着と自己肯定感を改善するための具体的なステップ
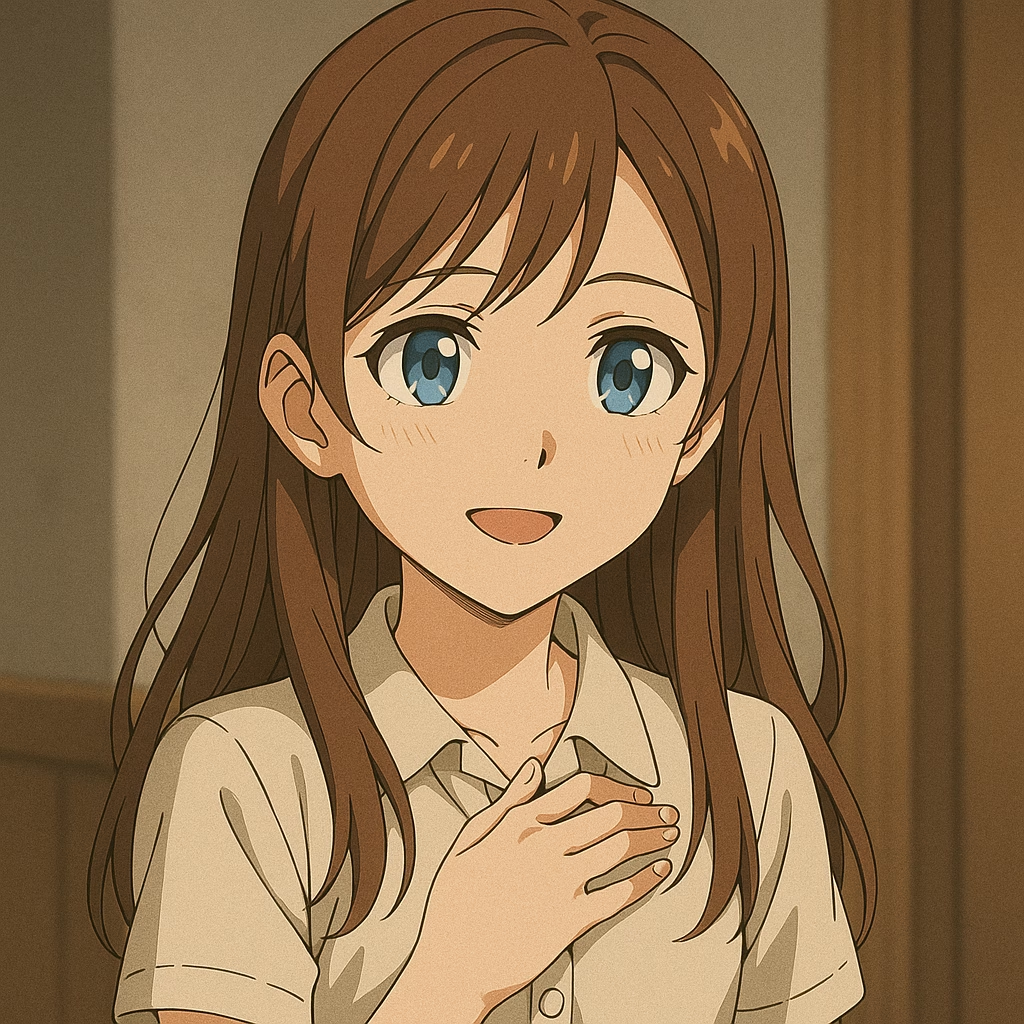
回避型愛着と自己肯定感の低さは、過去の経験から生まれた「心の癖」です。そのため、意識して行動や考え方を少しずつ変えていくことで改善していけます。大切なのは「一気に変えよう」と焦らないこと。心の仕組みは長年の積み重ねでつくられているため、ゆっくりと着実に新しい体験を積むことが効果的です。
具体的には、まず自分のパターンを理解することが第一歩です。「なぜ人との距離をとってしまうのか」「どうして自分を責めやすいのか」といった気づきがあれば、行動を少し変えやすくなります。そして次に、小さな成功体験を意識的に作ること。たとえば「今日は勇気を出して頼み事をしてみた」「不安な気持ちを言葉にできた」など、小さな一歩が積み重なって自信になります。
さらに、人に気持ちを伝える練習も大切です。いきなりすべてを打ち明けるのではなく、「これくらいなら言えそう」という範囲から始めることで安心感が育ちます。そして時には、カウンセリングや信頼できる人のサポートを得ることで、客観的に自分を見つめ直すことができます。
ここからは、具体的なステップを3つに分けてご紹介します。
自分のパターンを理解する
改善の第一歩は「気づき」です。普段の人間関係の中で「なぜか距離を置きたくなる場面」や「つい自分を責めてしまう場面」を振り返ってみましょう。ノートに書き出してみると、自分の傾向が少しずつ見えてきます。
例えば「相手に頼みごとをすると迷惑をかけると思って断ってしまう」「褒められると素直に受け取れず冗談で流してしまう」など、繰り返されるパターンに気づくことが大切です。気づくだけで「またこの癖が出ているな」と客観的に見られるようになり、少しずつ行動を変える余地が生まれます。
自己理解を深めることは、心のGPSを持つようなものです。今まで無意識に繰り返していた行動を「自分の選択」として意識できるようになると、「本当はどうしたいのか?」を考えやすくなります。これは安心できる関係を築くための土台になります。
小さな成功体験を積み重ねる
人間関係を大きく変える必要はありません。むしろ「小さな一歩」を積み重ねる方が効果的です。たとえば、普段なら「大丈夫」と言って断ってしまうところを「少し手伝ってもらえる?」と言ってみるだけでも大きな前進です。
小さな成功体験は「やってみたら意外と大丈夫だった」という安心感を積み重ねることにつながります。すると「人に頼るのも悪くない」「自分を出しても拒絶されない」という感覚が少しずつ育っていきます。
また、自分を褒める習慣を取り入れることも有効です。「今日はちゃんと伝えられた」「不安を感じても逃げなかった」など、自分の努力に気づき、言葉にして認めることで自己肯定感は自然と高まっていきます。小さな成功を軽視せず、大切にしていきましょう。
信頼できる人に気持ちを伝える練習
「気持ちを打ち明けることが怖い」という方は、いきなり大切な人に全てを話そうとせず、まずは安心できる相手に少しずつ気持ちを伝える練習をしてみましょう。たとえば「今日はちょっと疲れた」と一言だけでも立派な自己開示です。
少しずつ「本音を言っても大丈夫」という体験を重ねることで、心は安心を学んでいきます。やがて、相手との関係が深まる喜びを感じられるようになり、「距離を取らなくてもいいんだ」という感覚に変わっていきます。
もし身近に安心できる人がいない場合は、カウンセリングやサポートを利用するのも良い方法です。専門家との対話は「安心できる関係」を体験する場にもなります。その経験は日常の人間関係に活かせる大きなヒントとなります。
安心できる関係を築くために大切な心の習慣
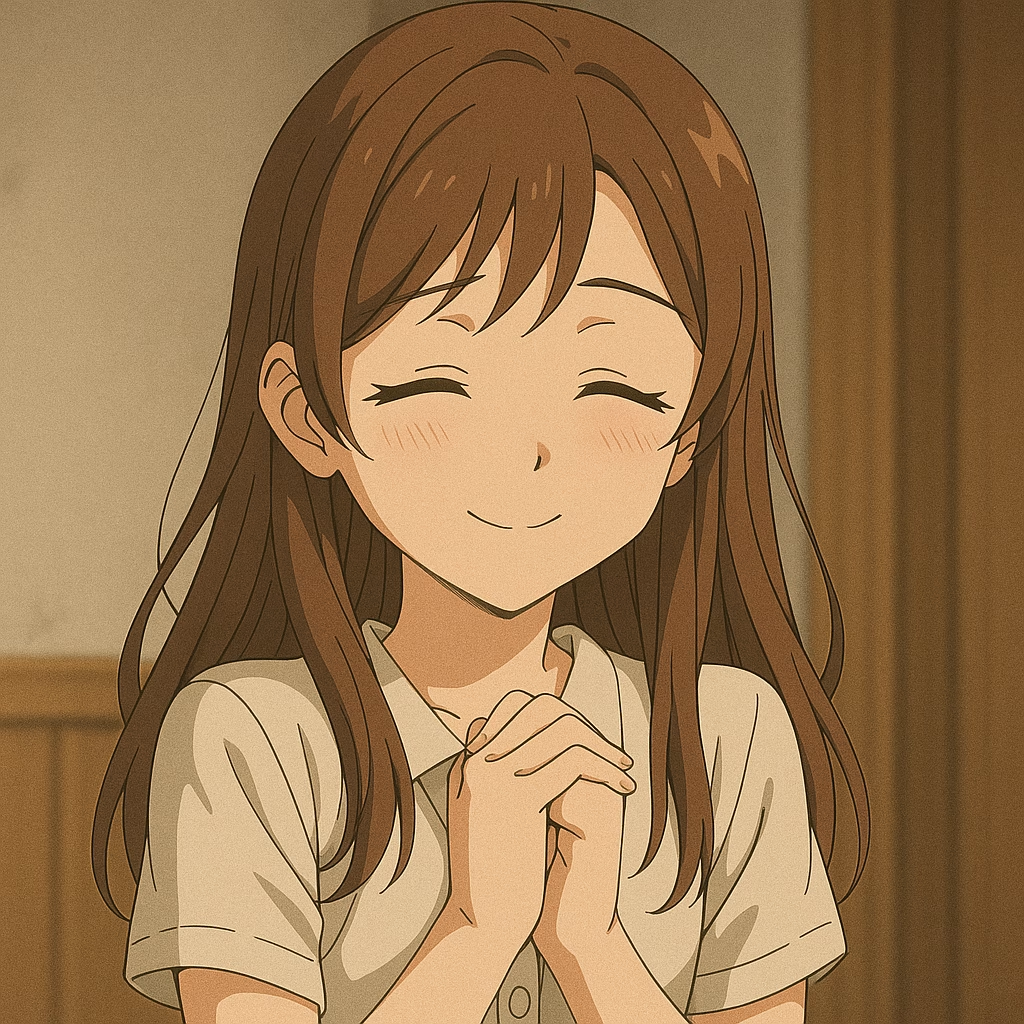
回避型愛着や自己肯定感の低さを抱えていると、人との関わりに不安を感じやすくなります。しかし、それは「一生変わらない性質」ではなく、少しずつ改善していけるものです。大切なのは、自分を責めずに「変わりたい」という気持ちを持ち続けること。そして、日常の中でできる小さな習慣を取り入れることで、心は確実に変化していきます。
安心できる関係を築くためには、まず「自分を安心させる」ことが欠かせません。自己否定の声に気づいてやさしく声をかける、頑張った自分を褒める、そして無理なく気持ちを共有できる相手を見つける…。こうした積み重ねが「自分は大丈夫」という土台を育みます。
ここでは、安心できる関係を作るために役立つ3つの心の習慣をご紹介します。
自己否定に気づいたらやさしい言葉をかける
自己肯定感が低い人は「また迷惑をかけてしまった」「やっぱり自分はダメだ」と、自分を責める言葉を無意識に繰り返してしまいます。そんなときこそ、自分にやさしい言葉をかける習慣を持つことが大切です。
たとえば、「うまくできなくても大丈夫」「今日はよく頑張ったね」といった言葉を自分に伝えるだけでも効果があります。最初は違和感があるかもしれませんが、繰り返すことで少しずつ心に染み込み、自己否定の声を和らげてくれます。
まるで小さな子どもをなぐさめるように、自分に寄り添う気持ちを持つこと。それは「安心できる関係」を築くための第一歩であり、自分自身が最初の「安心できる存在」になることでもあります。
小さな喜びや感謝を見つける習慣
安心感を育てるためには、日常の中にある「小さな喜び」や「感謝できること」に目を向けることが役立ちます。たとえば、「朝のコーヒーがおいしかった」「友達の一言で元気になれた」といった小さな出来事に意識を向けてみましょう。
この習慣は、心のバランスを整える効果があります。ネガティブな思考に偏りやすいときでも、意識的にポジティブな要素を見つけることで「自分は恵まれている部分もある」と感じられるようになるのです。
感謝の習慣は、人との関係にも良い影響を与えます。「ありがとう」と伝えることで相手との信頼関係が深まり、「安心できるつながり」を感じやすくなります。日々の中で小さな感謝を積み重ねることが、人間関係を温かくしてくれるのです。
信頼できる人との関係を大切にする
安心できる関係は、数の多さよりも「質」が大切です。無理にたくさんの人と仲良くしようとする必要はなく、「この人なら安心できる」と思える人との関係を大切にすることが重要です。
信頼できる人に少しずつ本音を伝え、理解してもらえる経験を積むことで「自分は受け入れられる存在なんだ」という感覚が強まります。それは自己肯定感を高める大きな支えになります。
また、信頼できる人との関係は、つらいときの心の避難所になります。「一人で抱え込まなくてもいい」と思えるだけで、心の余裕が生まれ、人間関係に対する不安も和らいでいきます。
信頼できる人との関係を少しずつ深めていくこと。それこそが、安心できる関係を築くための大切な土台になるのです。
回避型愛着と自己肯定感の改善にはカウンセリングが効果的です
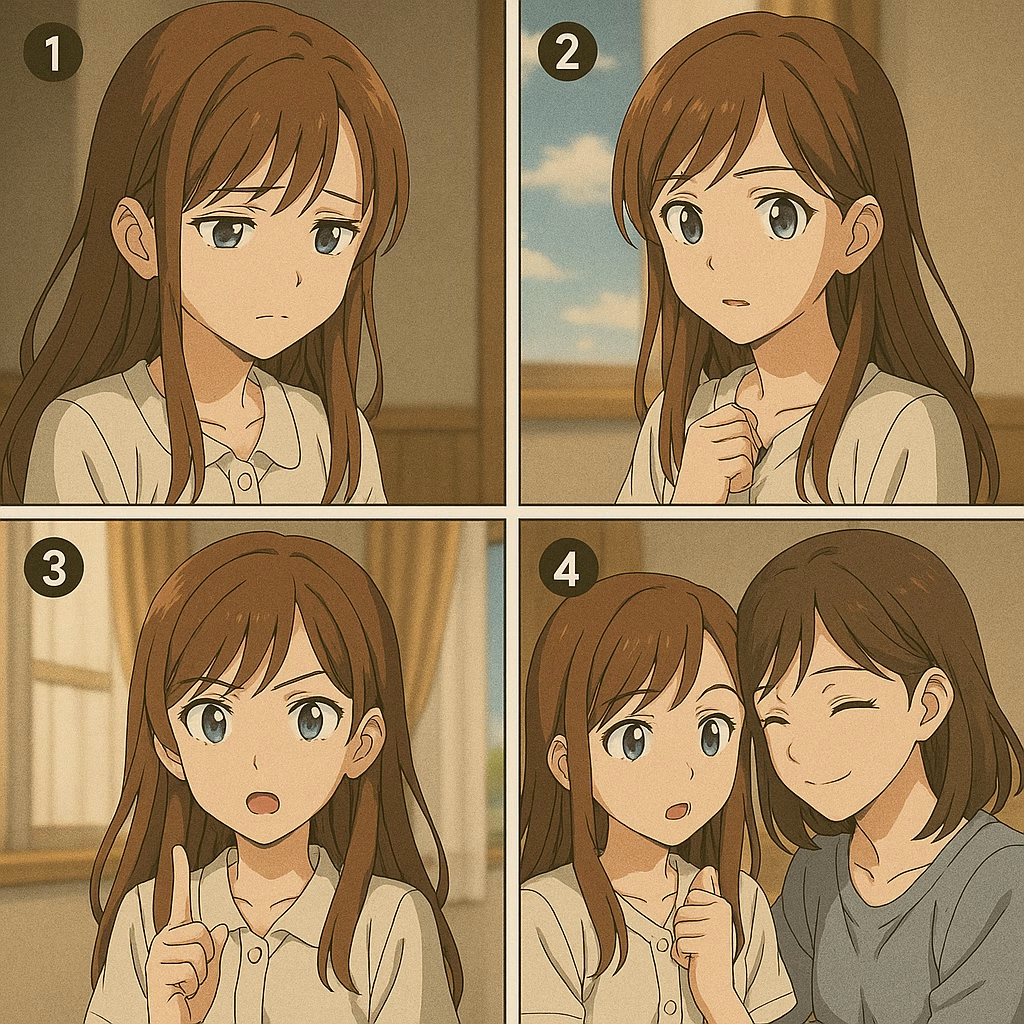
回避型愛着や自己肯定感の低さは、決してあなたの性格が弱いから起きているのではありません。これまでの環境や人間関係の中で、無意識のうちに身についた「心の癖」にすぎません。だからこそ、気づきとサポート次第で、誰でも少しずつ変わっていくことが可能です。
しかし、頭では「変わりたい」と思っても、自分ひとりで改善しようとすると行き詰まることも多いものです。「どうしても人との距離をとってしまう」「自分を認められず苦しい」という気持ちは、身近な人にさえ打ち明けにくく、孤独感を深めてしまうこともあります。そんなときに役立つのがカウンセリングです。
カウンセリングでは、安心できる対話の中で自分の気持ちを整理し、回避型愛着や自己肯定感の低さの背景を一緒に見つめていくことができます。「なぜ人を信じられないのか」「なぜ自分を責めてしまうのか」といった疑問を解きほぐしながら、少しずつ心の負担を軽くしていけるのです。
さらに、実際のカウンセリングでは、自分を大切にする習慣や、安心できる関係を築くための具体的な方法を学ぶことができます。小さな成功体験を積み重ねながら、自分自身と周囲の人との関わりに「安心」と「自信」を取り戻していくサポートを受けられるでしょう。
もし今「もっと人とつながりたい」「自分に自信を持ちたい」と思っているのなら、その気持ちこそが新しい一歩のスタートです。安心できる関係は、誰にでも築いていけるものです。まずは気軽にカウンセリングを利用してみてください。その小さな決断が、これからのあなたの人間関係や心の在り方を大きく変えるきっかけになるはずです。


を軽くする方法-150x150.avif)


