自己肯定感が低い人が抱えがちな“幼少期の刷り込み”とは
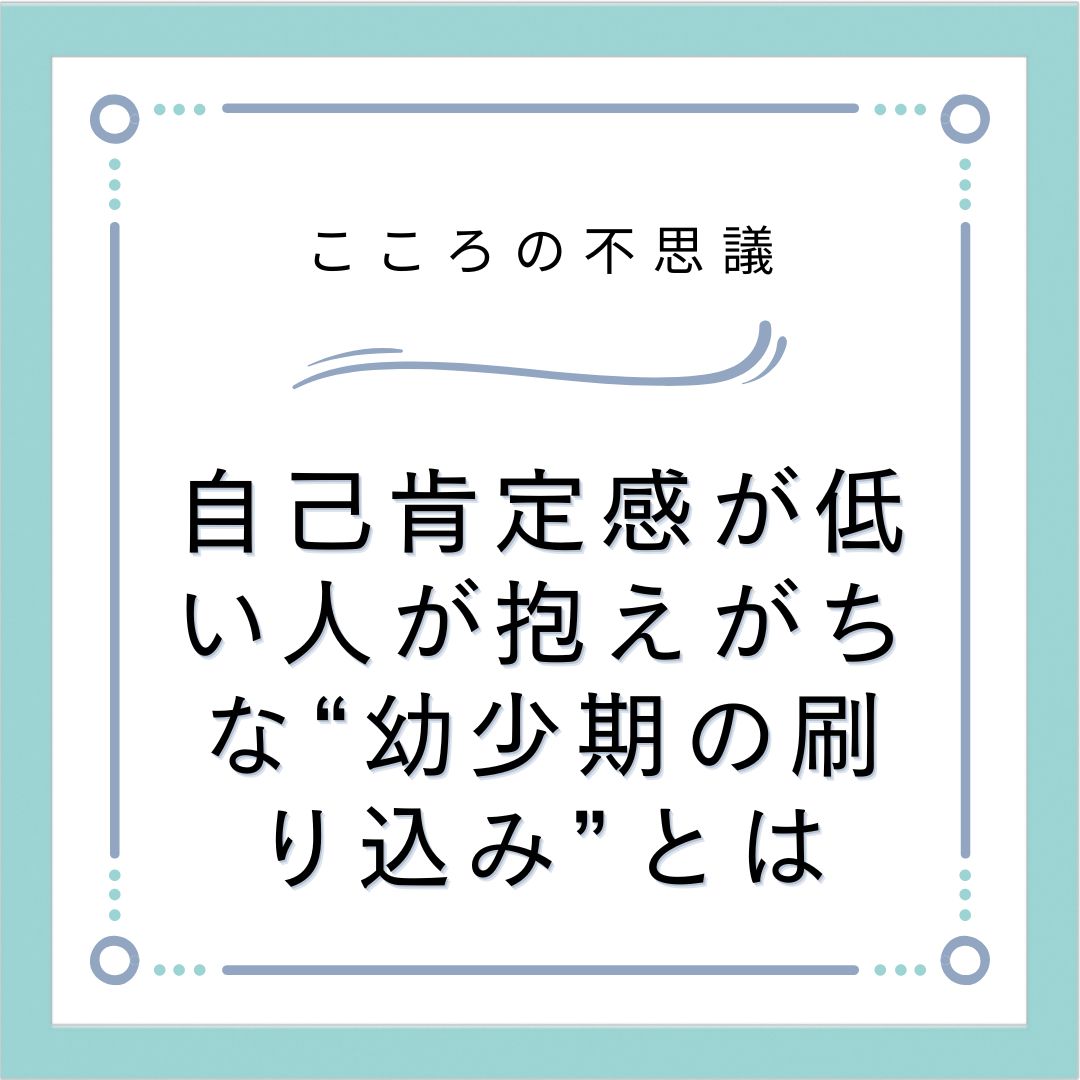
「なんで自分はこんなに自信がないんだろう…」そんなふうに感じたことはありませんか?仕事や人間関係、恋愛の場面で、自分の価値を信じられなかったり、ちょっとした失敗で「自分はダメだ」と思い込んでしまったりする——それは、もしかすると幼い頃に受けた“ある刷り込み”が影響しているかもしれません。特に、「いい子でいないと」「失敗しちゃいけない」といったメッセージを家庭の中で受け続けていた人は、大人になってからも自己肯定感を持ちにくくなる傾向があります。今回は、自己肯定感が低くなる背景にある「幼少期の刷り込み」について、わかりやすく紐解いていきます。
幼少期の刷り込みが自己肯定感に与える影響は何ですか?
幼少期に家庭環境で受けた「いい子でいないと」「失敗してはいけない」といったメッセージが、成人後に自己肯定感の低下に影響することがあります。これらの刷り込みは、自分の価値を信じることや間違いを許容する心の土台を弱める可能性があります。
自己肯定感が低いとどのような影響がありますか?
自己肯定感が低いと、仕事や人間関係、恋愛などさまざまな場面で自分の価値を認めることが難しくなり、結果的に自己信頼の不足や avoidance 行動、ネガティブな思考に陥ることが多くなります。
家庭の中で受けたメッセージが自己肯定感に影響する理由は何ですか?
家庭は子供の心理的基盤を形成する場所であり、親からのメッセージは無意識のうちに自己像や価値観を形成します。特に「いい子を維持する」「失敗を避ける」といった制約は、自己肯定感を妨げる要因となり得ます。
どのようにして幼少期の刷り込みを克服できるのでしょうか?
幼少期の刷り込みを克服するには、自己理解を深めることや、専門的なカウンセリングを受けることにより、ネガティブな思い込みを見直し、自己肯定感を育むための具体的な方法や思考パターンを学ぶことが有効です。
自己肯定感を高めるために一般的に推奨される方法は何ですか?
自己肯定感を高めるには、自分の良い点に焦点を当てたり、小さな成功体験を積み重ねること、ポジティブな自己対話を行うことなどが推奨されます。また、専門のカウンセリングや自己啓発の書籍も役立ちます。
投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー
-
【経歴】
・キャリアカウンセラー15年
・心理カウンセラー10年
※相談件数10,000件以上
【主な相談内容】
1.ストレス管理とメンタルケア
・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。
・仕事や家庭でのストレス解消法。
2.自己理解と自己成長
・自己肯定感を高めたい。
・自分の強みや価値観を明確にしたい。
3.人間関係の悩み
・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。
・対人関係における不安や緊張感への対処法。
4.不安や恐怖の克服
・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。
・パニック障害や全般性不安障害のケア。
5.うつ症状や気分の浮き沈み
・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。
・抑うつ状態から抜け出したい。
6.人生の転機や変化への対応
・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。
・新しい環境への不安や戸惑い。
7.恋愛や夫婦関係の悩み
・パートナーシップの問題解決。
・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。
8.自己批判やネガティブ思考の改善
・自分を責めすぎる傾向を変えたい。
・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。
9.家族関係や親子間の問題
・子育ての悩み。
・親や家族との関係性の見直し。
10.生きる意味や自己実現の探求
・人生の目的を再確認したい。
・自分らしい生き方を見つけるサポート。
【アプローチ方法】
1.傾聴を重視したカウンセリング
・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。
・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。
2.クライアント中心療法
・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。
・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。
3.認知行動療法(CBT)
・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。
・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。
4.ナラティブセラピー
・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。
・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。
5.対話を通じた柔軟なサポート
・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。
・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。
最新の投稿
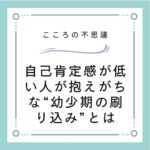 電話カウンセリング2025年7月15日自己肯定感が低い人が抱えがちな“幼少期の刷り込み”とは
電話カウンセリング2025年7月15日自己肯定感が低い人が抱えがちな“幼少期の刷り込み”とは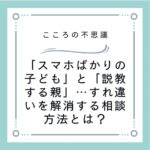 電話カウンセリング2025年7月10日「スマホばかりの子ども」と「説教する親」…すれ違いを解消する相談方法とは?
電話カウンセリング2025年7月10日「スマホばかりの子ども」と「説教する親」…すれ違いを解消する相談方法とは?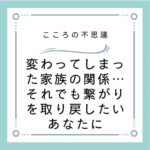 電話カウンセリング2025年7月8日変わってしまった家族の関係…それでも繋がりを取り戻したいあなたに
電話カウンセリング2025年7月8日変わってしまった家族の関係…それでも繋がりを取り戻したいあなたに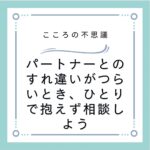 電話カウンセリング2025年7月7日パートナーとのすれ違いがつらいとき、ひとりで抱えず相談しよう
電話カウンセリング2025年7月7日パートナーとのすれ違いがつらいとき、ひとりで抱えず相談しよう
目次
- ○ 「いい子」でいなければ、愛されないと思っていた
- ・条件付きの愛情が「自分には価値がない」という思いを作る
- ・失敗に対する過剰な恐れがチャレンジを妨げる
- ・親の期待が「他人軸」で生きる習慣を作る
- ○ 大人になっても続く「いい子」の呪縛
- ・他人に頼ることができないのは、自立しすぎた子どもの名残かも
- ・自分を責める癖は、昔の「条件付きの愛」の延長線上
- ・人の期待に応えすぎて、自分の気持ちがわからなくなる
- ○ 「刷り込み」に気づいたら、変化は始まる
- ・まずは「そう思っても仕方なかったよね」と過去の自分をねぎらう
- ・今感じている「本音」に耳を傾けてみる
- ・「できない自分」も含めて肯定する練習をする
- ○ 「私は私でいい」と思える未来のために
- ・「心地よい自分」でいられる時間を増やしていこう
- ・誰かと比べそうになったら「過去の自分」と比べてみる
- ・「自分を大切にすること」が他人との関係も変えていく
- ○ 🌿 「そのままの自分でも、大丈夫」そう思える心を一緒に育てていきませんか? 🌿
「いい子」でいなければ、愛されないと思っていた
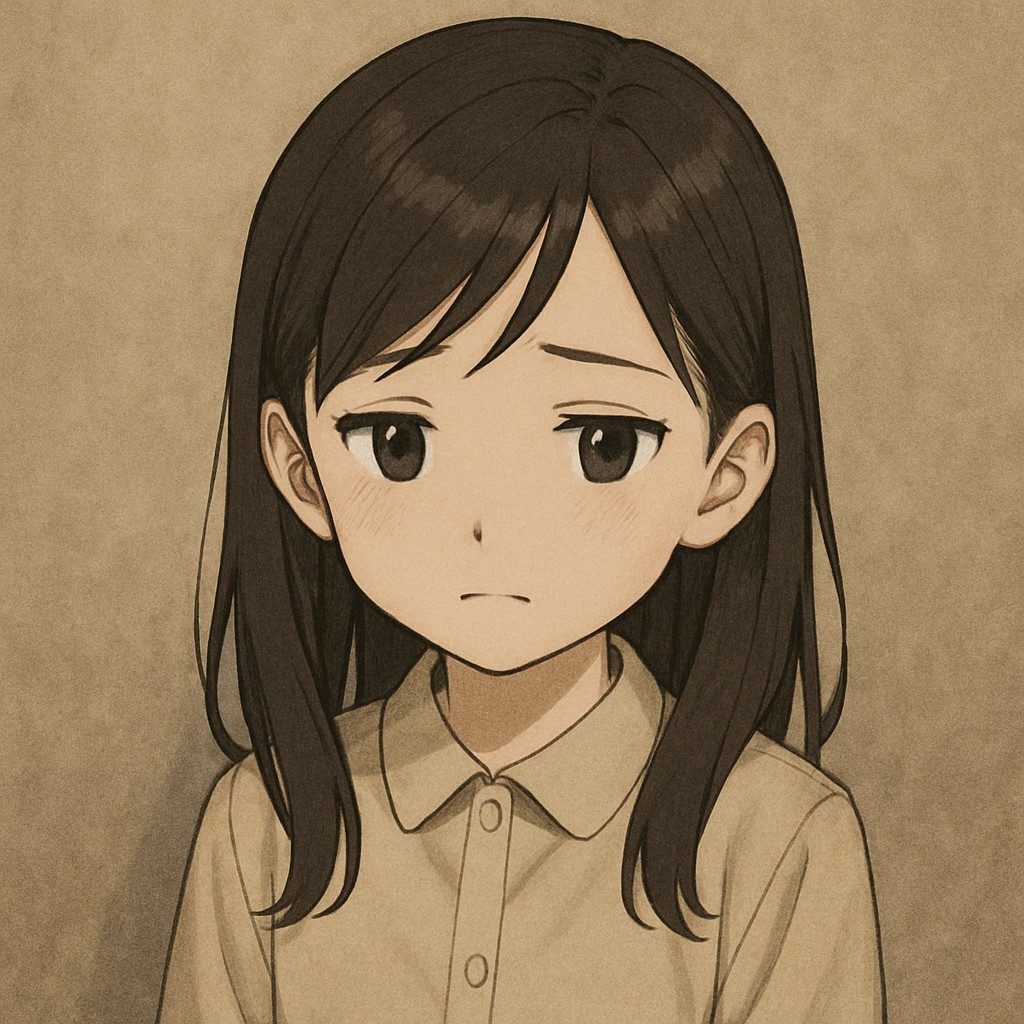
「もっと頑張りなさい」「そんなことじゃダメでしょ」「どうしてできないの?」——小さい頃、こんな言葉をよく聞いていたという方はいませんか?
子どもにとって、親や大人の言葉は絶対的なものであり、心の奥深くに強く刻まれます。「ちゃんとしていないと怒られる」「いい子でいないと愛されない」そんな思い込みが、知らず知らずのうちに刷り込まれていくのです。
その刷り込みは、自分に対する見方や他人との関わり方に影響を与えます。大人になってからも「失敗=価値がない」「頑張らないと認められない」といった思考のクセとなり、自己肯定感を持ちにくくしてしまうのです。
自己肯定感が低いと、自分を信じられなかったり、人からの評価に過敏になったりします。「ありのままの自分でいい」と思えないため、常に他人の目を気にし、無理をしてしまうことも少なくありません。
では、そんな“刷り込み”はどのように私たちの中に根づいていくのでしょうか?以下では、幼少期の体験がどのように影響しているのかを具体的に見ていきます。
条件付きの愛情が「自分には価値がない」という思いを作る
「いい子にしていたときだけ褒められた」「成績が良いときだけ親が機嫌が良かった」——そんな体験をしていた人は、親の愛情が“条件付き”に感じられていたかもしれません。
このような体験は、「自分はそのままでは愛されない」という思いを生み出します。たとえば、泣いたときに「泣くんじゃない!」と叱られたり、失敗したときに「ちゃんとやりなさい!」と強く責められたりすると、子どもは「感情を出しちゃいけない」「完璧じゃないと受け入れてもらえない」と学んでしまいます。
本来、愛情は無条件であるべきものです。けれども、家庭内で「○○できたらOK」「○○しなかったらダメ」といったやり取りが続くと、子どもは自分の存在価値を条件に結びつけてしまうのです。
こうして育った人は、大人になってからも常に自分にプレッシャーをかけ続け、「頑張らないと愛されない」と思い込み、心が休まることがなくなります。
失敗に対する過剰な恐れがチャレンジを妨げる
「一度でもミスしたら怒られる」「失敗すると責められる」——そんな経験を繰り返していた人は、自然と「失敗=自分の否定」と捉えるようになります。
大人になってからも、「完璧じゃないといけない」「間違えてはいけない」と思い込み、なかなか新しいことに挑戦できなくなってしまいます。
本来、失敗は学びの一部であり、成長にとって必要なものです。けれども、子どもの頃に「失敗=罰」として扱われてしまうと、失敗そのものが怖くなります。
その結果、「やってみたいけど怖い」「どうせうまくいかないからやめておこう」といった思考に陥り、可能性を狭めてしまうのです。
このような恐れは、自己肯定感をさらに下げてしまいます。「挑戦できない自分はダメだ」と感じ、負のループにはまってしまうのです。まずは「失敗しても大丈夫」という感覚を少しずつ取り戻していくことが、自己肯定感の回復への第一歩になります。
親の期待が「他人軸」で生きる習慣を作る
親から「こうしなさい」「ああしなさい」と常に指示され、自分の意見を尊重してもらえなかった経験はありませんか?
そのような環境では、「自分で考えて決める力」が育ちにくくなります。代わりに「どうしたら怒られないか」「どうしたら喜んでもらえるか」という“他人の期待”に合わせて動く癖がついてしまいます。
大人になってからも、周囲の目を気にしすぎたり、相手に合わせすぎて疲れてしまったりするのは、この“他人軸”の影響かもしれません。
本来、人生は自分の価値観で歩むものですが、幼少期に「親の期待=正解」という刷り込みが強いと、「自分がどうしたいか」がわからなくなってしまうのです。
他人の期待ばかりを気にしていると、自分の本心を見失い、自信を持つことも難しくなります。少しずつ「自分の気持ち」を大切にする時間を増やしていくことで、自己肯定感を育て直すことができるのです。
大人になっても続く「いい子」の呪縛
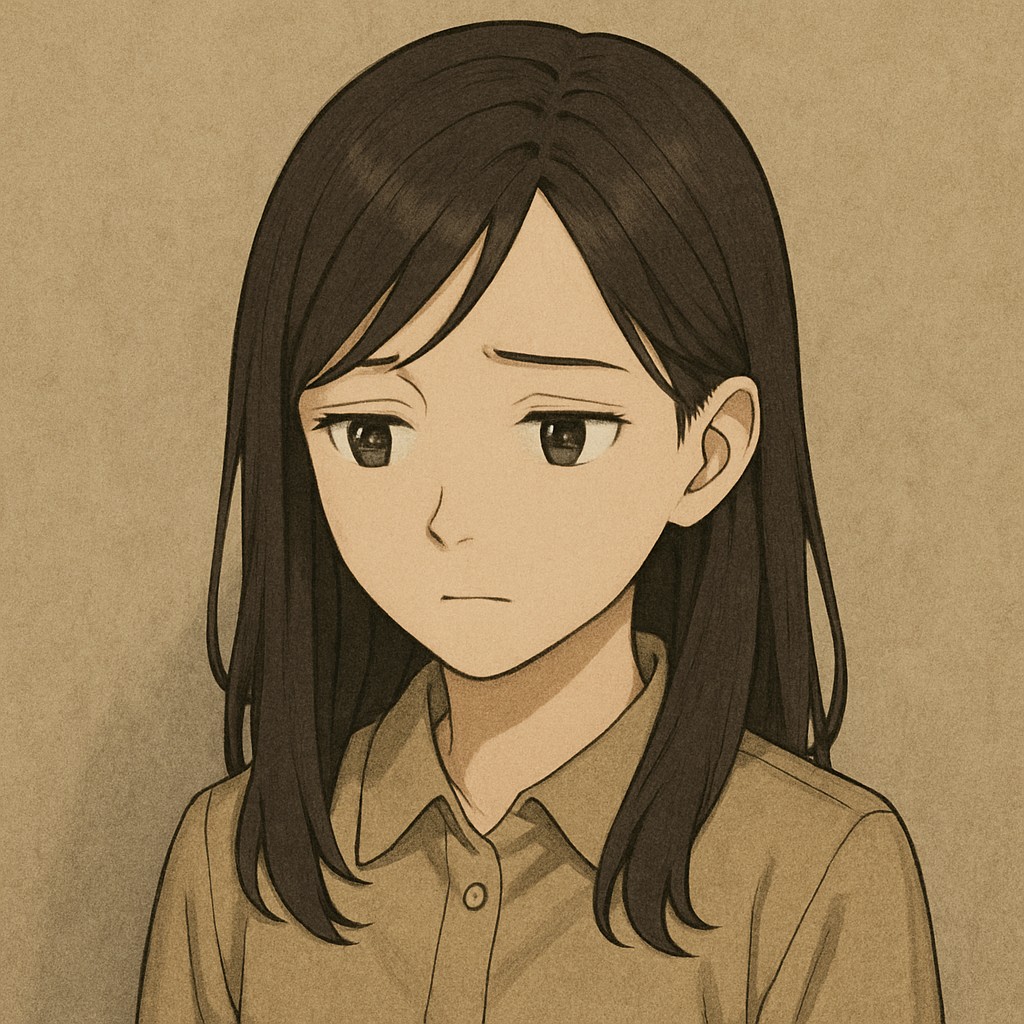
子どもの頃に身についた思い込みは、大人になった今も私たちの行動や考え方に大きな影響を与えています。とくに「いい子でいなきゃ」「頑張らないと認められない」といった刷り込みは、自分を追い詰めたり、人との距離感に悩んだりする原因になりやすいのです。
たとえば、人に頼れなかったり、自分の失敗を過剰に責めてしまったり、周囲の期待に応えようと無理をしすぎたり——これらは一見、性格の問題のように思えますが、実は過去の家庭環境の影響が色濃く残っているケースも多いのです。
「もう大人なんだから、自分で変えられる」と思っても、心の奥にこびりついた価値観はそう簡単には手放せません。でも、まずはそれに「気づく」ことが、変化の第一歩になります。
ここでは、幼少期の刷り込みが今の自分にどう影響しているのかを、さらに深掘りしていきます。
他人に頼ることができないのは、自立しすぎた子どもの名残かも
「人に迷惑をかけちゃいけない」「自分のことは自分でなんとかしないと」そんな思いを強く持っている人はいませんか? それは、幼い頃から過度に“しっかり者”でいることを求められていた名残かもしれません。
たとえば、親が忙しかったり、家庭内で感情を出すことが許されなかったりすると、子どもは無意識に「自分の気持ちは後回しにしなきゃ」と思うようになります。そして、感情を抑えて大人のように振る舞うことが「正しい」と思い込んでしまうのです。
大人になった今でも、「助けて」が言えなかったり、疲れているのに頑張り続けてしまうのは、自立しすぎた子ども時代の影響かもしれません。他人に頼ること=甘えではありません。むしろ、必要なときに頼れる人こそ、強さを持っているのです。
自分を責める癖は、昔の「条件付きの愛」の延長線上
ちょっとした失敗で自分を責めてしまったり、うまくいかないと「自分には価値がない」と感じてしまう——そんな思考のクセはありませんか? それは、子どもの頃に「いい結果のときだけ褒められた」経験が積み重なったことによる可能性があります。
このような家庭では、子どもは「自分は○○できたから愛される」「失敗したら愛されない」と思い込んで育っていきます。その結果、結果が出なかったり期待を裏切ったと感じたときに、自分の存在価値そのものを否定してしまうようになるのです。
本来、人の価値は結果や能力ではなく「存在そのもの」にあるはずです。それでも、「頑張らなきゃ」「できない自分はダメ」と思ってしまうのは、かつての条件付きの愛が今も心の中に生きているからかもしれません。まずは、「できない自分」も受け入れてあげることから始めてみましょう。
人の期待に応えすぎて、自分の気持ちがわからなくなる
誰かに頼まれると断れない、人の顔色を見て行動してしまう、空気を読みすぎて疲れてしまう——そんなふうに、他人の期待に合わせすぎてしまう人は多いものです。これもまた、幼少期に「親の期待に応えることで愛された」という経験の影響かもしれません。
小さい頃から「こうしなさい」「あなたは○○するべき」と言われ続けて育った人は、「自分で決める」という感覚を持ちにくくなります。そして、知らず知らずのうちに「相手が望むこと=正解」と思い込むようになります。
その結果、大人になってからも自分の気持ちがわからなくなり、「本当はどうしたいのか」が曖昧になってしまうのです。
「人のために頑張ること」は素晴らしいことですが、自分の気持ちを無視し続けていると、心がすり減ってしまいます。他人の期待を意識しすぎず、自分の感情にも耳を傾ける練習をしていきましょう。
「刷り込み」に気づいたら、変化は始まる
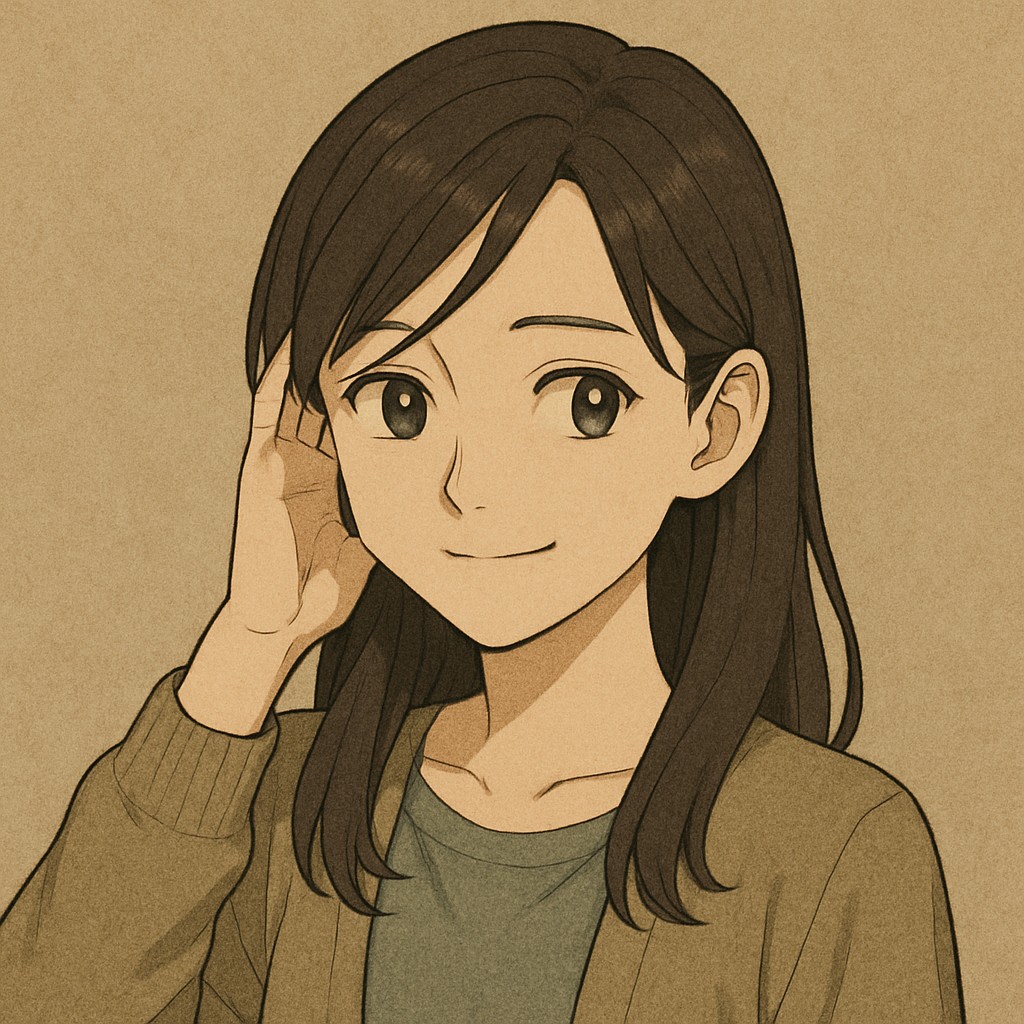
ここまで読んで、「もしかしたら自分もそうだったかもしれない」と気づいた方もいるかもしれません。そうであれば、それはとても大きな一歩です。幼少期の刷り込みというのは、無意識のうちに根づいているもの。気づかないまま「なんでうまく生きられないんだろう」「どうしていつも自分を責めてしまうんだろう」と悩んでいる人はとても多いのです。
でも、「そうか、自分は“いい子でいなきゃ”ってずっと思ってきたんだな」と気づけたときから、ゆっくりと心のあり方は変えていくことができます。自己肯定感は、生まれつきではなく「育て直せる」もの。今からでも遅くはありません。
ここからは、刷り込みに気づいたあとの向き合い方や、少しずつ自分を大切にする練習についてお話していきます。完璧じゃなくても、自分に優しく、しなやかに生きるヒントを見つけていきましょう。
まずは「そう思っても仕方なかったよね」と過去の自分をねぎらう
変わりたいと思ったときに、最初にしてほしいのは“過去の自分”への理解とねぎらいです。「なんで私はいつも自分を責めるんだろう」と悩んでいる人も、元をたどれば「そうせざるを得なかった理由」があったはず。
親に認められたかったり、怒られたくなかったり、愛されたかったり。そうした想いがあったからこそ、頑張って“いい子”を演じてきたのです。
その時の自分に「よく頑張ってきたね」「そのままで本当は十分だったよ」と声をかけてあげること。それは、自分を責める思考パターンをほぐしていく第一歩になります。
いきなりすべてを肯定するのは難しいかもしれません。でも「当時の私には、それが必要だった」と認めてあげるだけでも、心の中に少しずつ優しさが芽生えてきます。
今感じている「本音」に耳を傾けてみる
他人の期待に応えることが当たり前だった人ほど、自分の気持ちを後回しにしてしまうクセがあります。でも、それでは本当の意味で自分を大切にすることはできません。
そこで大切なのが、「今の自分は本当はどう感じているのか?」に意識を向けることです。
たとえば、「本当は疲れているのに断れない」「行きたくないけど笑顔で参加してしまう」など、日常の中に“我慢しているサイン”はたくさんあります。
そんなとき、「本当はどうしたい?」と自分に問いかけてみるだけでも、気づきが生まれます。
慣れないうちは、モヤモヤした気持ちや違和感を言葉にするのも難しいかもしれません。でも、自分の感情に関心を持ち始めるだけで、少しずつ「自分軸」が取り戻せるようになります。心の声を無視せず、素直に耳を傾ける習慣を持ちましょう。
「できない自分」も含めて肯定する練習をする
自己肯定感が低い人ほど、「頑張れている自分しか認められない」「ミスをする自分はダメ」といった思い込みを持ちがちです。
でも本当は、人間は完璧ではないからこそ魅力的で、価値があるのです。むしろ、できないことや失敗する姿を認められるようになると、自分にも他人にも優しくなれます。
たとえば、「今日は疲れて何もできなかった」と落ち込むのではなく、「そんな日もあるよね」と受け止めてあげること。これだけでも、自分に対する接し方が変わってきます。
「全部できなくても、自分は価値ある存在なんだ」と繰り返し伝えることが、自己肯定感を育てる大事な一歩なのです。
最初は違和感があるかもしれません。でも、小さな肯定の積み重ねが、やがて「私は私でいい」と思える感覚につながっていきます。焦らず、じっくり育てていきましょう。
「私は私でいい」と思える未来のために
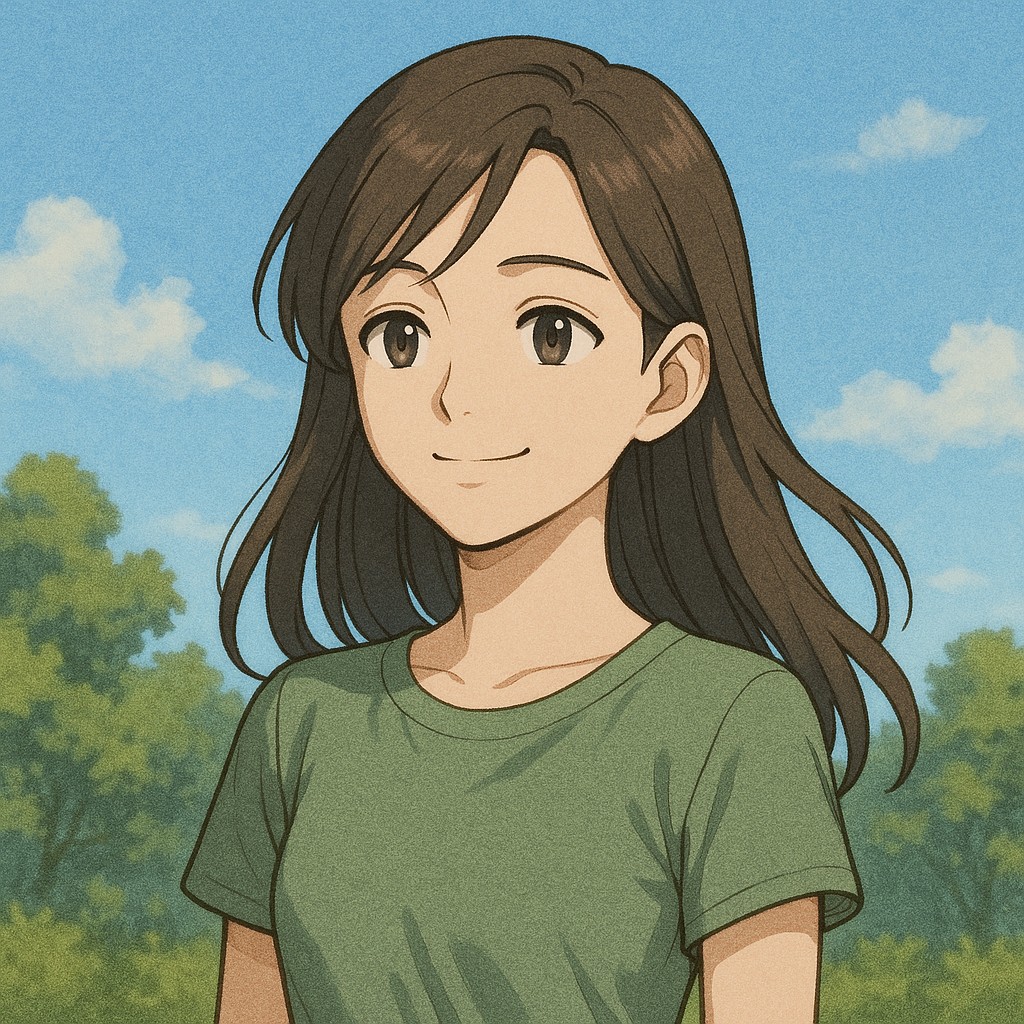
これまで紹介してきたように、自己肯定感が低くなる背景には、幼少期の刷り込みや親の期待との関係性が大きく影響しています。でも、それは「一生変えられないもの」ではありません。
むしろ、今こうして「自分を見つめてみよう」「変わりたい」と思えている時点で、心の中には確かな変化が始まっているのです。
大切なのは、完璧を目指すのではなく、「ありのままの自分を少しずつ受け入れていく」こと。日々の中で自分の気持ちに気づき、労わり、自分の味方になってあげることで、自己肯定感は少しずつ育っていきます。
人と比べなくていい。誰かの期待に応えなくてもいい。ただ「私はこれでいい」と、肩の力を抜いて生きられるようになることが、心の安定にもつながります。
ここでは、これからの日々をもっと心地よく過ごすためのヒントをお伝えしていきます。
「心地よい自分」でいられる時間を増やしていこう
自己肯定感を育てていくうえで大切なのは、自分が安心できる環境や時間を意識的に作っていくことです。
たとえば、誰にも気を使わなくていい時間を過ごす、趣味に没頭する、気の合う友人と話す——そんなひとときの積み重ねが「自分はこれでいいんだ」と感じる感覚を育ててくれます。
逆に、無理に人と付き合ったり、苦手なことに無理して取り組み続けると、自信が削られていってしまいます。まずは「心地よくいられる状態」を自分自身に許してあげましょう。
小さなことでいいんです。好きな音楽を流す、ゆっくりお茶を飲む、疲れたら何もしない。そんな一つひとつの行動が、自分を大切にする練習になります。
「頑張ること」ばかりに意識が向いていた人ほど、「くつろぐ」「力を抜く」ことが、自己肯定感の回復につながるのです。
誰かと比べそうになったら「過去の自分」と比べてみる
SNSや職場、友人関係など、私たちは日常的に“他人との比較”にさらされています。でも、他人の人生と自分の人生は比べられるものではありません。
誰かがうまくいっているように見えるとき、「あの人と比べて自分はダメだな…」と思うのではなく、「1年前の自分と比べてどうか?」と考えてみてください。
たとえば、以前はすぐに自分を責めていたけれど、最近は「まぁ、いいか」と思えることが増えた。以前よりも、人の顔色をうかがう時間が減った——それだけでも、大きな前進です。
自分の変化や成長は、外から見えづらいもの。でも、ちゃんとあなたの中で育っています。比べるなら、他人ではなく「過去の自分」と。
そうすることで、自分の歩みを肯定的に受け止められるようになり、少しずつ自信も回復していくはずです。
「自分を大切にすること」が他人との関係も変えていく
自己肯定感を高めることは、自分自身にとってだけでなく、他人との関係にも良い影響をもたらします。
なぜなら、「自分を大切にしている人」は、他人を必要以上にコントロールしようとしないし、他人の言動に振り回されることも少なくなるからです。
たとえば、自分を責めなくなったことで、人にも優しくなれるようになった。自分の気持ちを言えるようになったことで、相手との関係が対等になった——そんな変化が少しずつ現れてきます。
人との境界線がしっかりすると、無理な我慢や過剰な気遣いも減り、心が楽になります。
「自分なんて…」と思っていた頃とは違い、自分を認めてあげられるようになると、人とのつながり方も自然と変わっていきます。自己肯定感を育てることは、まわりとの関係をもっと心地よくするための土台でもあるのです。
🌿 「そのままの自分でも、大丈夫」そう思える心を一緒に育てていきませんか? 🌿
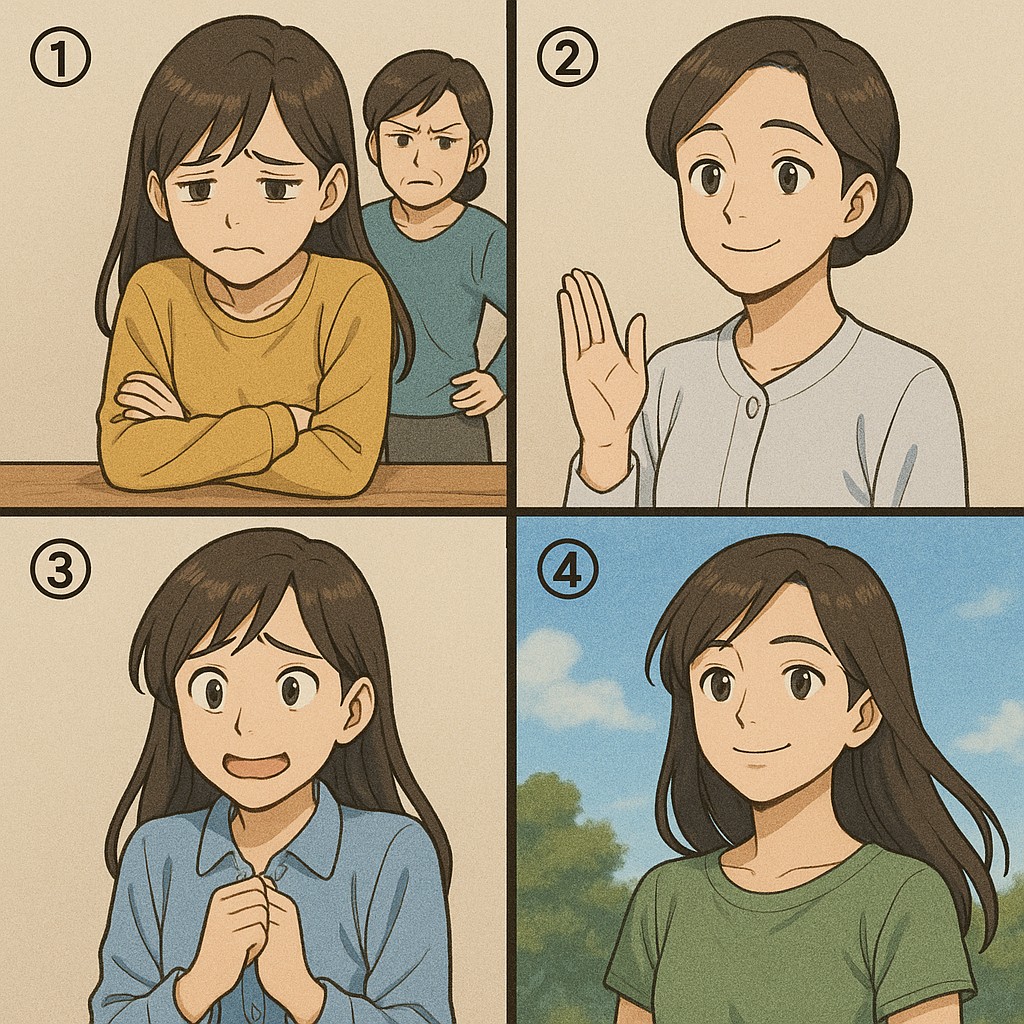
この記事を読んで、「あ、これ自分に当てはまるかも…」と感じた方へ。
もしかすると、これまでずっと無意識に、自分を責めたり、誰かの期待に応え続けたりしてきたのかもしれませんね。
でも、それはあなたが「愛されたい」「認められたい」と願って、一生懸命頑張ってきた証です。
だけど、もうひとりで頑張りすぎなくても大丈夫。
自分の気持ちに耳を傾けながら、過去の傷や思い込みをゆっくりとほどいていくことで、
🌱 「私は私でいい」と思える感覚を少しずつ取り戻していくことができます。
💬 カウンセリングでは、あなたのペースで話すことができます。
どんな感情も否定せず、そっと受け止めながら、心の奥にある本音を一緒に見つけていきます。
🧡「自分に優しくなりたい」
💡「人の目を気にせず、自分らしく生きたい」
🌈「いつか“安心できる自分”に出会いたい」
そんな想いがある方は、どうぞ一度ご相談ください。
✨ 心の荷物を少しずつ下ろしていく場所として、
あなたをお待ちしています。

