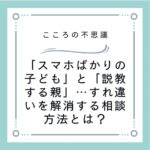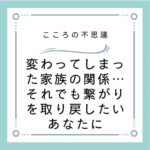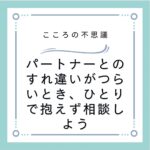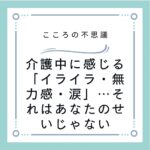「スマホばかりの子ども」と「説教する親」…すれ違いを解消する相談方法とは?
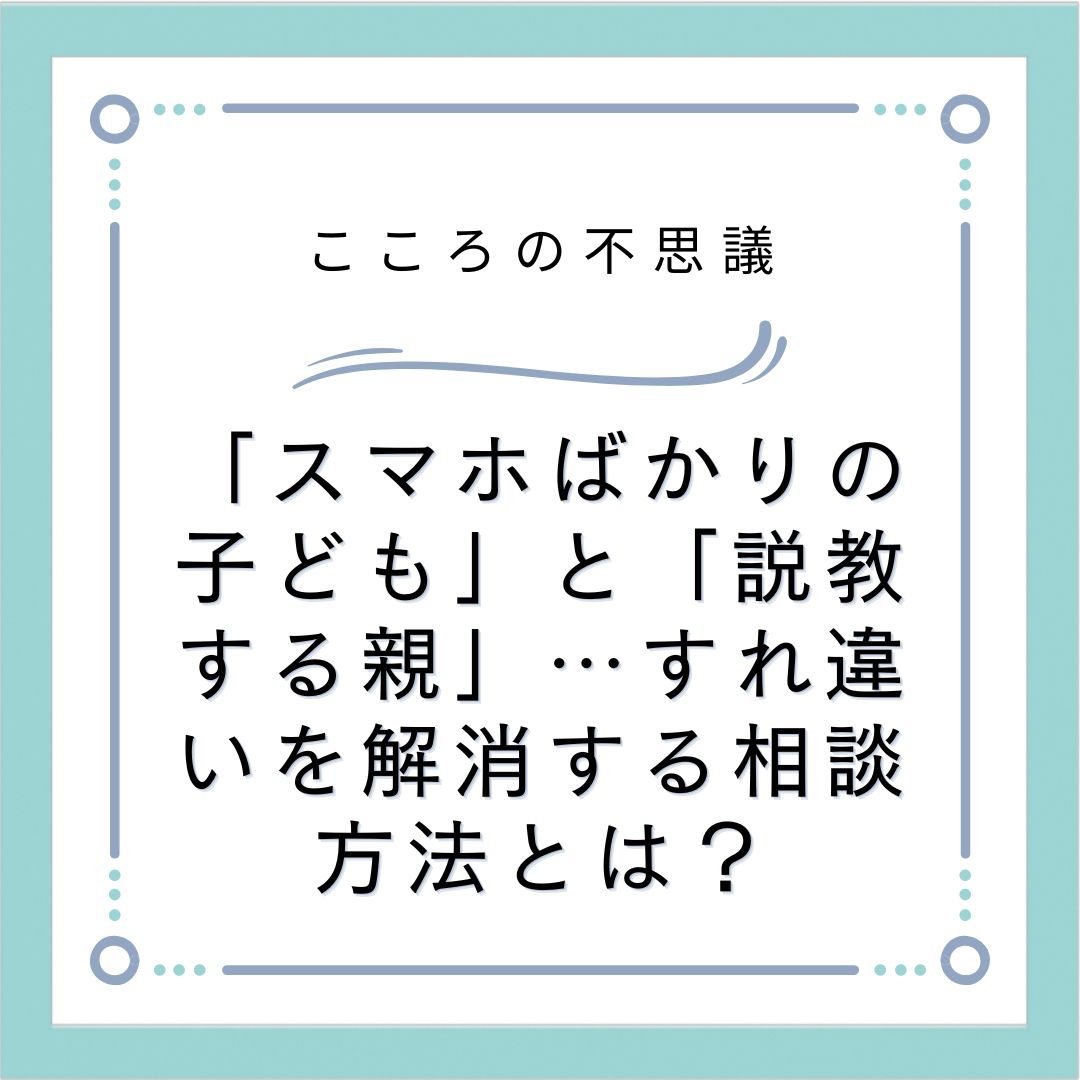
「うちの子、最近ずっとスマホばっかり見てて…」「話しかけても返事がないし、つい怒っちゃうんです」。そんな親御さんの声を、日常的に耳にするようになりました。一方で、子どもたちにも「何でもかんでも説教されるから話したくない」「自分の世界を邪魔されたくない」という本音があるのも事実。親と子の間で起きているすれ違いは、どちらが悪いという問題ではなく、価値観やコミュニケーションのズレから起こるものです。今回は、「スマホばかりの子ども」と「説教する親」の関係性に焦点をあて、対立を避けながらお互いの気持ちを理解し合う相談方法について考えていきます。
親子間の価値観のズレを解消するにはどうすれば良いですか?
価値観のズレを解消するには、相手の立場や考えを理解しようと努めることが重要です。また、対話の中でお互いの意見を尊重しながら妥協点を見つける努力も必要です。
子どもと良い関係を築くためのコミュニケーション方法は何ですか?
子どもとの良い関係を築くには、まず子どもの話をしっかりと聴くことが重要です。否定せずに共感し、子ども自身が安心して話せる環境を作ることが、信頼関係を深めるポイントです。
親子のすれ違いを防ぐためにはどうしたら良いですか?
すれ違いを防ぐには、お互いの価値観や気持ちを尊重し合うことが必要です。定期的に時間を設けて子どもと対話し、共感と理解を深める努力を続けることが、良好な関係構築に役立ちます。
子どもが話を聞いてくれず、親が怒ってしまいます。どうすれば良いですか?
親が感情的にならず、子どもとの対話の際には冷静さを保つことが大切です。子どもの気持ちを理解しようと努力し、説教ではなく、子どもの意見や気持ちを尊重したコミュニケーションを心掛けることが効果的です。
子どもがスマホばかり見ていて心配です。どのように対処すれば良いですか?
子どもがスマホに偏りすぎている場合は、親子間のコミュニケーションを改善し、共通の時間を増やすことが効果的です。子どもの気持ちに寄り添いながら、適切なルールを設定し、スマホの使用時間を管理することが重要です。
投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー
-
【経歴】
・キャリアカウンセラー15年
・心理カウンセラー10年
※相談件数10,000件以上
【主な相談内容】
1.ストレス管理とメンタルケア
・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。
・仕事や家庭でのストレス解消法。
2.自己理解と自己成長
・自己肯定感を高めたい。
・自分の強みや価値観を明確にしたい。
3.人間関係の悩み
・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。
・対人関係における不安や緊張感への対処法。
4.不安や恐怖の克服
・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。
・パニック障害や全般性不安障害のケア。
5.うつ症状や気分の浮き沈み
・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。
・抑うつ状態から抜け出したい。
6.人生の転機や変化への対応
・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。
・新しい環境への不安や戸惑い。
7.恋愛や夫婦関係の悩み
・パートナーシップの問題解決。
・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。
8.自己批判やネガティブ思考の改善
・自分を責めすぎる傾向を変えたい。
・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。
9.家族関係や親子間の問題
・子育ての悩み。
・親や家族との関係性の見直し。
10.生きる意味や自己実現の探求
・人生の目的を再確認したい。
・自分らしい生き方を見つけるサポート。
【アプローチ方法】
1.傾聴を重視したカウンセリング
・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。
・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。
2.クライアント中心療法
・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。
・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。
3.認知行動療法(CBT)
・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。
・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。
4.ナラティブセラピー
・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。
・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。
5.対話を通じた柔軟なサポート
・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。
・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。
最新の投稿
目次
- ○ 「スマホばかり見ている」それは本当に問題?
- ・スマホは「逃げ場」じゃなく「安心できる場所」かも?
- ・「またスマホ?」ではなく「今日は何見てるの?」と聞いてみる
- ・子どもの心に届くのは「共感」から始まる言葉
- ○ 「伝わらない」には理由がある:親子のすれ違いの正体
- ・言葉よりも“温度感”が大事
- ・親の「べき」に子どもは疲れている
- ・「失敗させたくない」は親の不安かも?
- ○ 対話を「習慣」にする:親子関係を深めるための新しいアプローチ
- ・1日1回、たわいもない話をする時間をつくる
- ・ルールは一緒に決めると納得しやすい
- ・「わからない」でOKを出す勇気を持とう
- ○ 「わかり合おう」とする姿勢が、親子の関係を変えていく
- ・「今だけの関係性」ではなく「これからの信頼」を意識する
- ・大切なのは「正しさ」よりも「つながり」
- ・「親だって迷っていい」と伝えることで、子も自分を許せる
- ○ 🌱 「わかってほしい」気持ちも、「どうしたらいいかわからない」気持ちも、大切なサインです。
「スマホばかり見ている」それは本当に問題?

子どもがずっとスマホを見ていると、つい親として不安になりますよね。「何をそんなに見てるの?」「勉強しないで大丈夫?」「目が悪くなるよ」…気づけば、毎日のように注意や小言を言ってしまっている、というご家庭も少なくありません。でも、実はその「スマホばかり」という行動の裏側には、子どもなりの理由や感情があることも多いのです。そして、その行動をどう受け止めるかで、親子関係のあり方が大きく変わってきます。
一方で、注意された子どもは「また怒られた」「自分の気持ちはわかってもらえない」と感じ、ますます親との距離を取るようになってしまうことも…。こうして、親の「心配」と子どもの「自分を守りたい気持ち」がすれ違いの原因となり、気づけば対話が減ってしまうのです。
このような状態を放置してしまうと、関係はどんどん「説教する親」と「聞く耳を持たない子ども」という構図になってしまいます。でも、ちょっとした視点の変化と工夫で、親子の関係は良い方向に変わっていくことができます。
ここからは、スマホをめぐる親子のすれ違いの背景や、対話のコツについて、具体的に見ていきましょう。
スマホは「逃げ場」じゃなく「安心できる場所」かも?
子どもがスマホばかり見ていると、「逃げてるだけなんじゃないの?」と思ってしまうかもしれません。でも実は、スマホの中には子どもにとっての「安心できる世界」があることも多いんです。SNSやゲーム、動画、音楽など、それぞれが自分の気持ちを落ち着かせたり、他人とつながれたりする手段になっていることもあります。
たとえば、学校でうまく友達と話せなかったり、先生から注意を受けて落ち込んでいたりするとき、スマホは「現実から逃れる手段」というよりも「心のバランスをとる手段」になっていることがあります。大人でも疲れたときにYouTubeを見たり、SNSで気晴らししたりするように、子どもたちも同じように使っているのかもしれません。
もちろん、使いすぎは問題ですが、「なぜスマホに頼っているのか?」という視点で考えてみると、子どもの気持ちに寄り添うヒントが見えてきます。
「またスマホ?」ではなく「今日は何見てるの?」と聞いてみる
親が「またスマホ見て!」と口にすると、子どもは「責められた」と感じてしまうことが多いものです。そんなとき、少しだけ言葉を変えて「何見てるの?」と、興味を持って聞いてみるだけで、子どもはホッとした表情を見せることがあります。
子どもにとって、「興味を持ってくれてる」「受け入れてくれてる」と感じられるやりとりは、とても安心感を与えます。スマホの中身に関心を持つことは、子どもの世界に一歩足を踏み入れることと同じ。「こんな動画見てるんだ」「そのゲーム面白いの?」と一緒に話すことで、子どもも自然と心を開きやすくなります。
それだけでなく、「じゃあ時間を決めて見ようか」といった話し合いもしやすくなり、ルールも受け入れやすくなります。説教よりも、まずは好奇心から入ってみる。この姿勢が、親子関係をぐっと柔らかくする鍵になります。
子どもの心に届くのは「共感」から始まる言葉
親としては「ちゃんと育ってほしい」「失敗してほしくない」という気持ちから、つい厳しいことを言いたくなるもの。でも、その言葉が子どもに届くかどうかは、「共感」があるかどうかで大きく変わります。
たとえば、「スマホばかり見てないで勉強しなさい」ではなく、「疲れたときはスマホ見たくなるよね。でも今はテスト前だから、一緒に計画立ててみようか」と言われたら、子どもも聞く耳を持ちやすくなります。共感の言葉があるだけで、「自分の気持ちをわかってくれてる」と感じ、素直になれるのです。
大人も同じですよね。いきなり指示や注意だけされると反発したくなるもの。子どもとの会話も同じで、まずは「わかるよ」と伝えることから始めると、対話の土台ができていきます。共感は、親子の橋をかける第一歩です。
「伝わらない」には理由がある:親子のすれ違いの正体
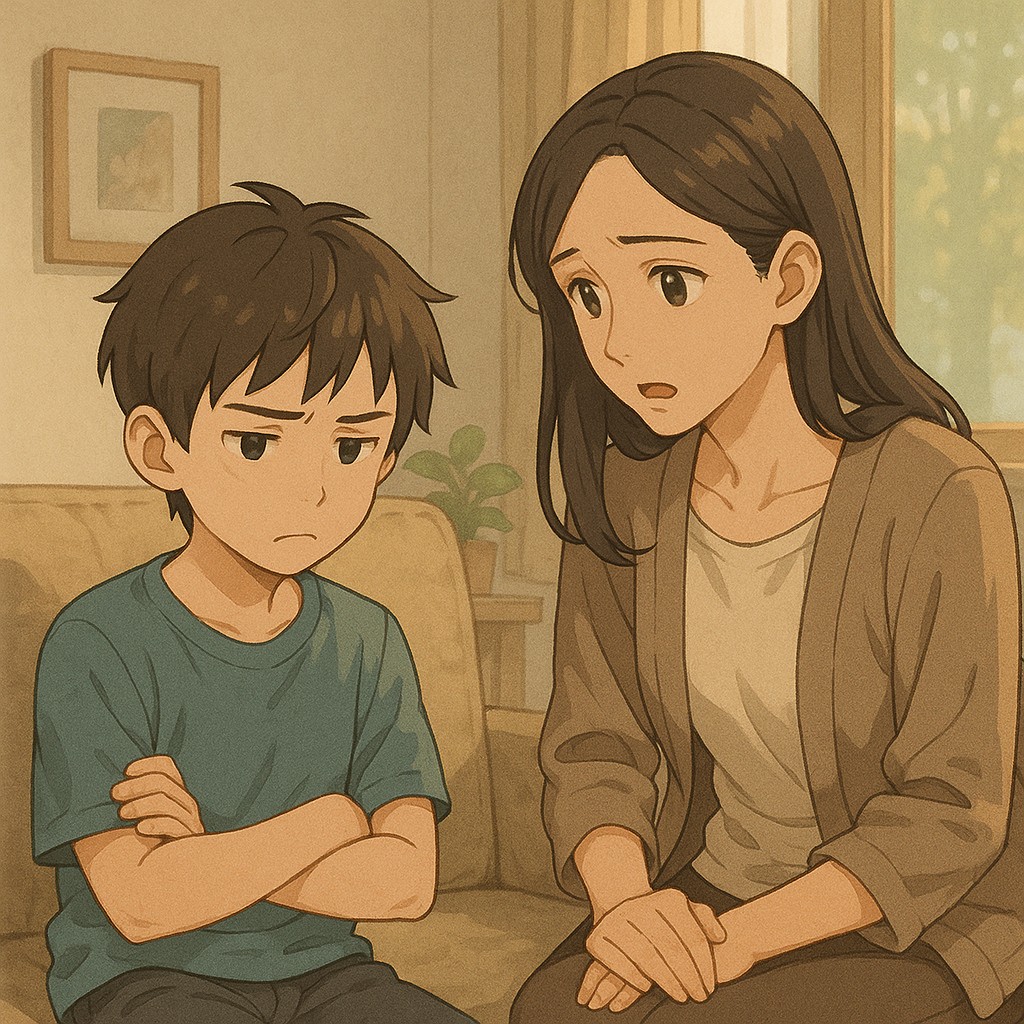
「ちゃんと話しているつもりなのに、なんでわかってくれないの?」「言ってもムダって顔をされるのがつらい」…子どもとの会話がうまくいかないと、そんなモヤモヤを感じることもありますよね。けれど、その「伝わらない」「わかってもらえない」感覚には、実はちゃんと理由があります。
親は「正しいことを伝えよう」として話すことが多い一方で、子どもは「自分を否定されたくない」という気持ちで構えてしまいがちです。これは立場の違いによって生まれる自然なズレですが、放っておくと心の距離がどんどん広がってしまいます。
また、親の言葉が「正論」であっても、タイミングや言い方によっては“攻撃された”と受け取られてしまうことも。特に思春期の子どもは、自分の世界を大切にしたいという意識が強く、親の言葉に敏感です。だからこそ「伝える」こと以上に、「伝わる」工夫が大切になってきます。
ここでは、どうして親の言葉が届かないのか、どうすれば子どもの心にスッと入っていくのかについて、具体的に考えてみましょう。
言葉よりも“温度感”が大事
「何を言うか」も大事ですが、実は「どう言うか」がもっと大事。たとえば、同じ「宿題やったの?」という言葉でも、イライラした口調で言われると責められた気持ちになりますよね。逆に、落ち着いたトーンで「今日は疲れてそうだけど、宿題手伝おうか?」と声をかけられたら、心の受け止め方も変わってくるはずです。
これは子どもも同じです。言葉そのものより、親の表情、声のトーン、雰囲気などの“温度感”が、伝わり方を大きく左右します。親がピリピリしていると、子どもも身構えてしまい、素直な気持ちを出せなくなります。
逆に、穏やかに、優しいまなざしで話しかけるだけで、子どもは「この人は自分の味方だ」と感じやすくなります。言葉の中身にこだわるよりも、まずは「安心感をどう伝えるか」を意識してみましょう。それが、心の壁をゆるめる第一歩です。
親の「べき」に子どもは疲れている
「勉強はしっかりすべき」「スマホは時間を決めて使うべき」「早く寝るべき」…親の中には「こうあるべき」がたくさんありますよね。それは愛情の裏返しであり、「ちゃんとしてほしい」という願いからくるもの。でもその「べき」が、子どもにとってはプレッシャーになってしまうこともあるのです。
特に思春期の子どもは、「自分の考えで動きたい」という気持ちが強くなります。そんなときに「~すべき」という言葉が繰り返されると、「自分の意思を無視されている」と感じ、反発したり無視したりするようになります。
だからといって何も言わないわけにはいかないのが親の立場。そんなときは、「どうしたい?」と子どもの気持ちを聞いてみることから始めてみましょう。そのうえで「じゃあ、こういうやり方はどう?」と一緒に考えていくことで、「押しつけ」ではなく「対話」が生まれます。子どもの気持ちを尊重する姿勢が、自然と行動を変えるきっかけになります。
「失敗させたくない」は親の不安かも?
「スマホばかりじゃ将来困る」「ゲームばかりで勉強に集中できなくなったらどうしよう」…そんな不安を感じるのは、親として当然のこと。でもその不安が強すぎると、つい先回りして子どもをコントロールしようとしてしまいます。
実は、子どもをコントロールしたくなる背景には、「失敗させたくない」「遠回りさせたくない」という親自身の不安があることが多いのです。でも、子どもは時に失敗しながら学び、自分なりのバランスを見つけていくもの。親が全部の道筋を決めてしまうと、子どもは「自分で考える力」を育てるチャンスを失ってしまいます。
「ちょっと心配だけど、任せてみよう」「困ったらサポートできるようにそばにいよう」という姿勢が、子どもにとって大きな安心になります。親自身も「不安を全部解消しようとしなくていい」と思えるだけで、少し肩の力が抜けて、自然な関わりができるようになりますよ。
対話を「習慣」にする:親子関係を深めるための新しいアプローチ
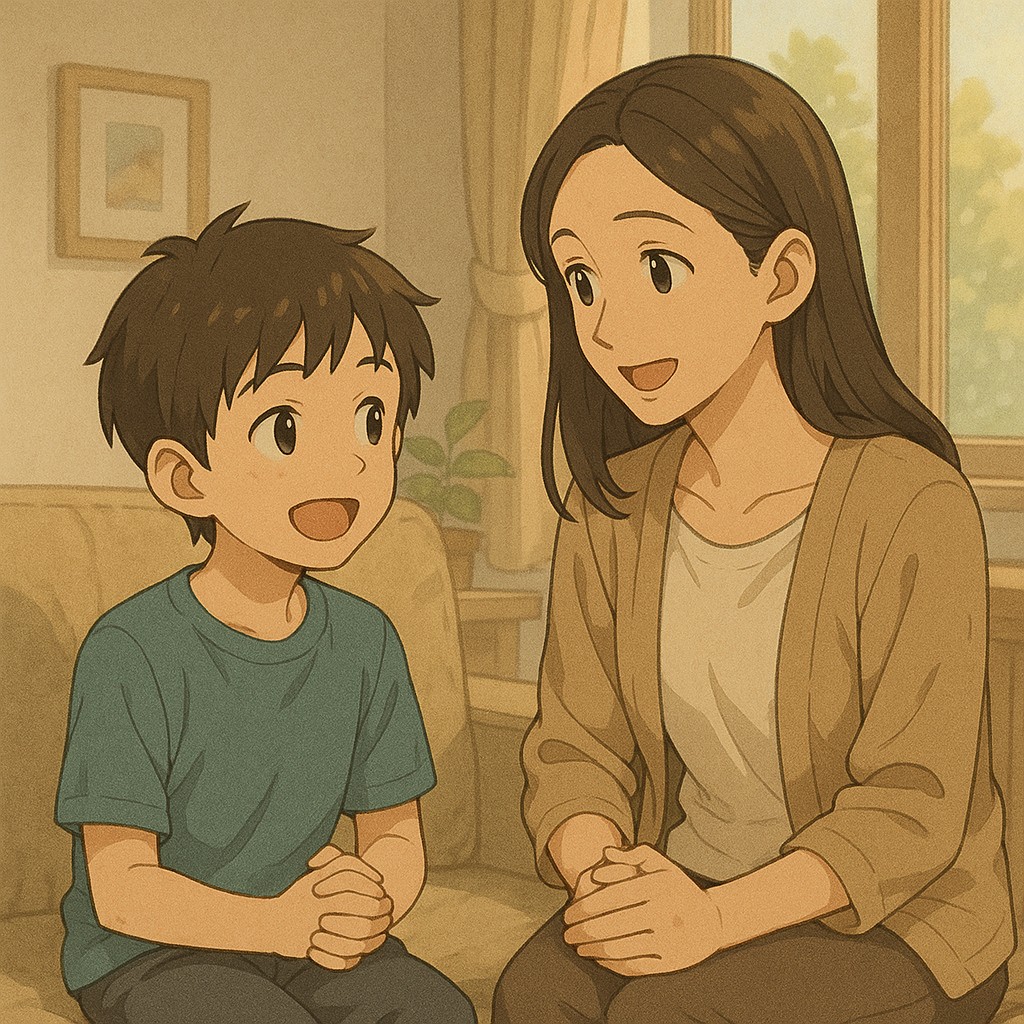
これまで見てきたように、親子のすれ違いは「言葉の内容」よりも「伝え方」や「関わり方」に原因があることが多くあります。親は子どものためを思って話しているのに、それが伝わらない。子どもは自分の気持ちを理解してほしいのに、うまく言えない…。このようなすれ違いを解消するためには、「対話のあり方」を見直すことがカギとなります。
ここで大切なのは、「特別な場面だけ対話する」のではなく、「日常的に話せる空気」をつくること。たとえば、「何かあったときにだけ真面目に話す」よりも、「普段からゆるく、楽しく話せる関係」がある方が、深い話もしやすくなるのです。
つまり、親子の対話は“イベント”ではなく“習慣”にしていくのが理想。小さなやり取りの積み重ねが信頼を育て、「本音で話しても大丈夫」という安心感につながります。
ここでは、今日から実践できる親子の対話づくりの工夫を紹介します。
1日1回、たわいもない話をする時間をつくる
「今日は学校どうだった?」「お昼、何食べたの?」…そんな何気ない会話でも、子どもにとっては心の安心材料になります。ポイントは、“内容の濃さ”より“つながる頻度”。忙しい毎日でも、1日1回、たとえ1〜2分でも子どもとゆるく話す時間をつくってみましょう。
このような会話を習慣にしていくと、子どもは「自分の話を聞いてもらえる」「ここは安全な場所だ」と感じるようになります。そして、何か困ったことや悩みが出てきたときに、自分から相談しやすくなるんです。
「別に話すことないよ」と言われても、無理に話題を引き出そうとせず、親がリラックスして話しかけることで、自然と子どもも安心して応じてくれるようになります。笑いながらのやりとりが、親子の絆を深める大事な時間になるのです。
ルールは一緒に決めると納得しやすい
スマホの使い方や勉強の時間など、親子でぶつかりやすいテーマこそ「一方的に決めない」ことが大切です。たとえば、「スマホは1日1時間にしなさい!」と親が決めてしまうと、子どもは納得できず反発しがち。でも、「どうしたらお互いに気持ちよく過ごせるかな?」と相談ベースで話すと、子どもも考えるようになります。
「じゃあ、ゲームはこの時間だけ」「寝る前の1時間はスマホをやめる代わりに、週末は好きな動画を一緒に見よう」など、お互いの意見を出し合って決めることで、ルールが“押しつけ”ではなく“合意”になります。
このプロセスは、子どもに「自分の意見が大切にされている」と感じさせると同時に、責任感も育てます。一緒にルールを作ることで、親子の関係に「信頼」と「協力」の空気が生まれるのです。
「わからない」でOKを出す勇気を持とう
親だって、完璧じゃありません。「どう声をかけていいかわからない」「何を言えば伝わるのか迷う」…そんなときは、無理に正解を出そうとせず、「実は、うまく伝えられる自信がないんだ」と素直に伝えてみるのも一つの方法です。
子どもは、大人の“素直な姿勢”に意外と敏感です。親が「どう接していいかわからない」と言うことで、子どもも「自分もどう言っていいかわからなかった」と打ち明けやすくなります。完璧に伝えようとするよりも、「伝えようとしている気持ち」があるかどうかの方が、ずっと大事なのです。
「わからない」や「迷ってる」という言葉を出せる関係は、強さではなく“柔らかさ”の証し。親が安心して迷える姿を見せることで、子どもも「この人は味方なんだ」と感じやすくなります。
「わかり合おう」とする姿勢が、親子の関係を変えていく
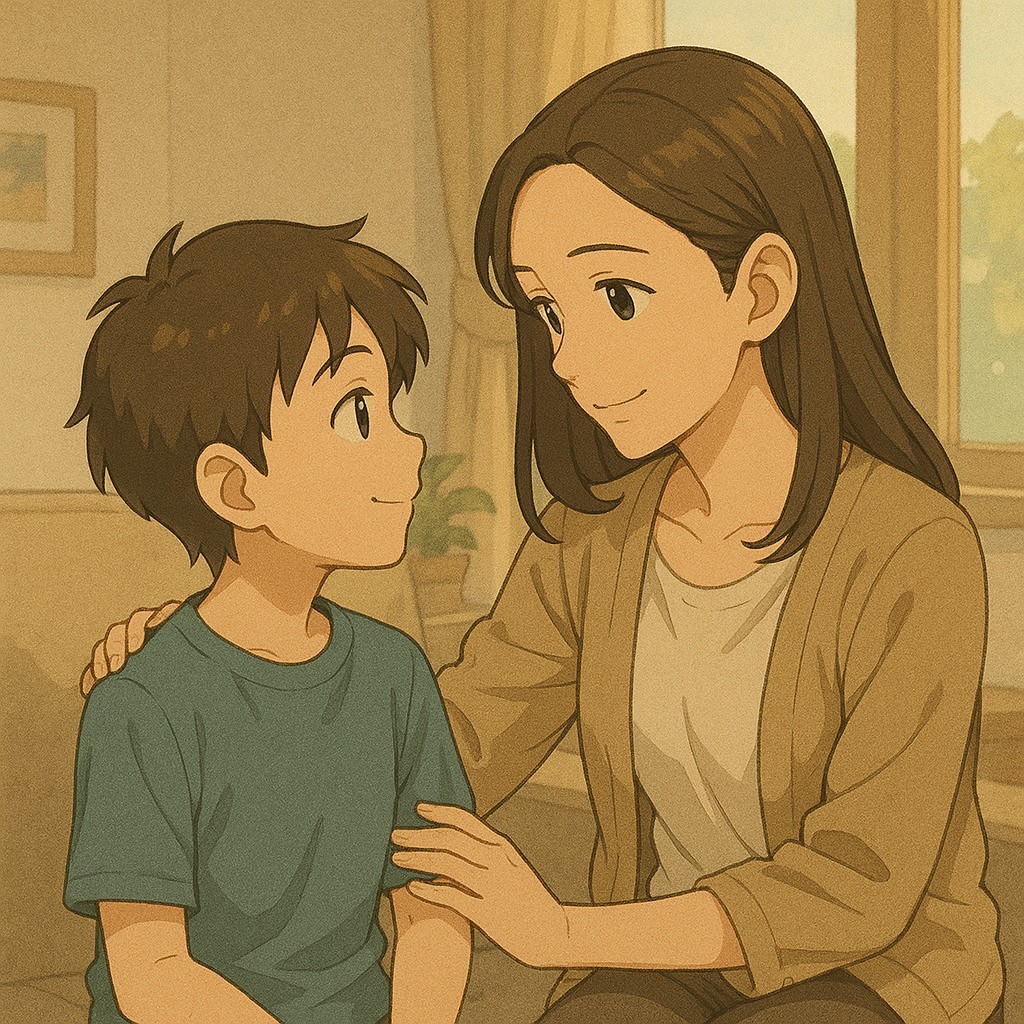
子どもがスマホを手放さない理由や、親の言葉が届かない背景には、それぞれの想いや不安があることが見えてきました。そして、それを「どう解決するか」よりも、「どう向き合うか」が、親子の関係性に大きな影響を与えるということも。
すれ違いや衝突は、親子である以上きっと避けられないもの。でも、そのひとつひとつの場面で「どう関わるか」「どう話すか」が少しずつ変わるだけで、親子の心の距離は縮まっていきます。完璧な対応や言葉が必要なのではなく、「わかりたい」「伝えたい」という姿勢があるだけで十分なのです。
子どもは、たとえ反抗的な態度をとっていても、心のどこかで「見守っていてほしい」「認めてほしい」と感じています。親もまた、「子どもとつながっていたい」と願っています。その“本音”が出会う場所こそ、日々の対話の中にあるのではないでしょうか。
ここでは、これから親子がより良い関係を築いていくためのヒントを3つご紹介します。
「今だけの関係性」ではなく「これからの信頼」を意識する
子育ての中でつい目の前の問題ばかりに目がいってしまいがちですが、親子の関係は“今だけ”で終わるものではありません。思春期が過ぎ、社会に出て、やがて大人になったときに「困ったら相談できる」「話したくなる」関係を築けているかどうかが、その後の人生にも大きく関わってきます。
今、スマホをめぐってすれ違っていても、それを通して「どう向き合ったか」は必ず子どもの記憶に残ります。「あのとき、自分の話を聞いてくれた」「ちゃんと気持ちをわかろうとしてくれた」という経験が、のちの信頼へとつながっていくのです。
だからこそ、今のやりとりを“将来の絆の種まき”ととらえてみてください。急がず、焦らず、でも誠実に。そんな姿勢が、親子の関係をじんわりと育てていきます。
大切なのは「正しさ」よりも「つながり」
「間違っていることを正したい」「ちゃんと導いてあげたい」…親としてのこうした気持ちはとても自然なもの。でも、ときにはその“正しさ”が、子どもとのつながりを遠ざけてしまうこともあるのです。
たとえば、ルールを破った子どもを叱るとき、「どうしてそんなことしたの!?」と感情的になるよりも、「何があったのか教えてくれる?」と、まず耳を傾けてみる。そうすることで、子どもも自分の行動を振り返るきっかけが得られます。
「正しいかどうか」を優先するより、「この子とつながり続けたい」という思いを大事にする。そんな心構えが、子どもの自己肯定感や信頼関係を深めていくことにつながります。
「親だって迷っていい」と伝えることで、子も自分を許せる
子どもに対して“しっかりした親”でいようと頑張るあまり、自分の不安や迷いを押し殺してしまう親御さんも多いと思います。でも、実はその“迷い”こそが、子どもとの共感のきっかけになるのです。
「どう言えばいいかわからなくて悩んでたよ」「あなたのことをちゃんと理解したくて一生懸命考えてた」――そんな言葉をかけられたとき、子どもは初めて「親も人間なんだ」「一緒に悩んでくれているんだ」と感じます。すると、自然と心を開くようになります。
親が完璧であろうとするより、「一緒に考えていこうね」と寄り添う姿勢を見せること。それが、子ども自身にも「失敗してもいい」「迷っても大丈夫」と思える心の余裕を育てていきます。
親も子も、まだまだ成長の途中。
だからこそ、完璧じゃなくていい。少しずつ、お互いに「わかろうとする」気持ちを重ねていくことで、スマホの画面の向こうにも、あたたかな親子の絆がきっと見えてくるはずです。
🌱 「わかってほしい」気持ちも、「どうしたらいいかわからない」気持ちも、大切なサインです。

子どもとの関係で悩むことは、決して「ダメな親」だからではありません。
むしろ、「ちゃんと向き合いたい」と思うからこそ、悩みやすくなるもの。
「何度言っても聞いてくれない…」
「スマホばかりの様子を見ると不安で仕方ない…」
そんな想いを、あなたはどこかでずっと抱えてきたのかもしれません。
💭 けれど、その気持ちをずっと一人で抱えていると、心が疲れてしまいますよね。
「誰かに聴いてもらうこと」「言葉にしてみること」で、
自分の中の感情が整理され、子どもへの見方が少しずつ変わっていくこともあります。
📞 私のカウンセリングでは、
あなたが感じていることをやさしく受けとめながら、
子どもとの向き合い方を一緒に見つけていきます。
🍀 説教になってしまう背景には、親自身の「心の余裕のなさ」や「完璧に育てなきゃ」というプレッシャーがあることも。
まずは、あなた自身の心を軽くしてあげることが、親子関係を変える第一歩になるのです。
🧑💼【オンライン・電話カウンセリング対応】
🌼 顔を出さずにお話しいただけるので、はじめての方も安心です。
🌟 あなたのペースで、ゆっくりお話ししてみませんか?