承認欲求が強い女性へ:他人軸で生きづらい人が“自分軸”に変わる具体的な方法
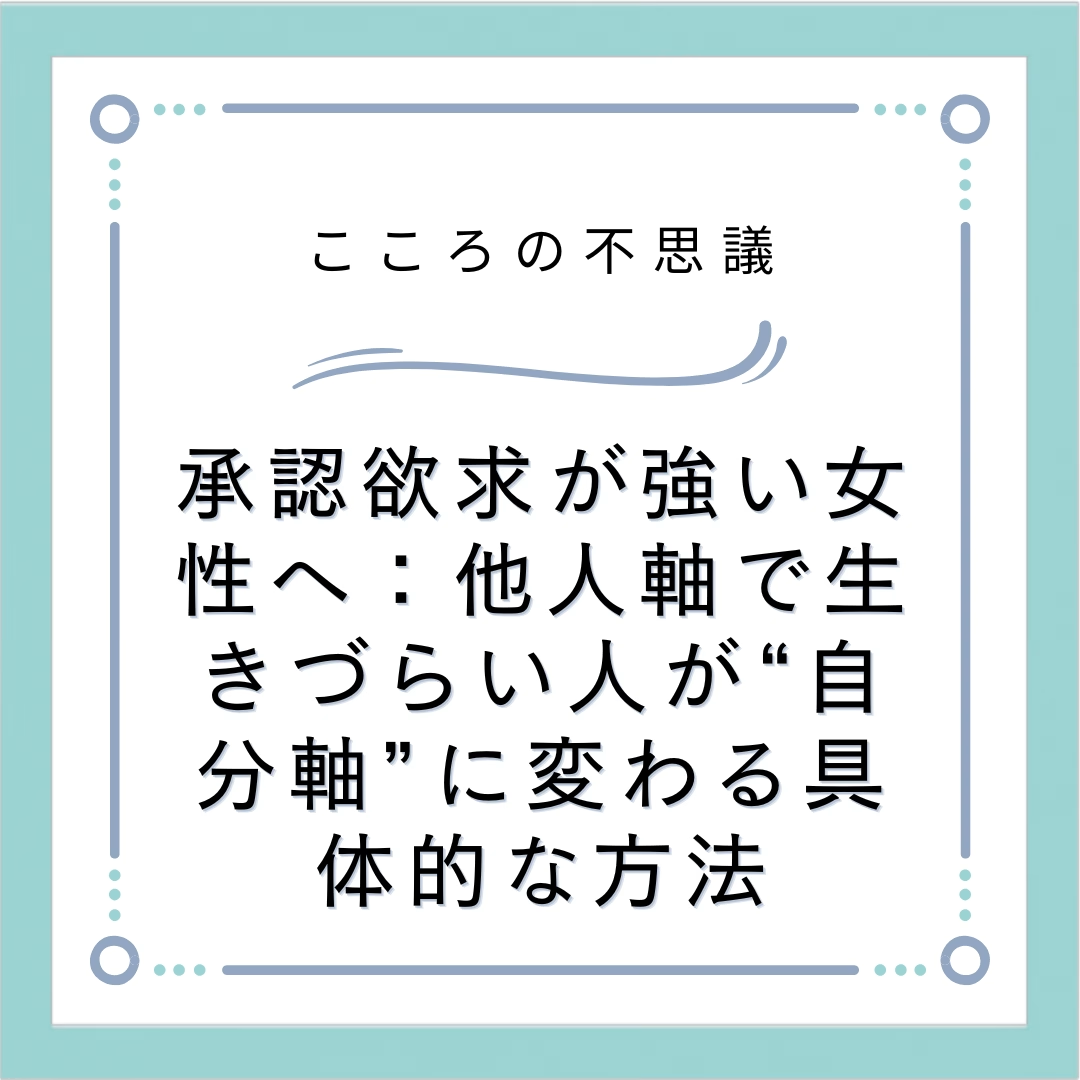
「人にどう思われているかが気になって、本音を言えない」「嫌われたくなくて、つい相手に合わせてしまう」——そんな自分にモヤモヤした経験はありませんか?
承認欲求が強い人ほど、他人の評価に敏感で、常に「ちゃんとしていなきゃ」「期待に応えなきゃ」と無意識に頑張りすぎてしまう傾向があります。最初は“優しさ”や“気配り”から始まった行動でも、気づけば「他人の基準」で動くことが当たり前になり、自分の気持ちを置き去りにしてしまうのです。
「他人にどう見られるか」を軸にしていると、どんなに努力しても満たされない瞬間が増えていきます。なぜなら、他人の評価は常に変化し、自分のコントロールの外にあるからです。そのため、褒められた時には安心しても、否定されたり無視された瞬間に、心がぐらついてしまう。そんな“他人軸”の生き方は、いつの間にか自分の幸福を他人に委ねる状態を作ってしまいます。
この記事では、「承認欲求が強い」と感じている女性に向けて、“他人軸”から“自分軸”へと少しずつシフトしていくためのヒントを紹介します。心理的な背景を理解しながら、日常の中で実践できる小さなステップを提案していきます。
誰かに認められるためではなく、「自分が心地よく生きるために」選択する力を取り戻す。そのための気づきを、一緒に探っていきましょう。
この記事でつかめる心のヒント
- 他人の評価に振り回されないことが大事: 他人の評価は変わりやすくコントロールできないため、自分の価値観や幸福を優先して、参考程度にとどめるのがポイントです。
- 少しずつ自分軸を育てるステップ: 自分の本音や価値観を見つめ直し、小さな決断から自分の意志で選ぶ練習を積むことで、自分軸へのシフトが進みます。
- 承認欲求への向き合い方: 無理に他人に認められようとせず、自己理解を深めて自分の気持ちを大切にし、自分の基準で行動できるように心がけましょう。
- 他人の期待に従う理由: 承認欲求が強いと、他人からの期待や評価を優先しがちですが、安心感や自己肯定感を高めることで自分の基準に従った行動ができるようになります。
- 心地よく生きるためのポイント: 自己理解を深め、自分の好きなことや大切な価値観を明確にし、それに沿った選択を意識して、素直な気持ちを表現することが大切です。
電話カウンセリングのリ・ハートに訪れる方の主な検索キーワード
投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー
-
【経歴】
・キャリアカウンセラー15年
・心理カウンセラー10年
※相談件数10,000件以上
【主な相談内容】
1.ストレス管理とメンタルケア
・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。
・仕事や家庭でのストレス解消法。
2.自己理解と自己成長
・自己肯定感を高めたい。
・自分の強みや価値観を明確にしたい。
3.人間関係の悩み
・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。
・対人関係における不安や緊張感への対処法。
4.不安や恐怖の克服
・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。
・パニック障害や全般性不安障害のケア。
5.うつ症状や気分の浮き沈み
・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。
・抑うつ状態から抜け出したい。
6.人生の転機や変化への対応
・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。
・新しい環境への不安や戸惑い。
7.恋愛や夫婦関係の悩み
・パートナーシップの問題解決。
・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。
8.自己批判やネガティブ思考の改善
・自分を責めすぎる傾向を変えたい。
・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。
9.家族関係や親子間の問題
・子育ての悩み。
・親や家族との関係性の見直し。
10.生きる意味や自己実現の探求
・人生の目的を再確認したい。
・自分らしい生き方を見つけるサポート。
【アプローチ方法】
1.傾聴を重視したカウンセリング
・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。
・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。
2.クライアント中心療法
・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。
・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。
3.認知行動療法(CBT)
・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。
・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。
4.ナラティブセラピー
・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。
・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。
5.対話を通じた柔軟なサポート
・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。
・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。
最新の投稿
目次
- ○ 承認欲求が強い女性が「他人の目」に疲れる理由
- ・「嫌われたくない」が口ぐせになっていませんか?
- ・褒められないと不安になる“条件付きの自信”
- ・SNSの反応で一喜一憂してしまう心理
- ○ なぜ“他人軸”で生きてしまうのか?その心の背景にあるもの
- ・「期待に応えること」が愛される条件だと思ってきた
- ・「自分の意見を言うと嫌われる」と思い込んでいる
- ・「自分の感情を後回しにする」クセが染みついている
- ○ “自分軸”に切り替える3つのステップ
- ・ステップ①:「私はどう感じる?」と自分の感情に意識を向ける
- ・ステップ②:小さな自己決定を積み重ねる
- ・ステップ③:他人との比較を減らし、心地よい距離を保つ
- ○ “自分を認める力”があれば、他人の評価に振り回されなくなる
- ・「自分を認める」ことを最優先にする
- ・「完璧じゃなくていい」と自分に許可を出す
- ・「自分のペースで生きる」勇気を持つ
- ○ 他人軸から自分軸へ──“心の軸”を取り戻すためにできること
承認欲求が強い女性が「他人の目」に疲れる理由

「人にどう思われるか」ばかり気にしてしまい、気づけば自分の気持ちを後回しにしていませんか?
承認欲求が強い女性は、優しくて気配りができ、周囲に安心感を与える一方で、自分を犠牲にしてしまうことも少なくありません。誰かに褒められると嬉しい。認められると自信が湧く。でも、褒められなければ不安になり、認めてもらえないと自分の存在が揺らいでしまう――そんな状態が続くと、心は少しずつ疲れてしまいます。
現代はSNSなどで他人の反応をすぐに知ることができる分、他人からの評価に過敏になりやすい時代です。「いいね」の数やコメントの反応が、自分の価値を測るもののように感じてしまうこともあります。けれど、他人の評価は常に変わるもの。そこに自分の幸せの軸を置いてしまうと、どうしても不安定になってしまうのです。
ここでは、承認欲求が強い女性がなぜ他人の目に振り回されやすいのか、その心理的な背景や日常のパターンを具体的に見ていきましょう。
「嫌われたくない」が口ぐせになっていませんか?
承認欲求が強い人は、「好かれたい」という思いよりも、「嫌われたくない」という恐れが行動の中心になっていることが多いです。
たとえば、飲み会で意見を求められた時、本当は違う考えを持っていても、「場の空気を壊したくないから」と周りに合わせてしまう。そうすると一時的には安心しますが、「また本音を言えなかった」と後から自己嫌悪に陥ることもあります。
これは決して弱さではなく、“安心を得たい”という自然な欲求の表れです。ですが、このパターンが続くと「自分の意見=危険」「本音を出すと人に嫌われる」という思い込みが強まり、自分らしさを表現できなくなってしまいます。
まずは、「嫌われる=ダメな自分」という考え方を少しずつ緩めていくことが、自分軸を取り戻す第一歩です。
褒められないと不安になる“条件付きの自信”
「頑張っているのに誰も気づいてくれない」と感じたことはありませんか?
承認欲求が強い女性は、努力家で責任感が強い人が多いです。だからこそ、褒められることで自分の頑張りを確かめたい気持ちが生まれます。けれど、「褒められたら安心」「褒められないと不安」というサイクルが続くと、自信の土台が他人の評価に依存してしまいます。
本来、自信は「できたこと」よりも「自分で選んだこと」によって育つもの。
他人の反応を待つのではなく、「今日はこれをやり切れた」「自分で決めて動けた」と、自分で自分を認める習慣が大切です。少しずつ“条件付きの自信”を“自分発の自信”に変えていくことが、心の安定につながります。
SNSの反応で一喜一憂してしまう心理
SNSは便利で楽しい反面、「他人と自分を比較する装置」にもなりやすい場所です。
誰かの成功投稿を見て焦ったり、自分の投稿に反応が少なくて落ち込んだり……。
そんな時、心の奥では「自分も認められたい」「存在を感じてほしい」という気持ちが働いています。
けれど、SNSの反応は一瞬の印象にすぎません。フォロワーの数や「いいね」の数が、人としての価値を示すわけではありません。
大切なのは、「自分は誰にどう見られたいのか」よりも、「自分がどう感じたいのか」。
心地よく使える範囲でSNSとの距離を取ることは、“自分軸”を保つうえでとても有効です。
他人のペースから少し離れて、自分の時間と気持ちを取り戻していきましょう。
なぜ“他人軸”で生きてしまうのか?その心の背景にあるもの
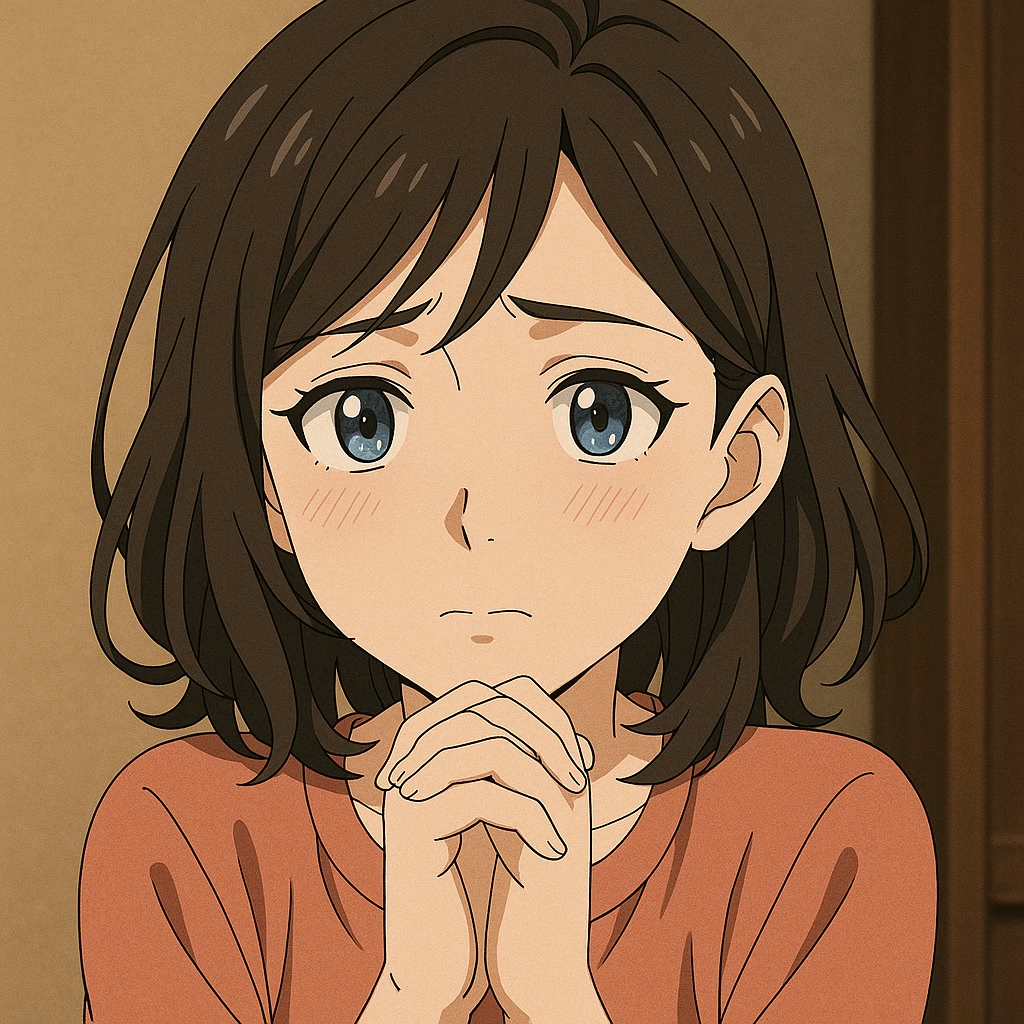
他人の目が気になるのは、単なる性格ではなく、心の奥にある「安心したい」「見捨てられたくない」という深い感情が関係しています。
多くの場合、他人軸の生き方は“誰かをがっかりさせたくない”という優しさや、“自分を守るための無意識の工夫”から生まれています。
それは、幼いころに「頑張ったら褒められる」「いい子でいないと嫌われる」と学んできた経験かもしれません。
他人の期待に応え続けてきた人は、知らず知らずのうちに「自分の感情よりも相手の反応を優先する」ことが習慣になっています。
それによって一時的には安心を得られるものの、「自分が本当は何を感じているのか」「どうしたいのか」がわからなくなってしまうのです。
ここでは、“他人軸”で生きてしまう人の内側にある3つの心理的な背景を見ていきましょう。
どれも弱さではなく、むしろ人とのつながりを大切にしてきた証です。理解することで、少しずつ自分軸への切り替えのヒントが見えてきます。
「期待に応えること」が愛される条件だと思ってきた
子どもの頃、親や先生から「ちゃんとしていれば褒められる」「いい子でいれば怒られない」と教えられてきた人は多いでしょう。
そうした環境では、「自分の気持ちを表現するより、周囲の期待に応えること」が愛される条件のように感じてしまいます。
成長してからもその感覚が残り、上司や恋人、友人などに対しても「相手がどう思うか」を優先する癖がついてしまうのです。
一見、協調性があって良いことのように見えますが、心の中では「自分の気持ちを伝える=相手をがっかりさせる」と感じてしまい、自己表現を抑えてしまうことがあります。
でも、本当の愛情や信頼関係は、相手に“期待通りの自分”を見せることではなく、“本音の自分”を出しても関係が続くことから生まれます。
「期待に応えなきゃ」と頑張ってしまう時は、「私は誰のために動いているんだろう?」と一度立ち止まってみるだけでも、心が少し軽くなります。
「自分の意見を言うと嫌われる」と思い込んでいる
他人軸で生きる人の中には、「意見を言ったら嫌われる」「波風を立てたくない」という気持ちが強い人もいます。
その背景には、過去の経験で「反論したら否定された」「意見を言ったら笑われた」など、傷ついた記憶があることも少なくありません。
そうした体験が積み重なると、「自分の意見を出す=危険」「黙っていた方が安全」と学習してしまいます。
しかし、本当のコミュニケーションは、意見の一致ではなく“違いを尊重しながら話し合うこと”で深まります。
相手の考えを尊重しつつ、自分の考えも大切にする姿勢こそ、自分軸の始まりです。
最初から大きな主張をしなくても構いません。
たとえば「私はこう感じたよ」と、自分の感情だけを伝える形でもいいのです。小さな自己表現を積み重ねることで、「言っても大丈夫だった」という経験が自信につながります。
「自分の感情を後回しにする」クセが染みついている
他人軸で生きている人は、感情を抑えるのがとても上手です。
「怒ってもしょうがない」「悲しんでる暇はない」と、自分の気持ちを封じ込めてしまう。
その結果、心の中にストレスや疲れが溜まっていき、ふとした瞬間に涙が出たり、何もやる気が起きなくなったりします。
感情を我慢するのは、短期的には人間関係をスムーズにするかもしれません。
でも、長期的には「自分が何を感じているか分からない」という“心の迷子状態”をつくってしまいます。
自分軸を取り戻すためには、まず「今、どんな気持ちがあるんだろう?」と立ち止まってみることが大切です。
怒りや悲しみがあっても、それを感じるのは悪いことではありません。
むしろ、それが「本当の自分とつながる」ためのサインです。
感情を味わうことから、自分を大切にする感覚が少しずつ育っていきます。
“自分軸”に切り替える3つのステップ

他人の評価や期待を気にせず、「自分らしく生きたい」と思っても、いきなり他人軸から自分軸へ切り替えるのは簡単ではありません。
長年身についた“他人優先の思考”は、ある意味で心の安全装置でもありました。だからこそ、焦って手放そうとするよりも、「少しずつ自分の軸を取り戻していく」くらいのペースがちょうどいいのです。
自分軸を育てるとは、周りを無視して好き勝手に生きることではありません。
大切なのは、「他人の意見を参考にしても、最終的な選択は自分がする」という姿勢。
それができるようになると、他人からどう見られるかに左右されにくくなり、心にしなやかな安定感が生まれます。
ここでは、他人軸を手放し、自分軸へ少しずつ切り替えるための3つの実践ステップを紹介します。
どれも今日から意識できるシンプルな方法ばかりです。完璧を目指さず、あなた自身のペースで始めてみましょう。
ステップ①:「私はどう感じる?」と自分の感情に意識を向ける
他人の意見を気にしすぎる人ほど、自分の感情に注意を向ける時間が少なくなっています。
たとえば、友人から誘われた時に「断ったら悪いかな」と考える前に、「私は本当は行きたい?」と自分に聞いてみる。
この小さな問いが、自分軸を取り戻す第一歩です。
感情は、私たちの本音を知らせてくれる“心のコンパス”のようなもの。
「嬉しい」「不安」「面倒くさい」など、どんな感情もあなたの内側からのサインです。
それを無視せずにキャッチできるようになると、自然と「自分がどうしたいか」を基準に選択できるようになります。
最初は違和感があっても構いません。
慣れないうちは、「正直な気持ちをノートに書き出す」「自分の気持ちを声に出して言ってみる」といった形で練習すると効果的です。
感情を感じることに罪悪感を持たず、「今の私はこう感じている」で終わらせるだけでも、心の整理が進んでいきます。
ステップ②:小さな自己決定を積み重ねる
自分軸を育てるうえで大切なのは、「自分で決める」経験を増やすこと。
それは大きな決断ではなく、日常の小さな選択からで十分です。
たとえば「今日はコーヒーにするか紅茶にするか」「休日は誰かと会うか、一人で過ごすか」――その一つひとつを“自分で選んだ”と意識してみてください。
他人軸の人は、無意識に「相手がどう思うか」を基準に選びがちですが、少しずつ「私はこれが好き」「こうしたい」と口にすることで、選択の主導権を自分に戻せます。
この小さな積み重ねが、「自分で決めていいんだ」という感覚を育て、自尊心を支える土台になります。
最初は「間違えたらどうしよう」と不安になるかもしれません。
でも、たとえうまくいかなくても、それは“失敗”ではなく“自分で選んだ結果”。
その経験を重ねるほど、他人の反応よりも「自分の納得感」で判断できるようになっていきます。
これがまさに、“自分軸”で生きる感覚です。
ステップ③:他人との比較を減らし、心地よい距離を保つ
自分軸を保つうえで最も難しいのが、「他人との比較から離れること」です。
SNSや職場、人間関係の中で、どうしても「自分はあの人より劣っている」「もっと頑張らなきゃ」と思ってしまう瞬間はあります。
でも、比較の基準が他人になる限り、どれだけ努力しても心は満たされません。
比較を減らすコツは、「他人のペースを参考にせず、自分のペースを尊重する」こと。
たとえば、SNSの利用時間を減らす、他人の意見を聞いた後に「でも私はどう思う?」と一呼吸置く――そんな工夫が有効です。
また、「自分にとって心地いい人間関係」を見直すことも大切です。
他人軸の人ほど、周囲に気を使いすぎて疲れてしまいがち。
少し勇気を出して距離を取ることで、心がスッと軽くなることがあります。
“自分軸”とは、自分勝手になることではなく、「自分を大切にする選択を増やすこと」。
他人との比較を減らし、自分のペースで生きることができた時、初めて本当の安心感が生まれます。
“自分を認める力”があれば、他人の評価に振り回されなくなる

“自分軸”で生きるというのは、他人を無視して好き勝手に生きることではありません。
むしろ、他人を大切にしながらも「自分の気持ちを置き去りにしない」ことです。
承認欲求が強い人は、これまで「どうすれば好かれるか」「どうすれば失望させないか」を中心に生きてきました。
その分、他人の気持ちを感じ取る力に長けていて、人との関係を大切にする優しさを持っています。
ただし、その優しさを自分への思いやりにも向けてあげないと、心がすり減ってしまいます。
“自分軸”とは、外の評価に頼らず、「自分が自分をどう感じているか」を基準に生きること。
それができるようになると、たとえ誰かに否定されたとしても、自分の存在価値が揺らぐことはありません。
ここでは、他人の評価に振り回されないために必要な3つの心の習慣を紹介します。
どれも大きな変化ではなく、日々の小さな心がけから始まるものです。
「自分を認める」ことを最優先にする
他人に認められたいという気持ちは、人とのつながりを求める自然な欲求です。
でも、もしあなたが常に「誰かに認められないと不安」と感じるなら、それは“自己承認”が不足しているサインかもしれません。
自己承認とは、「完璧じゃなくても、今の自分でいい」と自分を認めること。
失敗しても、落ち込んでも、それでも頑張って生きている自分を肯定してあげることです。
他人の承認は一時的ですが、自分の承認はどんな時でもあなたを支えてくれます。
たとえば、「今日もよくやったね」「あの時の判断、私らしかったな」と小さく自分を褒めるだけでも十分です。
そうした積み重ねが、外の評価に左右されない“内側の安定”をつくっていきます。
「完璧じゃなくていい」と自分に許可を出す
承認欲求が強い人は、同時に完璧主義な傾向を持つことが多いです。
「失敗したらどう思われるか」「中途半端な自分を見せたくない」――そんな思いが、自分を常に追い込み続けてしまう。
でも、完璧を目指すほど、他人の評価に依存する度合いは強くなります。
自分軸を育てるためには、「できない自分もOK」「今日はこれで十分」と認める勇気が必要です。
完璧じゃなくても、あなたの価値は変わりません。むしろ、不完全な部分こそ人間らしさを感じさせ、周囲とのつながりを深めるきっかけになります。
たとえば、誰かに弱音を吐いたり、助けを求めたりすることも悪いことではありません。
「できない自分を見せる=迷惑をかける」と思いがちですが、実際はそれによって相手との信頼関係が強まることもあります。
「完璧じゃなくても愛されている」――その実感が、あなたを自由にしてくれます。
「自分のペースで生きる」勇気を持つ
他人軸の人ほど、他人のスピードや基準に合わせがちです。
でも、人にはそれぞれ心地よいペースがあります。
早く進むことが正解ではなく、自分にとって無理のないテンポを見つけることが大切です。
たとえば、「みんなが結婚してるから」「同僚が昇進したから」と焦る気持ちが出てきた時、
「私はどう生きたい?」と立ち止まってみてください。
その答えは、他人の評価よりもずっとあなたの人生に意味を与えてくれます。
周りに合わせることをやめ、自分のリズムで歩み始めたとき、人と比べる苦しさは少しずつ薄れていきます。
他人軸から自分軸へ――それは、競争ではなく回復のプロセスです。
「私は私で大丈夫」と思える瞬間が増えていけば、もう誰かの期待に縛られる必要はありません。
“自分を認める力”が育つと、外の評価はただの参考意見に変わります。
そして、あなたの中に静かな自信が芽生える。
その自信こそが、どんな時もあなたを支える“本当の自分軸”です。
他人軸から自分軸へ──“心の軸”を取り戻すためにできること
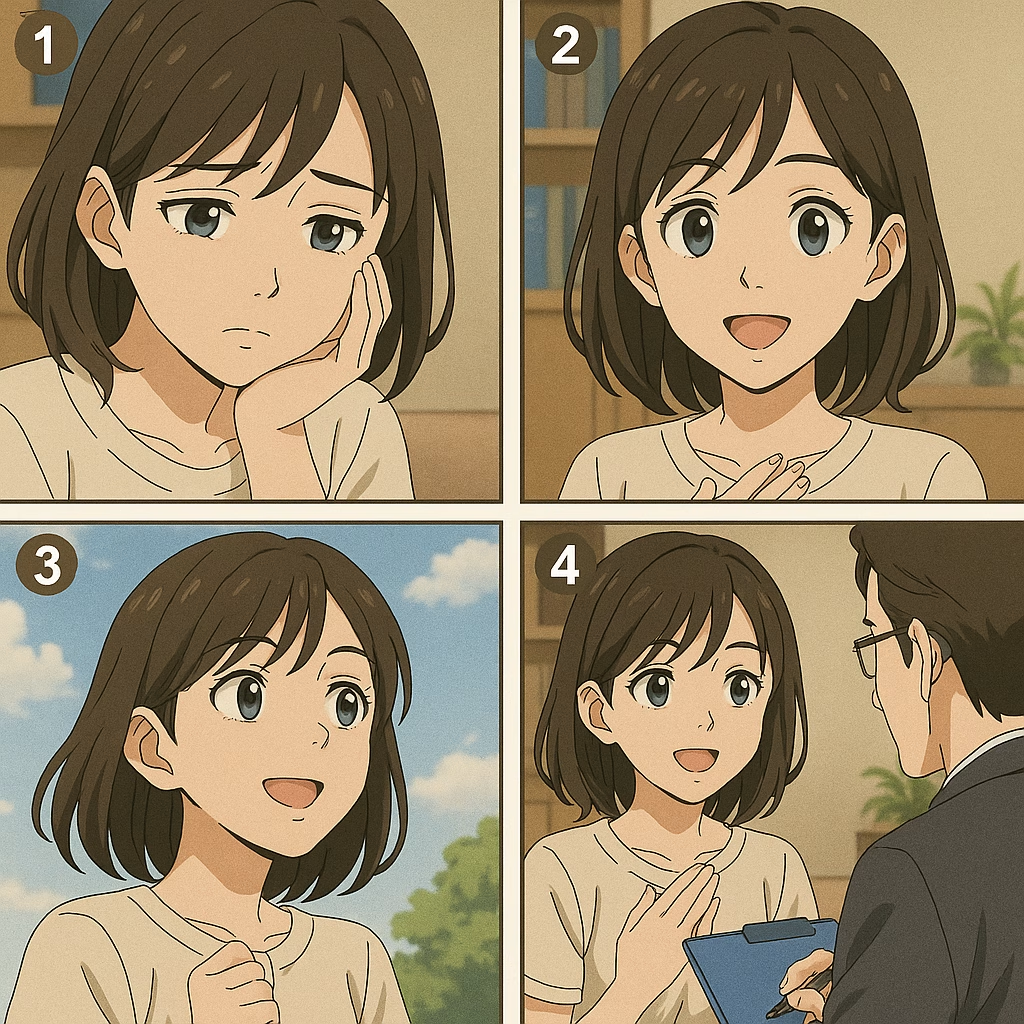
誰かの期待に応えようとしてきたあなたは、きっととても優しく、責任感のある人です。
でも、その優しさが自分を縛って苦しめているとしたら、少し立ち止まってみるタイミングかもしれません。
他人にどう思われるかより、「自分がどう感じているか」を大切にする。
そのシンプルな意識の切り替えが、少しずつ心を軽くしてくれます。
“自分軸”とは、他人を遠ざけることではなく、自分の気持ちを土台に人と関わる力のこと。
そうやって生き方のバランスを整えていくうちに、「人の目が怖い」「認められたい」と感じていた不安は自然と小さくなっていきます。
もし今、「頭では分かっているけれど、どう切り替えたらいいのか分からない」と感じているなら、
その迷いごと誰かに話してみるのもひとつの方法です。
カウンセリングでは、あなたの中にある“本当の気持ち”を丁寧に言葉にしていきながら、
他人軸から自分軸へシフトするプロセスを一緒に整理していけます。
誰かの目を気にせずに、自分の感情に誠実でいられるようになると、
生きる世界が少しずつ穏やかに変わっていきます。
焦らず、比べず、自分のペースで。
その一歩を踏み出したいと思ったとき、カウンセリングがきっと支えになってくれるはずです。


を軽くする方法-150x150.avif)


