自己肯定感が低い人がキャリアでつまずく理由と改善方法:自信を育てて成長するステップ
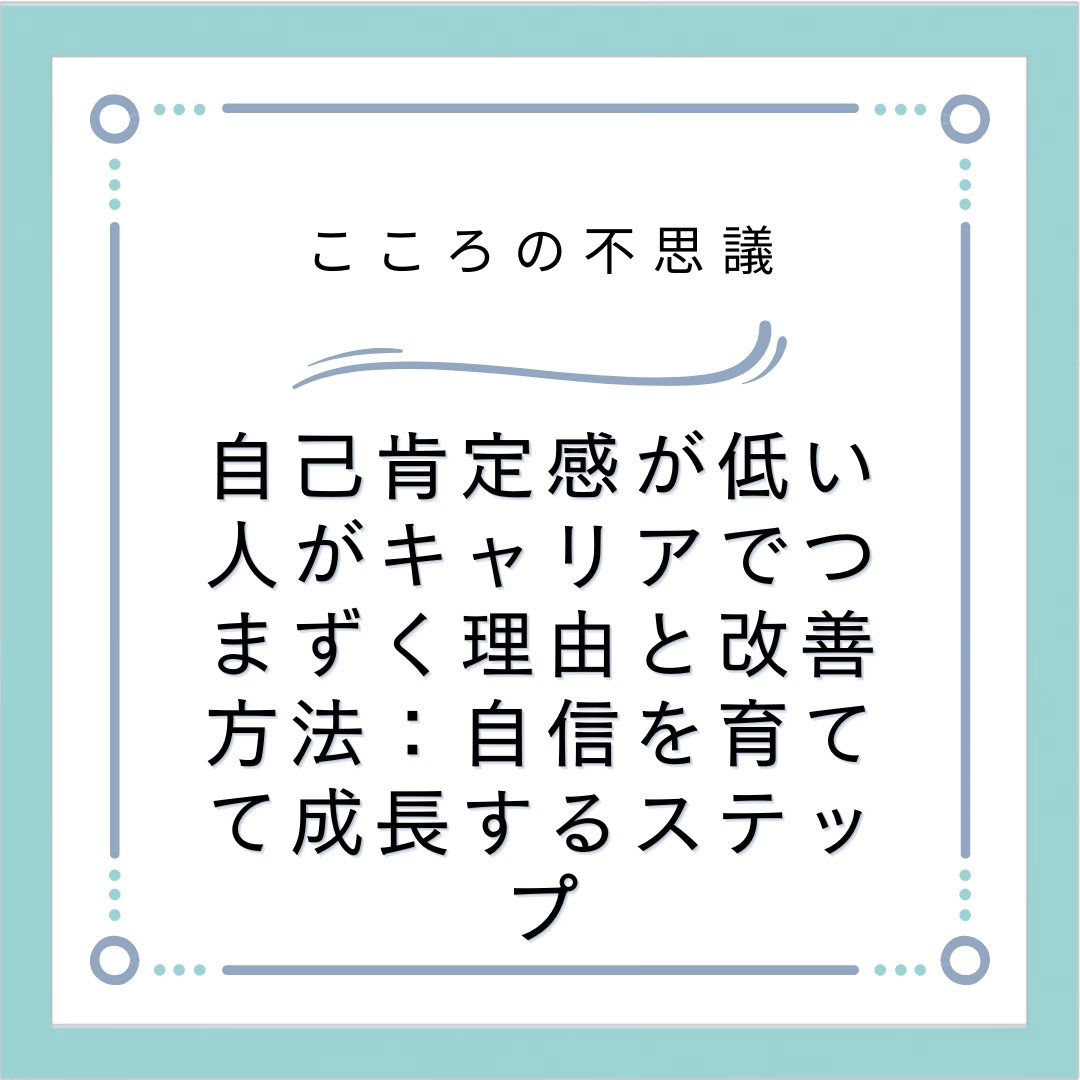
「自分にはまだ早いかも」「どうせ上手くいかないだろう」——そう思って、チャンスを見送った経験はありませんか?
努力しているのに結果が出ない。周りの人と比べて焦る。上司や同僚の言葉に一喜一憂して、自分のペースを見失ってしまう。
そんなとき、問題はスキルや才能ではなく、“自分をどう見ているか”にあることが少なくありません。
自己肯定感が低いと、「挑戦すること」より「失敗しないこと」を優先してしまいがちです。
その結果、新しい仕事に手を出せなかったり、評価を気にしすぎて意見を言えなかったりと、キャリアのステップアップを自ら止めてしまうケースもあります。
一方で、自己肯定感が高い人は、自分を信じて小さな挑戦を積み重ねることができるため、自然とチャンスをつかみやすい傾向があります。
この記事では、自己肯定感が低い人がキャリア形成でつまずきやすい理由を心理的な視点からわかりやすく解説します。
そして後半では、自信を取り戻し、前に進むための実践的なステップを紹介します。
「頑張っているのに、なぜかうまくいかない」と感じている方が、自分を責めずに少しずつ前を向けるようになる――そんなきっかけになる内容を目指しています。
自己肯定感が低いと感じている人はどうすればいい?
自己肯定感が低いと感じている人は、まず自分の良いところを書き出すことや、専門のカウンセリングを利用して自分を見つめ直すのも良い方法です。
記事の後半で紹介されている実践的なステップにはどんなものがあるの?
記事の後半では、自信を取り戻すための具体的な方法として、自己肯定感を育てるためのセルフケアや、ポジティブな思考の習慣化などが紹介されています。
自己肯定感を高めるにはどうしたらいいの?
自己肯定感を高めるには、小さな成功体験を積み重ねることや、自分の良いところを認める練習をすることがおすすめです。
どうして自己肯定感が低いと挑戦を避けてしまうの?
自己肯定感が低いと、自分に自信が持てず、「失敗したらどうしよう」と怖くなり、リスクを取ることを避けてしまう傾向があります。
自己肯定感が低いとキャリアにどんな影響があるの?
自己肯定感が低いと、新しい仕事に挑戦しにくくなったり、評価を気にしすぎて意見を言えなくなるなど、キャリアのステップアップを自ら妨げてしまうことがあります。
投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー
-
【経歴】
・キャリアカウンセラー15年
・心理カウンセラー10年
※相談件数10,000件以上
【主な相談内容】
1.ストレス管理とメンタルケア
・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。
・仕事や家庭でのストレス解消法。
2.自己理解と自己成長
・自己肯定感を高めたい。
・自分の強みや価値観を明確にしたい。
3.人間関係の悩み
・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。
・対人関係における不安や緊張感への対処法。
4.不安や恐怖の克服
・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。
・パニック障害や全般性不安障害のケア。
5.うつ症状や気分の浮き沈み
・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。
・抑うつ状態から抜け出したい。
6.人生の転機や変化への対応
・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。
・新しい環境への不安や戸惑い。
7.恋愛や夫婦関係の悩み
・パートナーシップの問題解決。
・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。
8.自己批判やネガティブ思考の改善
・自分を責めすぎる傾向を変えたい。
・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。
9.家族関係や親子間の問題
・子育ての悩み。
・親や家族との関係性の見直し。
10.生きる意味や自己実現の探求
・人生の目的を再確認したい。
・自分らしい生き方を見つけるサポート。
【アプローチ方法】
1.傾聴を重視したカウンセリング
・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。
・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。
2.クライアント中心療法
・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。
・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。
3.認知行動療法(CBT)
・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。
・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。
4.ナラティブセラピー
・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。
・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。
5.対話を通じた柔軟なサポート
・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。
・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。
最新の投稿
目次
- ○ 自己肯定感の低さがキャリアに影響する理由とは?
- ・自信が持てずにチャンスを逃してしまう
- ・他人の評価に依存してしまう
- ・失敗を恐れすぎて行動が止まる
- ○ 自己肯定感が低い人に見られる思考パターンと行動の特徴
- ・「完璧じゃないと意味がない」と思い込む
- ・「どうせ自分なんて」と考えてしまう
- ・「周りに合わせなきゃ」と自分を押し殺す
- ○ なぜ自己肯定感の低さがキャリアの成長を止めるのか?
- ・「行動できない悪循環」に陥る
- ・「他人軸」で判断し続けて疲弊する
- ・「成果を出しても満たされない」状態になる
- ○ 自己肯定感を高めてキャリアを前進させる具体的な方法
- ・小さな成功を意識して「できた自分」を認める
- ・自分の努力を言葉にして「内側から承認」する
- ・比較から離れ、「自分のペース」で進む勇気を持つ
- ○ 自分を責める働き方から抜け出す:自己肯定感を育てる第一歩
自己肯定感の低さがキャリアに影響する理由とは?
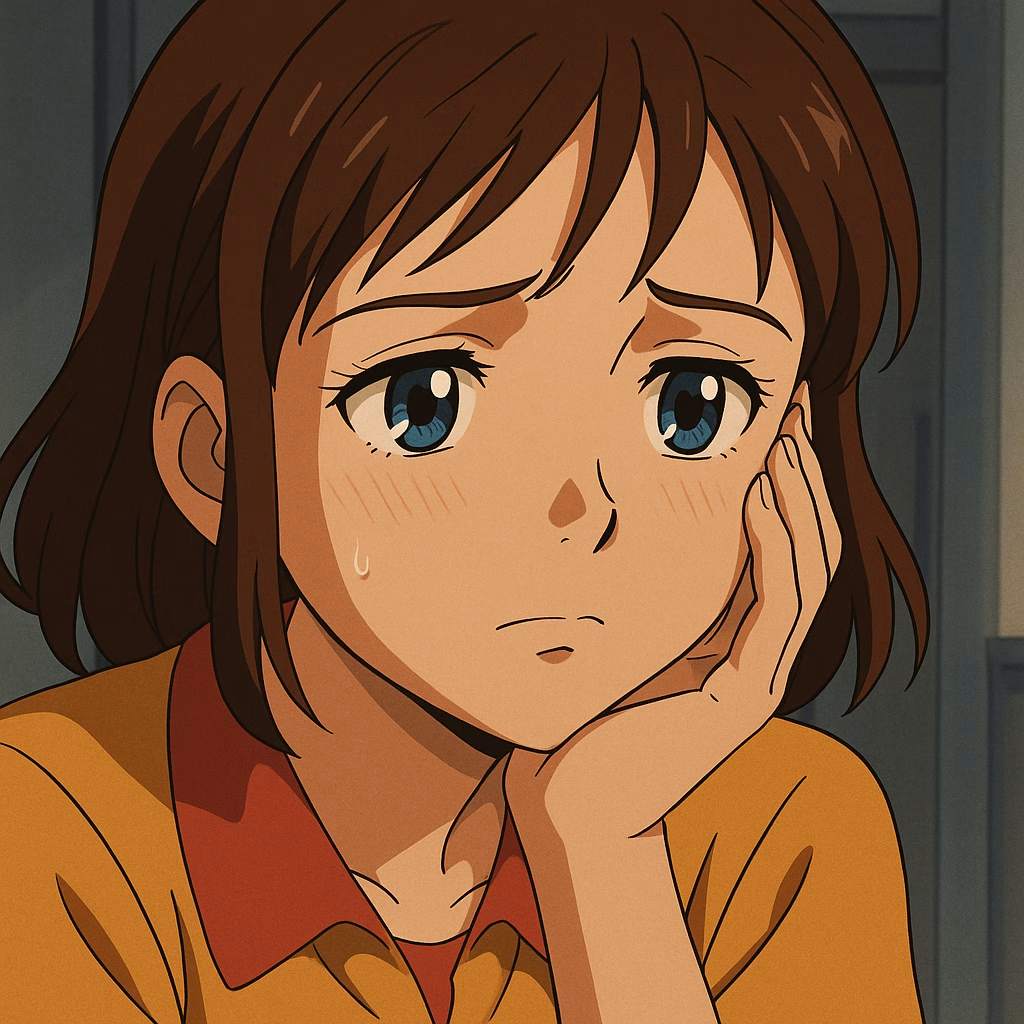
「仕事で頑張っているのに報われない」「自分には何かが足りない気がする」——そんな思いを抱いたことはありませんか?
多くの人がキャリアのどこかでつまずく瞬間を経験しますが、その原因が“能力の差”や“運の悪さ”だけとは限りません。実は、目に見えない“自己肯定感の低さ”が影響している場合がよくあります。
自己肯定感とは、「自分は自分でいい」と思える感覚のこと。これは、成功体験や失敗の受け止め方、他人との比較など、さまざまな経験の積み重ねで形づくられていきます。
この感覚が低いと、自分の価値を認められず、常に誰かと比べたり、評価を求めすぎたりしてしまいます。結果として、キャリアを伸ばすための行動が制限されてしまうのです。
では、なぜ自己肯定感が低いとキャリアが停滞しやすくなるのでしょうか?
その背景には、**「自信の欠如」「他者依存」「失敗への恐れ」**という3つの心理的な要因が関わっています。
以下では、それぞれの特徴をもう少し具体的に見ていきましょう。
自信が持てずにチャンスを逃してしまう
自己肯定感が低い人は、自分の力を過小評価しがちです。
「自分には無理」「どうせ上手くいかない」と思い込んでしまうため、せっかくのチャンスがあっても手を伸ばせません。
たとえば、上司に新しいプロジェクトへの参加を打診されても、「自分なんかがやっても迷惑をかけるかも」と断ってしまう。
本当は挑戦したい気持ちがあるのに、“失敗したらどうしよう”という不安が先に立ってしまうのです。
その結果、行動する前から可能性を閉ざしてしまい、キャリアの成長機会を逃してしまうケースは少なくありません。
自信のなさは、周囲から見ても「消極的」「頼りない」と映ることがあり、評価にも影響します。
一歩踏み出す勇気を持てるかどうか——その違いが、数年後のキャリアに大きな差を生むのです。
他人の評価に依存してしまう
自己肯定感が低いと、「自分の判断より他人の評価を優先する」という傾向が強まります。
上司の反応、同僚の視線、SNSでの反応…。
誰かの言葉一つで気分が上下してしまい、いつの間にか“他人基準”で働くようになってしまいます。
「上司に認められたい」「周りに悪く思われたくない」という気持ちは自然なものですが、そこにとらわれすぎると、本来の自分らしさを見失います。
結果的に、「自分がどうしたいのか」がわからなくなり、モチベーションも下がっていきます。
キャリアを築くうえで大切なのは、他人の評価を軸にすることではなく、自分が大切にしたい価値観を軸にすること。
それができないと、周囲の期待に合わせ続けて疲れ果て、心が折れてしまうこともあります。
失敗を恐れすぎて行動が止まる
自己肯定感が低い人は、失敗を「自分の価値の否定」と結びつけてしまいがちです。
「うまくいかなかった=自分はダメな人間だ」と感じてしまうため、次の挑戦を避けるようになります。
しかし、失敗そのものは誰にでも起きる自然なプロセスです。
それを恐れて行動を止めてしまうと、学ぶ機会や経験の積み重ねが減り、結果的に本当に「成長できない」状態に陥ってしまいます。
自己肯定感が高い人は、失敗しても「やってみた自分を認める」ことができます。
この違いが、長い目で見たときに大きなキャリアの差となって表れます。
失敗を怖がるのではなく、「挑戦できた自分をまず肯定する」——
そこから、少しずつ前進の感覚が生まれていきます。
自己肯定感が低い人に見られる思考パターンと行動の特徴
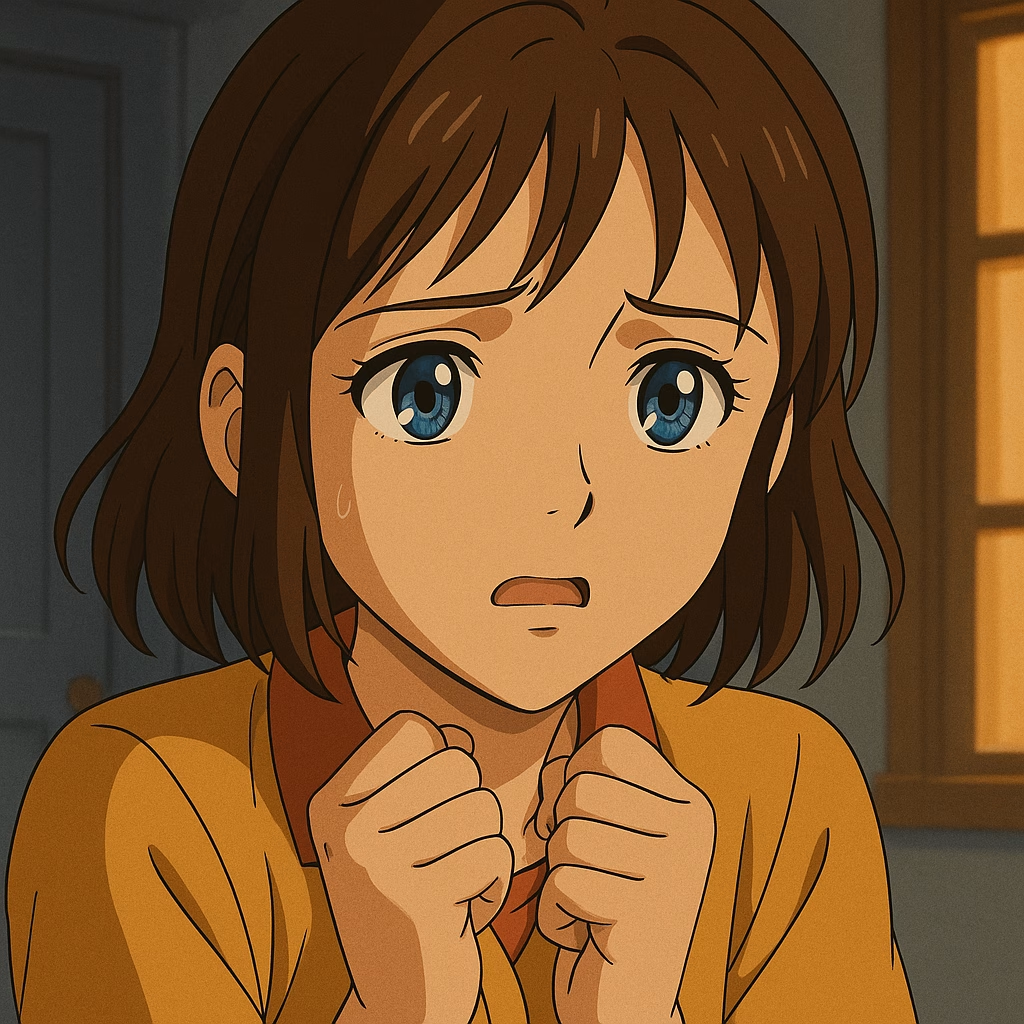
自己肯定感が低い人は、無意識のうちに“自分を制限する思考パターン”を繰り返していることがあります。
それは「どうせ自分なんて」という諦めに近い考えだったり、「周りに嫌われたくない」という過剰な気遣いだったり。
こうした思考は、本人の努力とは関係なく、日々の小さな選択や行動に影響を与えています。
そして厄介なのは、それが“習慣化”していること。
自分では気づかないうちに、「自分を信じない」方向へ脳が慣れてしまっているのです。
どれだけ努力しても成果を実感できなかったり、他人の成功を見て落ち込んだりする背景には、この思考のクセが関わっています。
ここでは、自己肯定感が低い人が陥りやすい代表的な3つの思考パターンを取り上げます。
「これ、自分にもあるかも」と感じたら、それは変化への第一歩。
まずは、どんな考え方があなたのキャリアを静かに止めているのかを、一緒に見つめていきましょう。
「完璧じゃないと意味がない」と思い込む
自己肯定感が低い人ほど、完璧を求めがちです。
ミスをすると「自分はダメだ」と極端に落ち込み、完璧にできない自分を許せません。
たとえば、プレゼンで少し言葉を詰まらせただけで、「最悪だった」「もう次はない」と自分を責めてしまう。
一方で、周囲の人は「内容は伝わっていたよ」と気にしていない。
このズレが積み重なると、「自分はいつも失敗している」と誤った自己イメージを強化してしまいます。
完璧主義は、一見“向上心”に見えますが、根底には「失敗したら価値がない」という恐れがあります。
この恐れが強いほど、挑戦へのハードルは上がり、キャリアの伸びしろを自ら狭めてしまいます。
本当は、“できなかった自分”にも価値がある。
完璧を求めすぎず、「今の自分ができたこと」にも目を向ける習慣が、心を少しずつ軽くしてくれます。
「どうせ自分なんて」と考えてしまう
失敗や否定的な経験を重ねてきた人ほど、「どうせ自分なんて」という思考がクセになります。
それは、自分を守るための防衛反応でもあります。
期待して裏切られるより、最初から期待しないほうが傷つかない。
そう感じている人は少なくありません。
でも、この思考の落とし穴は、“行動の前に諦めてしまう”こと。
たとえば、応募したかった仕事があっても、「どうせ受からないし」とチャレンジしない。
自分の意見を言いたい場面でも、「自分が言っても意味がない」と口を閉ざす。
こうして、チャレンジの機会を逃すたびに、「やっぱり自分はダメだ」という思い込みが強化されます。
まるで自分の中に“否定のループ”ができてしまうような状態です。
そこから抜け出す第一歩は、「根拠のない否定を、ただの“クセ”として認識すること」。
自分を責めずに、「またこう考えてるな」と気づくだけでも、思考の流れは少しずつ変わっていきます。
「周りに合わせなきゃ」と自分を押し殺す
自己肯定感が低い人は、人間関係で“波風を立てないこと”を最優先にしがちです。
周りに嫌われないように、自分の意見を抑えてしまう。
「相手を不快にさせたらどうしよう」と考えるあまり、本音を言えなくなっていきます。
たとえば、職場で意見を求められたとき、本当は違う考えがあっても「そうですね」と合わせてしまう。
その場はうまく収まりますが、内心では「なんで自分ばかり我慢してるんだろう」とモヤモヤが残る。
こうした小さな我慢の積み重ねが、知らぬ間にストレスや自己否定感を深めていきます。
本音を言うことは、わがままではありません。
自分の意見を持ち、それを伝えることは、立派な自己表現です。
「嫌われないように生きる」よりも、「自分を大切にして関われる関係」を増やしていくことが、キャリアでも人生でも長く続く安心につながります。
なぜ自己肯定感の低さがキャリアの成長を止めるのか?

自己肯定感が低いと、目の前のチャンスを「自分には無理」と思って逃したり、他人の反応ばかり気にして行動をためらったりする。
そんな小さな“遠慮”が積み重なって、気づけばキャリアの流れが止まってしまうことがあります。
表面的には「自信がないだけ」に見えるかもしれません。
でもその根っこには、「失敗したら自分の価値がなくなる」「人に迷惑をかけたくない」といった深い恐れがあります。
この恐れが強いほど、人は行動を控え、学ぶ機会や成功体験を減らしてしまう。
結果的に「やっぱり自分はダメだ」という思いが強まり、さらに自己肯定感が下がるという悪循環に陥っていくのです。
この“心のブレーキ”は、努力の量では解決できません。
いくら頑張っても、心の中で自分を否定している限り、成長は頭打ちになってしまいます。
ここでは、自己肯定感の低さがどんな形でキャリアを止めてしまうのかを、3つの視点から見ていきましょう。
「行動できない悪循環」に陥る
自己肯定感が低い人は、「失敗したらどうしよう」という不安が先に立ち、行動する前に立ち止まってしまいます。
たとえば、新しいスキルを学ぼうとしても「自分には難しそう」と思って手を出さない。
上司にアイデアを提案したくても、「採用されなかったら恥ずかしい」と黙ってしまう。
こうして「やらない」選択を繰り返すうちに、行動する感覚そのものが鈍くなっていきます。
挑戦しなければ成功体験も得られず、結果的に「やっぱり自分には何もできない」と感じてしまう。
つまり、行動しないことが、さらに自信を奪うループをつくってしまうのです。
このループを断ち切るには、“完璧にやる”ではなく“とりあえずやってみる”という姿勢が大切。
小さな行動でも「できた」という感覚を積み重ねることで、少しずつ心のブレーキは緩んでいきます。
「他人軸」で判断し続けて疲弊する
自己肯定感が低い人は、自分の判断より他人の意見を優先しがちです。
「上司がこう言ったから」「みんながそうしてるから」と、人の基準に合わせて行動してしまう。
一見、協調的で良いことのように見えますが、これが続くと“自分の軸”を見失ってしまいます。
他人の評価は常に変わるもの。
そのたびに気持ちが揺れ動き、「何が正しいのか」「自分はどうしたいのか」がわからなくなる。
結果的に、精神的にも疲れやすく、モチベーションを保てなくなっていきます。
キャリアの成長には、自分の価値観を基準に選ぶ力が欠かせません。
他人軸で動いているうちは、どれだけ頑張っても「誰かの期待を満たすだけ」の働き方になってしまうのです。
自己肯定感を回復させることは、自分の選択を信じる力を取り戻すことでもあります。
「成果を出しても満たされない」状態になる
自己肯定感が低い人の中には、「頑張り屋なのに、なぜか満足できない」という人も多いです。
昇進しても、資格を取っても、「まだ足りない」「もっと頑張らなきゃ」と思ってしまう。
どれだけ成果を出しても、それを「自分の実力」として受け取れないのです。
この状態では、達成感が長続きせず、常に“自分を追い立てるような働き方”になります。
周囲から見れば十分に評価されていても、本人の中では「認められた気がしない」。
それは、自分自身の価値を内側から支える“自己承認”が欠けているからです。
心の土台が「自分を信じる感覚」で満たされていないと、外の評価はいくら得ても安心にはつながりません。
本当のキャリアの成長とは、“外の成功”ではなく“内側の安定”とセットで成り立つもの。
自己肯定感を取り戻すことは、その安定を育てるための最初の一歩なのです。
自己肯定感を高めてキャリアを前進させる具体的な方法
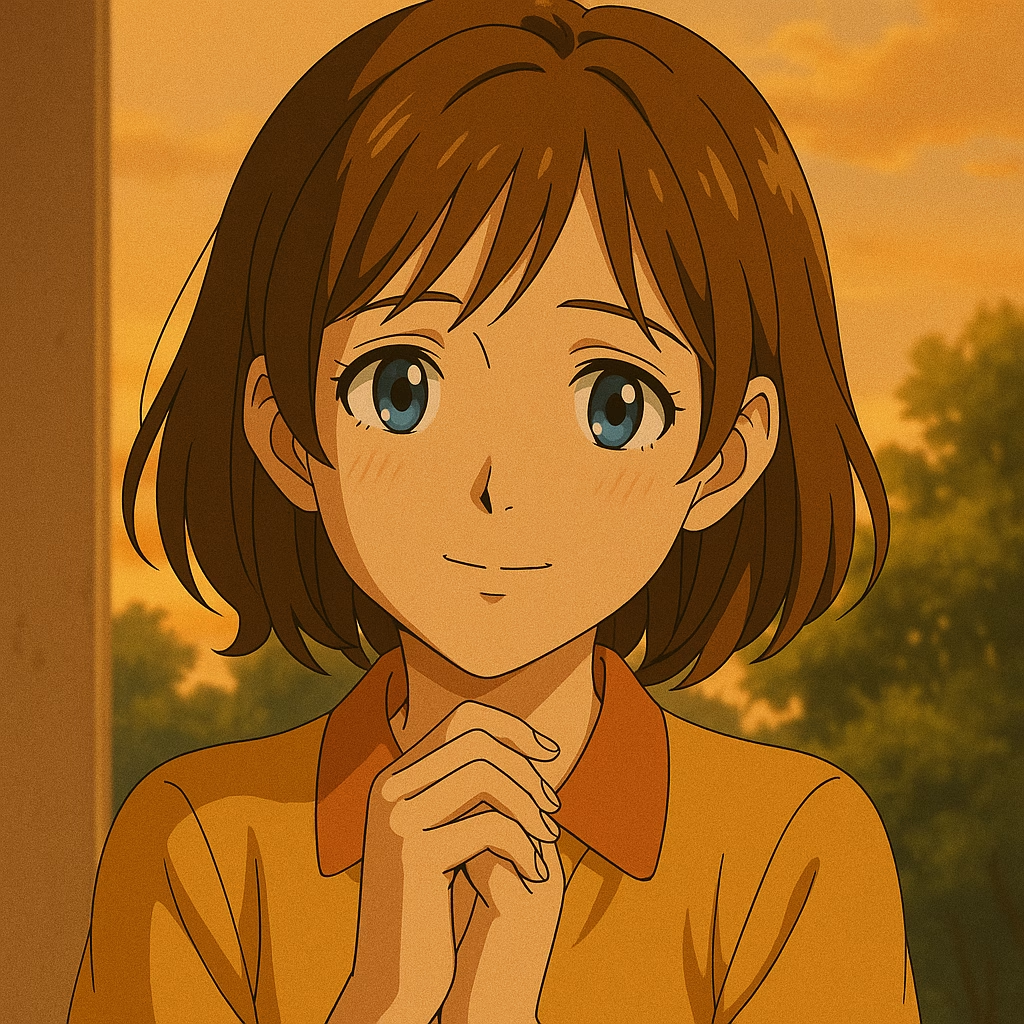
自己肯定感は、特別な才能がある人だけが持てるものではありません。
むしろ、日常の中で少しずつ「自分を認める」積み重ねをしていけば、誰でも育てていける感覚です。
これまで見てきたように、自己肯定感が低いと、失敗を恐れたり、人の目を気にしたりと、キャリアの流れを自分で止めてしまうことがあります。
しかし、裏を返せば——自分を少し信じるだけで、動き出す力が戻ってくるということでもあります。
大事なのは、「一気に変わること」ではなく「小さく進むこと」。
自己肯定感は“筋肉”のようなもので、少しずつ使ううちに自然と強くなっていきます。
ここでは、キャリアの中で自己肯定感を育てていくための3つのステップを紹介します。
焦らず、自分のペースで始めてみてください。
小さな成功を意識して「できた自分」を認める
多くの人は「大きな成果」を出したときだけ自分を褒めようとします。
でも、自己肯定感を育てるうえで大切なのは、小さな“できた”を丁寧に拾うことです。
たとえば、「昨日より早く出社できた」「会議で一言意見を言えた」「同僚の話を最後まで聞けた」。
ほんの些細なことでも、「自分は今日、これができた」と意識するだけで、心の中に少しずつ“自信の種”が育っていきます。
ポイントは、「完璧にできたかどうか」ではなく、「挑戦できたかどうか」を見ること。
たとえ結果が思い通りでなくても、「やってみた自分を認める」だけで、脳はポジティブな経験として記憶します。
この積み重ねが、いつの間にか“行動する勇気”を取り戻す土台になるのです。
自分の努力を言葉にして「内側から承認」する
他人からの評価や称賛に頼らず、自分で自分を認める習慣を持つことも大切です。
「今日もちゃんと仕事に向き合えたな」「緊張したけど、最後まで頑張れた」——そんな言葉を、自分自身にかけてあげるだけで効果があります。
声に出してもいいし、日記に書き留めても構いません。
ポイントは、「評価」ではなく「観察」に近い言葉を使うこと。
たとえば、「うまくやれた」よりも「今日、自分なりに工夫した」と表現すると、プレッシャーではなく自信を育てる言葉になります。
自分を認める言葉が増えるほど、心の中に“味方”ができていきます。
外の環境がどれだけ変わっても、この味方がいれば、自分を見失いにくくなります。
キャリアでの安定感とは、この“内なる支え”の強さに比例しているのかもしれません。
比較から離れ、「自分のペース」で進む勇気を持つ
自己肯定感を育てるうえで、もっとも難しく、そして大切なのが「他人との比較を手放す」ことです。
SNSや職場で、他人の成果や華やかな経歴を見て焦る気持ちは自然なこと。
でも、その比較が続くと、自分の成長を感じる余裕がなくなってしまいます。
人それぞれ、積み上げてきた経験も、持っている強みも違います。
「自分は自分のタイミングで進んでいる」と受け止めることができると、心はぐっと軽くなります。
比較をやめるコツは、「昨日の自分」と比べること。
昨日より少し前に出られたら、それで十分。
その小さな進歩を大切にしていくうちに、自分のペースで進む力が育っていきます。
他人の速度に合わせなくてもいい。
あなたのキャリアは、あなた自身が主人公です。
自分を責める働き方から抜け出す:自己肯定感を育てる第一歩
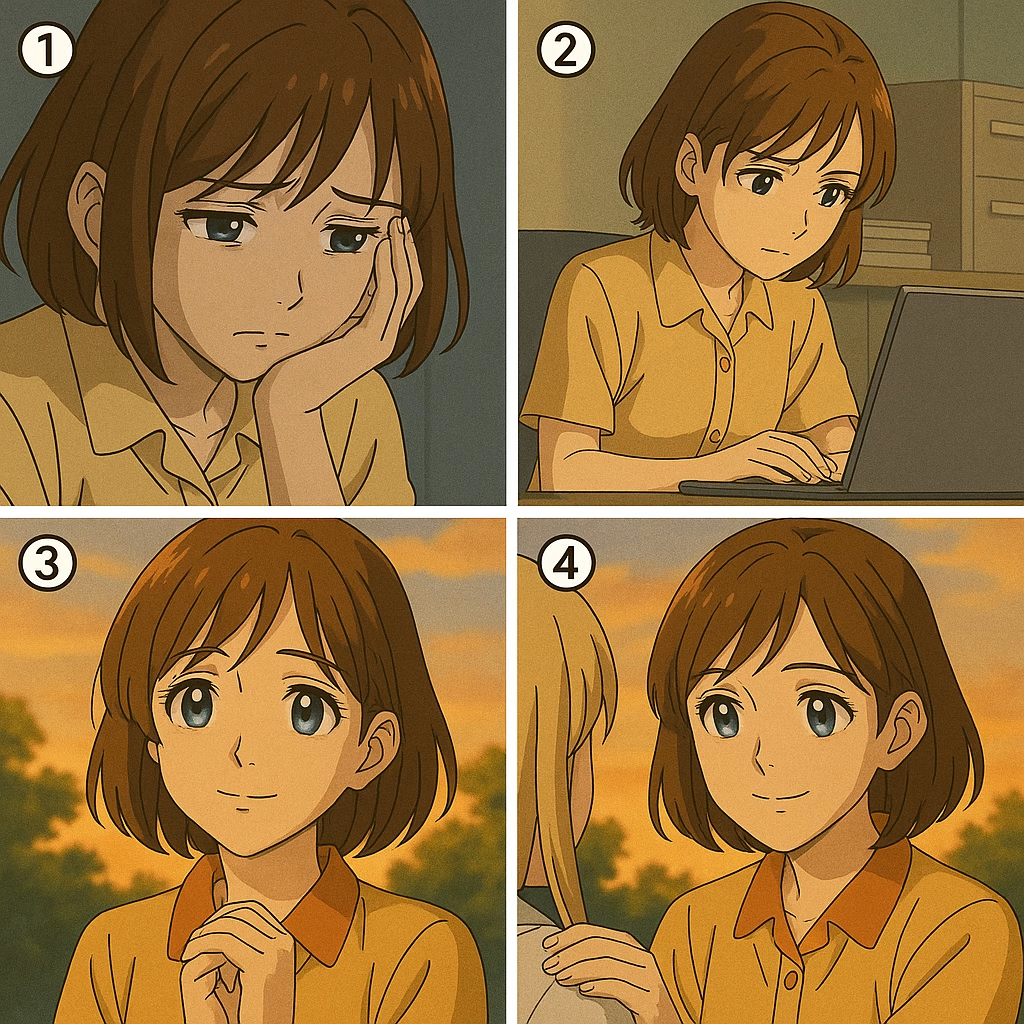
キャリアでつまずいたとき、多くの人は「もっと努力しなきゃ」「自分が弱いからだ」と考えがちです。
でも、本当は“努力不足”ではなく、“心のエネルギーがすり減っている”だけかもしれません。
自己肯定感が低い状態では、どれだけ頑張っても成果が感じられにくく、むしろ焦りや不安が増えてしまいます。
そんなときに必要なのは、さらに頑張ることではなく、「自分を支え直すこと」。
誰かに話を聴いてもらいながら、自分の考え方や感情のクセに気づくことで、少しずつ心の流れが変わっていきます。
カウンセリングは、その“気づき”を生む場所です。
答えを押しつけられる場所ではなく、自分の中にある答えを一緒に探していく時間。
「自分のことをもっと理解したい」
「今の働き方を見直したい」
そんな小さな気持ちからでも大丈夫です。
自分を否定する声に耳を傾けるより、少しだけ“本当の自分”の声を聴く時間を持ってみませんか?
その静かな一歩が、キャリアを、そしてあなた自身の未来をやさしく動かしていくはずです。


を軽くする方法-150x150.avif)


