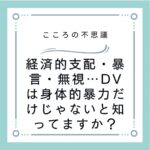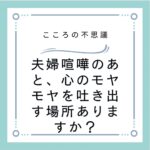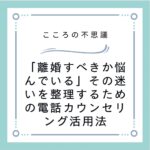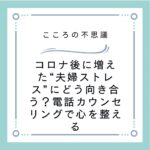心が安定しない時に行うべき行動3選

ご訪問ありがとうございます。
リ・ハート代表カウンセラーの佐藤です。
今回は「心が安定しない時に行うべき行動3選」というテーマでお話していきたいと思います。
誰しもが心の浮き沈みを経験したことがあると思います。そして、自分なりに対策をとってみたり、時間の経過とともに改善されるのを待ったりしています。
心は大きなストレスを受けたり、思うように物事が進まなかったりした時に安定しない状態になります。そうならないことが一番ですが、誰しもがそういった状況を経験するもので、大事なのは心が安定しない状況を如何に短くするか、そして不安定な状況を軽くするかということです。
心が安定しない時にこういったことを行うと早く抜け出せる可能性がある、不園庭な状況を軽減することができるといった内容を紹介していきますので、興味のある人は最後までお付き合いください。
投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー
-
【経歴】
・キャリアカウンセラー15年
・心理カウンセラー10年
※相談件数10,000件以上
【主な相談内容】
1.ストレス管理とメンタルケア
・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。
・仕事や家庭でのストレス解消法。
2.自己理解と自己成長
・自己肯定感を高めたい。
・自分の強みや価値観を明確にしたい。
3.人間関係の悩み
・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。
・対人関係における不安や緊張感への対処法。
4.不安や恐怖の克服
・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。
・パニック障害や全般性不安障害のケア。
5.うつ症状や気分の浮き沈み
・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。
・抑うつ状態から抜け出したい。
6.人生の転機や変化への対応
・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。
・新しい環境への不安や戸惑い。
7.恋愛や夫婦関係の悩み
・パートナーシップの問題解決。
・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。
8.自己批判やネガティブ思考の改善
・自分を責めすぎる傾向を変えたい。
・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。
9.家族関係や親子間の問題
・子育ての悩み。
・親や家族との関係性の見直し。
10.生きる意味や自己実現の探求
・人生の目的を再確認したい。
・自分らしい生き方を見つけるサポート。
【アプローチ方法】
1.傾聴を重視したカウンセリング
・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。
・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。
2.クライアント中心療法
・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。
・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。
3.認知行動療法(CBT)
・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。
・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。
4.ナラティブセラピー
・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。
・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。
5.対話を通じた柔軟なサポート
・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。
・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。
最新の投稿
目次
1.心が不安定である自分を認める
心が不安定になるような出来事があった場合に、心が不安定になっていることを自覚している人は多いです。しかし、その中で心が不安定になっている自分を認めている人は少ないです。
心が不安定である自分を認めるとはどういうことか。簡単にいうと、心が不安定になっている自分を受け入れるということです。
・自分は強い人間だから、こんなことで心が不安定になっている場合ではない
・強い気持ちで乗り越えなくては
・誰かに心が不安定であることを知られたくない
こういった気持ちになっている場合は、心が不安定になっている自覚はあるが受け入れることができていないと言えます。心が不安定であることを弱い人間、ネガティブな要因として捉えていると、なかなか受け入れることができないのです。確かに自分の弱さとして心の不安定を捉えていると、受け入れたくないですよね。
ここで大事なのは、心が不安定になることは弱いことではないということです。誰しもが心が不安定になっている時期は経験していますし、その事自体は全くネガティブなことではない、この認識を持つことで心の不安定を受け入れることができる、認めることができるようになります。
心が不安定であることを受け入れることができない人の特徴は、自尊心が高い人、いわゆるプライドが高い人とその真逆の人、自分に全く自信がない人です。この2タイプにおける特徴は自分が普通ではないと思っていることです。普通ではないので、「普通の人は心が不安定になる時期があるもの」に自分が該当していると思えないのです。
自尊心が高い人は自分はメンタルが強いから大丈夫と思ってしまう傾向があり、自分に自信が全くない人は自分だからこんなに心が不安定なんだと思ってしまう傾向にあります。そこで、この2タイプの人も含めるために使う表現が「誰しも」です。「誰しも」を使うことで、自分自身の心が不安定になっている状況も誰しもが経験することだから問題ないと思うことができ、受け入れることができるようになります。
ただ、自分自身でいきなりこの考え方ができるようになるかというとなかなか難しいです。カウンセリングを受け自分自身の全てを受け入れることができる基盤を作ることが大切です。
上記の話は周りの人で該当するような人がいた場合に、その人を理解するためにお役立てください。また、自分が該当しているかも、という人は是非リ・ハートの電話カウンセリングをご検討くださいね。
2.ルーティンを作る
心が不安定になる1つの要因に、いつもとは違うことが起きるということがあります。例えば、いつも決まった時間に電話してくる彼女(彼氏)から連絡がなくて不安になった、という経験はありませんか?例えばこれが不定期で連絡してくる彼女(彼氏)であれば特に不安を覚えることはないでしょう。いつもあることがない、もしくはいつもはないことがある時に不安を感じるものなのです。
上記で挙げた内容は、自分に対して周りで起きているルーティンですが、ここでのルーティンは自分で作ることです。自分に対して周りで起きているルーティンは、自分でコントロールすることができないため、心の安定の面で考えると不安要素になります。しかし、自分で自分に対して作るルーティンは、自分でコントロールできるものなので、心の不安要素ではなく安定供給してくれるものになってくれます。
自分で作ったルーティンをずっと行っていれば大丈夫、いつもと一緒という安心感を与えてくれます。もちろん、ルーティンをやっていても失敗することもあるでしょう。しかし、その失敗した時でもいつもと同じようにやってだめだったから仕方ないと割り切ることができます。
自分の中でのルーティン、ぜひ作ってみてくださいね。
3.心が安定するまで動かない
心が不安定な状態で感じている不安を解消するために行動し、更に大きな不安を感じてしまってより心が不安定になってしまった、という話は少なくありません。心が不安定な状態ですと、余裕がなくなってしまい焦りが生じてしまう可能性が高くなります。焦って行動を起こすともっと悪いことが起きる可能性が高くなってしまいます。
よって、心が不安定な状態の時には、まずはじっくりと腰を据えて現状を静観することです。この時に「さあ、どうなるか見てみよう」くらいの感じで客観的に見ることができると良いですね。どうしても自分のこととして捉えてしまうと、早く何か考えて行動を起こしたいと思ってしまいます。
この客観的な視点に関しては、カウンセリングを受けると身に付けることができます。自分自身どうしても自分のこととして物事を捉え過ぎてしまい、すぐにカッとなってしまう、ムキになってしまうという人は、リ・ハートの電話カウンセリングをご検討ください。
4.まとめ

「心が安定しない時に行うべき行動3選」というテーマでお話してきましたが、いかがでしたか?
心が不安定である自分を認め、自分のルーティンを作り、心が安定するまでは客観的な視点で静観する。これを行っていけば自ずと心が不安定な状態になりにくくなりますし、なった場合も早期に復活することができます。
自分自身でも取り組むことができる部分もありますが、心が不安定になることが多い人はなかなか自分で取り組んでいくことは難しいと思います。そういった時に、カウンセリングを活用すると今回紹介した3つの行動をとれるようになります。
心が不安定になっている自分が嫌で変わりたいという人は、ぜひリ・ハートの電話カウンセリングをご活用ください。
この記事を読んだ人はこちらも読んでいます【こころを整えるために必要な3つの条件】