職場の人間関係がつらい原因は共感力不足?傾聴スキルでストレスを減らす方法
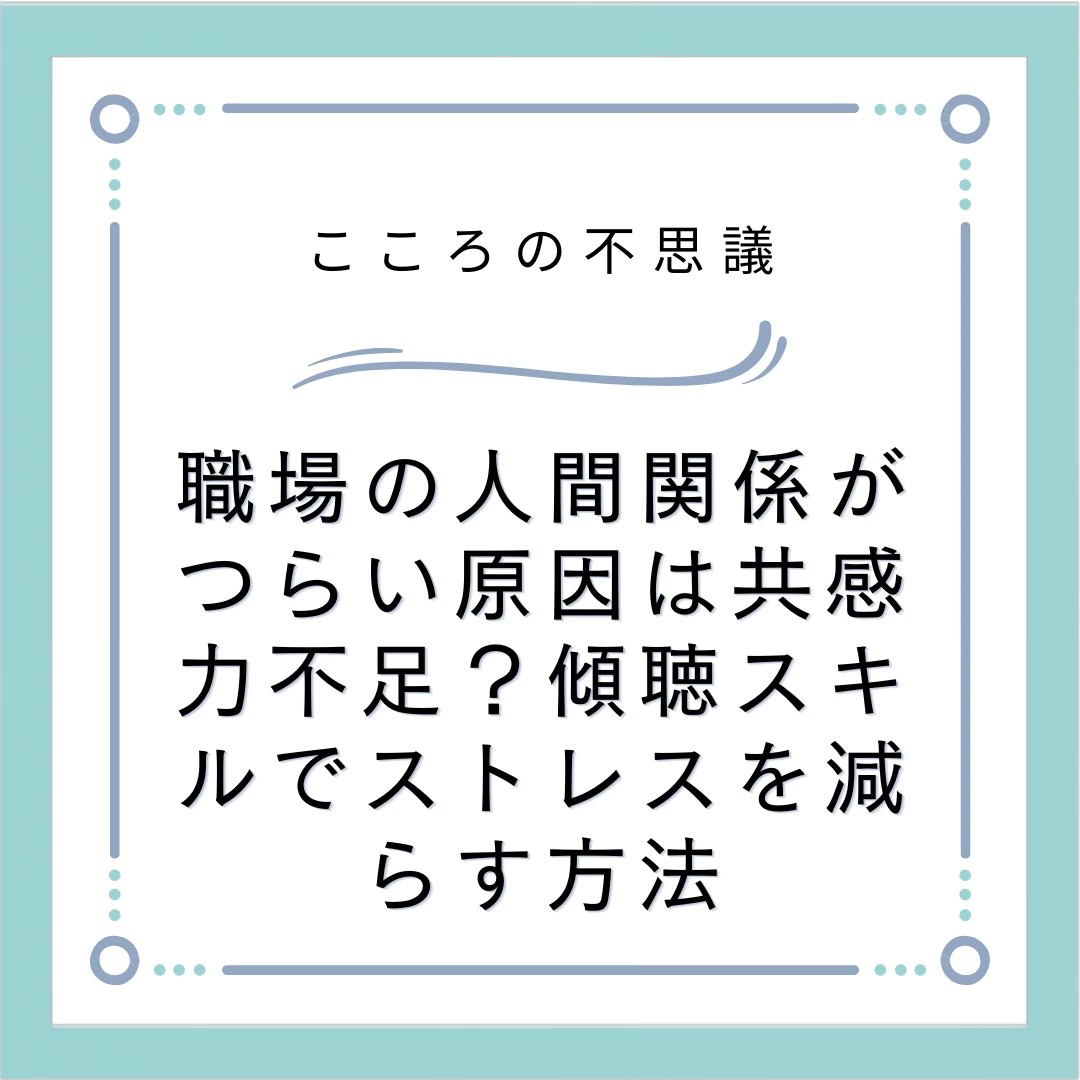
職場の人間関係って、仕事そのものより疲れることありますよね。ちょっとした言い方の違いで気まずくなったり、「何か怒ってる…?」「自分、嫌われてるのかな?」とモヤモヤしたり。実はこの“すれ違い”の背景には、意外と気づかれにくい 共感力の不足 が関わっていることが多いんです。
相手の気持ちを想像できないまま会話が進むと、誤解が生まれやすくなり、距離がどんどん開いてしまいます。そして、そのズレが積み重なるほど「話しにくい」「相談しづらい」という空気が広がっていき、職場のストレスはますます増えていきます。
でも、ここでちょっと視点を変えてみると、状況をラクにできる方法があります。それが 傾聴(けいちょう)スキル。
「ただ話を聞けばいいんでしょ?」と思われがちですが、実はもっと奥が深くて、共感力を育てるための“土台づくり”にもなる大事なコミュニケーション方法なんです。
本記事では、「なぜ職場の人間関係がうまくいかないのか?」という原因をひも解きながら、共感力不足がどんな影響を与えるのか、そして傾聴がどう解決のカギになるのかを分かりやすく紹介していきます。今日からすぐに実践できるコツも交えて解説するので、ぜひ肩の力を抜きながら読んでみてくださいね。
この記事でつかめる心のヒント
- 職場の人間関係の疲れは共感力不足が原因: 気づかれにくい共感力の不足により、誤解やすれ違いが頻発し、コミュニケーションがうまくいかなくなることが、職場のストレスと疲れの原因です。
- 共感力の低下が誤解と距離の拡大を招く: 共感力が不足すると、相手の気持ちを想像できず誤解が増え、関係が悪化して遠ざかるため、良好な職場関係が難しくなります。
- 傾聴スキルは共感力を育てる重要なコミュニケーション技術: ただ話を聞くのではなく、相手の気持ちを理解し共感を深めるための技術が傾聴スキルであり、これが共感力向上の土台となります。
- 傾聴スキルは練習と意識的な実践で身につく: 相手の話に集中し、共感的に耳を傾ける練習や質問を重ねることが、傾聴スキル習得への近道です。継続的な実践が上達を促します。
- 今すぐできる関係改善のコツは共感的聴き方の実践: 相手の話に適切にリアクションし、共感的に聴くことを意識するだけで、コミュニケーション能力が高まり、職場の人間関係を良くすることが可能です。
リハートカウンセリング.comを利用される方の主なご相談内容
投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー
-
【経歴】
・キャリアカウンセラー15年
・心理カウンセラー10年
※相談件数10,000件以上
【主な相談内容】
1.ストレス管理とメンタルケア
・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。
・仕事や家庭でのストレス解消法。
2.自己理解と自己成長
・自己肯定感を高めたい。
・自分の強みや価値観を明確にしたい。
3.人間関係の悩み
・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。
・対人関係における不安や緊張感への対処法。
4.不安や恐怖の克服
・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。
・パニック障害や全般性不安障害のケア。
5.うつ症状や気分の浮き沈み
・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。
・抑うつ状態から抜け出したい。
6.人生の転機や変化への対応
・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。
・新しい環境への不安や戸惑い。
7.恋愛や夫婦関係の悩み
・パートナーシップの問題解決。
・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。
8.自己批判やネガティブ思考の改善
・自分を責めすぎる傾向を変えたい。
・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。
9.家族関係や親子間の問題
・子育ての悩み。
・親や家族との関係性の見直し。
10.生きる意味や自己実現の探求
・人生の目的を再確認したい。
・自分らしい生き方を見つけるサポート。
【アプローチ方法】
1.傾聴を重視したカウンセリング
・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。
・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。
2.クライアント中心療法
・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。
・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。
3.認知行動療法(CBT)
・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。
・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。
4.ナラティブセラピー
・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。
・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。
5.対話を通じた柔軟なサポート
・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。
・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。
目次
- ○ 職場の人間関係がつらくなる原因とは?
- ・些細なコミュニケーションの誤解が積み重なる
- ・相手の反応を“自分への評価”として受け取ってしまう
- ・本音を言えない環境がストレスを増幅させる
- ○ 共感力不足が人間関係をこじらせる理由
- ・相手の気持ちを想像できないと誤解が増える
- ・“自分の枠”で相手を判断してしまう
- ・気持ちに寄り添えないと相手が心を閉ざす
- ○ 傾聴スキルが共感力を育て、人間関係をやわらかくする
- ・「聞く」のではなく「受け止める」に意識を変える
- ・相手のペースに合わせるだけで安心感が生まれる
- ・「否定しない姿勢」が信頼を深める
- ○ 共感力と傾聴が職場の人間関係をラクにしてくれる
- ・自分の心に余裕が生まれ、反応が柔らかくなる
- ・相手との距離が縮まり、信頼関係が育つ
- ・無理なく続けられる“日常の小さな習慣”になる
- ○ 職場の人間関係がラクになるヒント:共感力と傾聴が心を軽くしてくれる
職場の人間関係がつらくなる原因とは?

仕事そのものより、人とのやり取りでぐったりしてしまう…そんな経験、誰にでもありますよね。職場って、毎日顔を合わせる相手だからこそ、ちょっとした一言や表情の変化に敏感になりやすい場所です。例えば、上司が忙しそうなときに話しかけて素っ気なくされたり、同僚に相談したら意外と冷たい反応が返ってきたり。そうした小さなすれ違いが積もり積もって、「自分はここでうまくやれていないのでは?」という不安につながることもあります。
実は、こうした人間関係の“ギクシャク”の根っこには、特別なトラブルがあるわけではなく、もっとシンプルな“気持ちの伝わらなさ”が大きく関係しています。つまり、お互いの気持ちや状況を汲み取れないまま会話が進んでしまうことで、誤解がどんどん生まれてしまうんです。相手に悪気がないと分かっていても、心が追いつかない瞬間ってありますよね。
そして、こうしたズレをそのままにしておくと、「どうせ分かってもらえない」「話しても意味ない」と感じるようになり、だんだん距離を取ってしまいます。結果として、職場で孤立してしまったり、必要以上に遠慮してストレスを抱え込む原因にもなってしまうのです。
ここでは、そんな“すれ違い”がどう生まれるのか、そしてなぜ職場では特に起こりやすいのかを丁寧に紐解いていきます。
些細なコミュニケーションの誤解が積み重なる
職場で起きる人間関係のトラブルって、実は大きな事件が原因になることは少なく、多くが「ほんの少しの誤解」から始まります。例えば、相手が忙しくて余裕がないだけなのに「冷たい」と受け取ってしまったり、何気ないアドバイスが「指摘された」と感じて落ち込んでしまったり。
この“ズレ”が厄介なのは、お互いにそのつもりがないのに心の距離だけが広がっていってしまうこと。
もちろん人間は機械じゃないので、相手の本心を100%理解することは難しいけれど、「もしかして誤解してるかも?」という視点を少し持つだけで、気持ちがかなりラクになります。
誤解そのものより、その誤解に気づけないまま進むことが、関係を悪化させる最大の原因なんです。
相手の反応を“自分への評価”として受け取ってしまう
職場では、自分の言動が仕事の評価に直結しやすいため、相手の態度を「自分がどう見られているか」と結びつけてしまいがちです。
例えば、上司がそっけないと「自分がミスしたのかな?」と感じたり、同僚の表情が暗いと「何か気分を害した?」と自分を責めてしまったり。
しかし実際には、相手の態度のほとんどは“その人自身の事情”によるもので、こちらとは関係がないことが多いんです。
でも、そう分かっていても気になっちゃうのが人間のややこしいところ。
こうした“自分軸で受け取ってしまうクセ”があると、職場の人間関係はますます疲れやすくなります。
まずは「相手の態度=自分のせい」と直結させない癖をつけることが、心を軽くする第一歩。
本音を言えない環境がストレスを増幅させる
職場では「空気を読む」「迷惑をかけない」などの配慮が求められるため、どうしても本音を抑えがちになります。
本当は困っているのに言えない、本当は手伝ってほしいのに頼めない、そんな状況が続くとストレスはどんどん蓄積していきます。
さらに、本音を言えない環境では誤解も起きやすく、「自分の考えが伝わらない」「気持ちを分かってもらえない」と感じてしまいます。
ここでやっかいなのが、“話さないことで守っているつもりが、逆に関係を悪化させてしまう”ということ。
お互いの気持ちが見えないと、その空白に不安が入り込み、結果として距離が遠くなるのです。
本音を出すのは勇気がいるけれど、少しずつ安心できる関係をつくることが、職場のストレス軽減につながっていきます。
共感力不足が人間関係をこじらせる理由
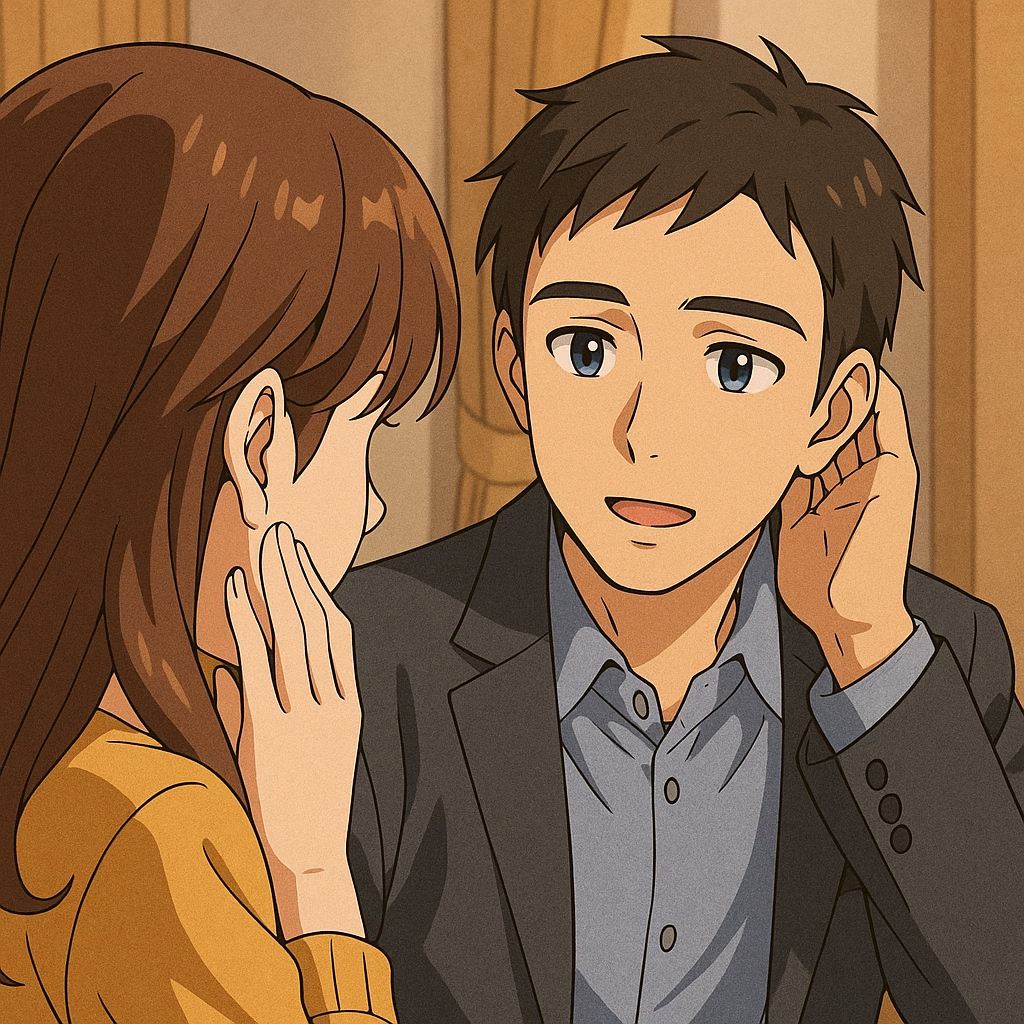
職場の人間関係がぎこちなくなる背景には、実は“共感力”の欠けがじわじわ影響していることが多いんです。共感力と聞くと、なんだか特別なスキルのように感じるかもしれませんが、要は「相手が今どう感じているかを想像しながら関わる力」。これが弱まってしまうと、相手の気持ちを取り違えたり、意図しない受け取り方をしてしまったりと、コミュニケーションのズレが一気に増えていきます。
例えば、相手が疲れているだけなのに「冷たい」と感じたり、忙しくて返事が遅れただけなのに「無視された」と思ってしまうことがありますよね。そうした誤解は、共感力が弱いと気づきにくく、気づけないまま心の距離がどんどん広がってしまいます。
しかも厄介なのは、共感力が欠けている状態って本人も気づきにくいということ。「自分は普通に接しているつもり」でも、相手からすると「話しづらい」「理解してもらえない」と感じてしまうケースが少なくありません。
ここでは、なぜ共感力の不足が職場の人間関係に大きな影響を与えるのか、その背景を分かりやすく紐解きながら、読み手が“あ、これ自分にもあるかも…”と気づける視点を届けていきます。共感力が低下したときに起こりやすい気持ちのすれ違いや、相手の反応をどう受け取りやすくなるのかなど、心の仕組みをやわらかく説明していきます。
相手の気持ちを想像できないと誤解が増える
共感力が不足していると、相手の気持ちを“そのままの表面だけ”で判断してしまいがちです。
例えば、同僚が黙りがちな日があったとして、本当は家庭のことで悩んでいるかもしれないし、体調が悪いだけかもしれない。でも共感力が弱い状態だと、そこに想像力が働かず、「機嫌悪いの?」「自分、何かした?」と自分軸で考えてしまいます。
すると、相手の意図とは全然違う方向に誤解が広がり、気まずさが生まれやすくなります。
もちろん誰だって毎日他人の心の中を完璧に理解するのは難しいけれど、“今この人はどう感じているんだろう?”とワンクッション置いて考えるだけで、関係が驚くほどスムーズになります。
共感は特別な才能ではなく、ちょっとした想像力の積み重ね。意識するかどうかで、人間関係の雰囲気はガラッと変わるんです。
“自分の枠”で相手を判断してしまう
共感力が弱まっていると、どうしても“自分の価値観”“自分の基準”で相手を見てしまいがちです。
例えば、自分ならすぐ返事をするタイプだから相手が返事をしないと「やる気がない」と判断したり、自分が丁寧に話をするタイプだからフランクな人を見ると「雑に扱われた」と感じたり。
これって実は、相手とのコミュニケーションを“自分基準の物差し”で測ってしまっている状態なんです。
相手には相手のペースや事情があるのに、その背景を考えずに「こうあるべき」で判断してしまうと、すれ違いがどんどん増えていきます。
共感力とは、相手の世界の見え方や事情を“一旦そのまま受け止める柔軟さ”でもあります。
少し視点を広げて、自分とは違う考えがあることを認められると、コミュニケーションがぐっと楽になりますよ。
気持ちに寄り添えないと相手が心を閉ざす
共感力が不足している状態が続くと、相手は「この人に何を言っても分かってもらえない」と感じてしまい、徐々に心を閉ざすようになります。
本当は悩んでいるのに相談しなくなったり、必要なことすら話しづらくなったり。
すると表面的なやり取りばかりになり、職場の人間関係はどんどん淡白で距離のあるものになってしまいます。
人は誰でも「理解されたい」「受け止めてもらいたい」という気持ちを持っています。
その願いが満たされないと、安心して関われないし、本音も出せません。
逆に、少しでも「この人はちゃんと聞いてくれる」と感じられると、一気に関係が柔らかくなります。
共感力は、相手の心を開くための“鍵”のようなもの。そこが欠けていると、どれだけ努力しても関係が深まりにくいんです。
傾聴スキルが共感力を育て、人間関係をやわらかくする

ここまで、人間関係がこじれる背景には「共感力の不足」があることを見てきましたが、じゃあどうすれば共感力って育つの?と気になるところですよね。実は、共感力を高めるうえで一番効果的なのが “傾聴(けいちょう)” というスキルなんです。
「話を聞くことが大事」とはよく言われますが、傾聴はその一歩先。相手の言葉だけでなく、気持ちや意図まで含めて“受け止める”スタイルの聴き方です。これは特別な人だけができるスキルではなく、ちょっとした意識の変化から誰でも少しずつ身につけていけます。
傾聴がうまく働くと、相手は「ちゃんと理解しようとしてくれている」と安心し、自然と本音を話しやすくなります。結果的に誤解が減り、信頼関係もスッと深まっていきます。
逆に、話を聞いているつもりでも“評価”“アドバイス”“否定”が混じってしまうと、相手は肩に力が入ってしまい、気持ちを閉ざすきっかけになります。
ここでは、傾聴がどう共感力を育て、職場のコミュニケーションをどれほど変えてくれるのか、その実践的なポイントを分かりやすく紹介していきます。今日から少しずつ取り入れるだけで、人との距離感がふんわり変わっていきますよ。
「聞く」のではなく「受け止める」に意識を変える
私たちは普段、人の話を聞いているようで実は“内容の正しさ”ばかりに気を取られがちです。
「それは違うよ」「こうした方がいいと思うよ」と、つい反応したくなることってありますよね。でも傾聴の第一歩は、この“すぐに判断するクセ”をいったん横に置くこと。
傾聴では、相手の言葉を「合ってるかどうか」ではなく、「この人は今こう感じているんだな」と受け止めることが大切です。
評価を挟まない聞き方をすると、相手は安心し、「この人には本音を話して大丈夫かも」と感じやすくなります。
これって理屈よりも“空気”として相手に伝わる部分で、少し意識するだけでも会話の雰囲気がグッと柔らかくなるんです。
自分の意見を言うのは、まず相手の気持ちを受け止めてから。それだけでコミュニケーションの質は驚くほど変わります。
相手のペースに合わせるだけで安心感が生まれる
傾聴では、「相手のペースに寄り添う」こともとても大事なポイントです。
話すスピード、間の取り方、言いよどみ…そうしたものにはすべて、その人の気持ちがにじんでいます。
焦っているときは早口になるし、不安があるときは言葉が詰まりやすい。当たり前のことだけど、いざ会話になるとつい忘れてしまいがちですよね。
相手が言い淀んでいるときに急かしたり、「つまりこういうことでしょ?」とまとめてしまうと、相手の心のスペースを奪ってしまいます。
逆に、相手のペースを尊重して待てると、「この人は自分を急かさない」と安心感が生まれ、話しやすさが一気に増します。
テンポを合わせるって、難しそうに見えてすごくシンプル。
相手がゆっくり話すならゆっくり聴く、迷いながら話すならその迷いも一緒に受け止める。
これだけで職場の空気は驚くほど落ち着いたものになります。
「否定しない姿勢」が信頼を深める
傾聴の大切なポイントのひとつが“否定しない姿勢”です。
相手が話しているとき、「いや、それは違うと思うな」「考えすぎじゃない?」と口を挟みたくなることがありますよね。でもこれをやってしまうと、たとえ悪気がなくても、相手は「この人には理解されない」と受け取ってしまいます。
否定しない姿勢は、賛成することとは別物。
「その気持ちになるのも分かるよ」「そう感じているんだね」と、ただ気持ちを受け止めるだけでいいんです。
それだけで、相手は“安心して話せるスペース”があると感じ、心の扉を少しずつ開いてくれるようになります。
特に職場では、意見の違いや価値観のギャップが出やすい環境だからこそ、否定されない経験は信頼につながります。
傾聴には、相手の気持ちに寄り添いながら関係を深める力があり、その姿勢ひとつで職場の雰囲気はゆるやかに変わっていくんです。
共感力と傾聴が職場の人間関係をラクにしてくれる
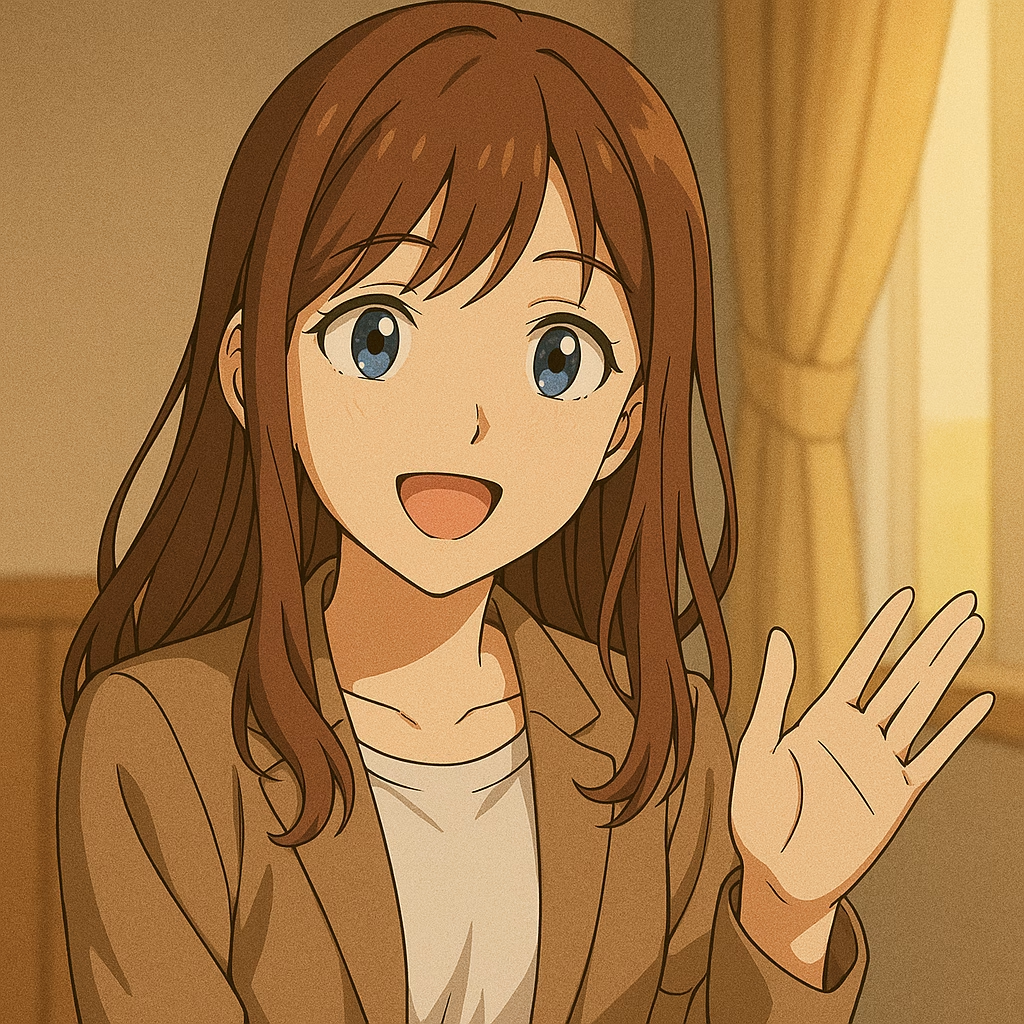
ここまで“共感力不足が起こすすれ違い”と“傾聴がそのズレを埋めてくれる理由”を見てきましたが、最後に大切なのは「少しずつ実践するだけで、職場の人間関係は確実に変わっていく」ということです。共感や傾聴って、特別な才能が必要なものではなく、毎日の中で気づいた瞬間にちょっと意識を向けるだけで育っていきます。
誰かが急に劇的に変わるわけではないけれど、あなたが“相手の気持ちを受け止める姿勢”を持つことで、周りの反応は驚くほど柔らかくなります。むしろ、人間関係の改善は「自分から変える」のがいちばん早い方法なんです。
職場は、価値観も性格も違う人たちが集まる場所。だからこそ真面目に向き合おうとすると疲れやすいし、気を遣いすぎて消耗してしまうこともあります。でも、共感力を少し育て、傾聴の姿勢を持てるようになるだけで、相手の気持ちの見え方が変わり、心の余裕が自然と増えていきます。
ここでは、共感と傾聴を日常に取り入れることで起きる変化や、実際にどんなふうに人間関係がラクになるのかを、より具体的に紹介していきます。今日から無理なく続けられるコツも含めて、気持ちがほっとする未来のイメージを作っていきましょう。
自分の心に余裕が生まれ、反応が柔らかくなる
共感力や傾聴を取り入れ始めると、まず変わるのは「自分の心の余裕」です。
相手の態度に翻弄されにくくなり、「あ、この人も大変なんだな」と自然に考えられるようになります。
心に余裕ができると、反射的にイラッとしたり、落ち込んだりする回数がぐっと減ります。
これは“相手を理解する力”が育つことで、物事を一方向から見るのではなく、多面的に受け取れるようになるから。
視野が広がると、同じ状況でも感じ方が変わり、結果として人間関係に振り回されにくくなるんです。
そして、こちらの反応が柔らかくなると、相手も話しやすくなるし、余計な緊張が消えていきます。
自分の心のゆとりは、まわりにも自然と伝わるもの。
“自分が変わると環境も変わる”ってこういうことなんだなと実感できるはずです。
相手との距離が縮まり、信頼関係が育つ
共感や傾聴を続けていると、相手の表情や反応がほんの少しずつ変わってきます。
例えば、今まで短い返事しかくれなかった同僚が、少しだけ話を深めてくれるようになったり、上司がこちらの意見に耳を傾けてくれるようになったり。
これは、相手が「この人は自分の話をきちんと聞こうとしてくれる」と感じるからこそ起きる変化です。
人は、自分を否定しない相手、自分の気持ちを受け止めてくれる相手には、自然と心を開いていきます。
こうした小さな信頼の積み重ねが、のちに大きな関係性の安定につながっていくんです。
また、距離が縮まることで仕事の協力もしやすくなり、職場全体がスムーズに動くようになります。
人間関係の良さは、生産性にも影響するので、共感力の向上は思った以上に大きな効果を持っています。
無理なく続けられる“日常の小さな習慣”になる
共感や傾聴は、特別な場面で使うコミュニケーションではなく、日常のちょっとした瞬間に取り入れられる“小さな習慣”です。
例えば、相手が話し始めたときに「まず受け止めよう」と意識する、ペースを合わせてみる、否定せずに気持ちを聞いてみる。
こうした積み重ねは、一度に大きな変化を起こすわけではないけれど、確実に関係を優しい方向へ導きます。
続けやすいポイントは、無理に「完璧に傾聴しよう!」と思わないこと。
むしろ、気づいたときに少しだけ姿勢を整えるだけで十分です。
それでも、周りの人は敏感にその変化を感じ取ってくれるもの。
習慣として根づくと、共感力は自然と育ち、気づけば職場の空気が以前よりずっと温かく、話しやすいものになっています。
「相手を理解しようとする気持ち」が、何よりの職場改善の第一歩です。
職場の人間関係がラクになるヒント:共感力と傾聴が心を軽くしてくれる

職場の人間関係って、「何が正解なのか分からないまま頑張ってしまう場所」でもありますよね。
今回の【起承転結】を通して、関係がギスギスする背景には“共感力不足”という見えにくい原因があって、それを補ってくれるのが“傾聴”というシンプルだけど奥深いスキルだということをお伝えしました。
ただ、実際に日常で使おうとすると「これで合ってるのかな?」「相手の気持ちをどう受け止めればいいんだろう…」と迷うこともあると思います。
特に職場の関係は感情だけではなく役割や責任も絡むので、ひとりで抱えるとしんどくなりがちです。
そんなときこそ、カウンセリングのような“安心して話せる場所”を持つことが役に立ちます。
カウンセラーはあなたの話を否定せず、評価せず、丁寧に傾聴しながら、気持ちの整理を一緒にしていきます。
誰かに安全に話を聞いてもらうだけで、自分の心のクセや、人との関係でつまずきやすいポイントが少しずつ見えてくるんです。
そして、自分のことが理解できるほど、職場の人間関係は思った以上にラクになります。
共感力を育てることは、他人のためだけじゃなく、自分自身を守ることにもつながります。
もし今、「職場の人間関係で消耗しているな…」と感じるときは、ひとりで踏ん張らなくて大丈夫。
あなたに合ったコミュニケーションの取り方を一緒に見つけるお手伝いができます。
気軽に相談してみてくださいね。あなたが少しでも心軽く働けるように、しっかり寄り添います。





