「考えすぎ・我慢しすぎをやめたい」認知行動療法で学ぶ思考パターンの整え方
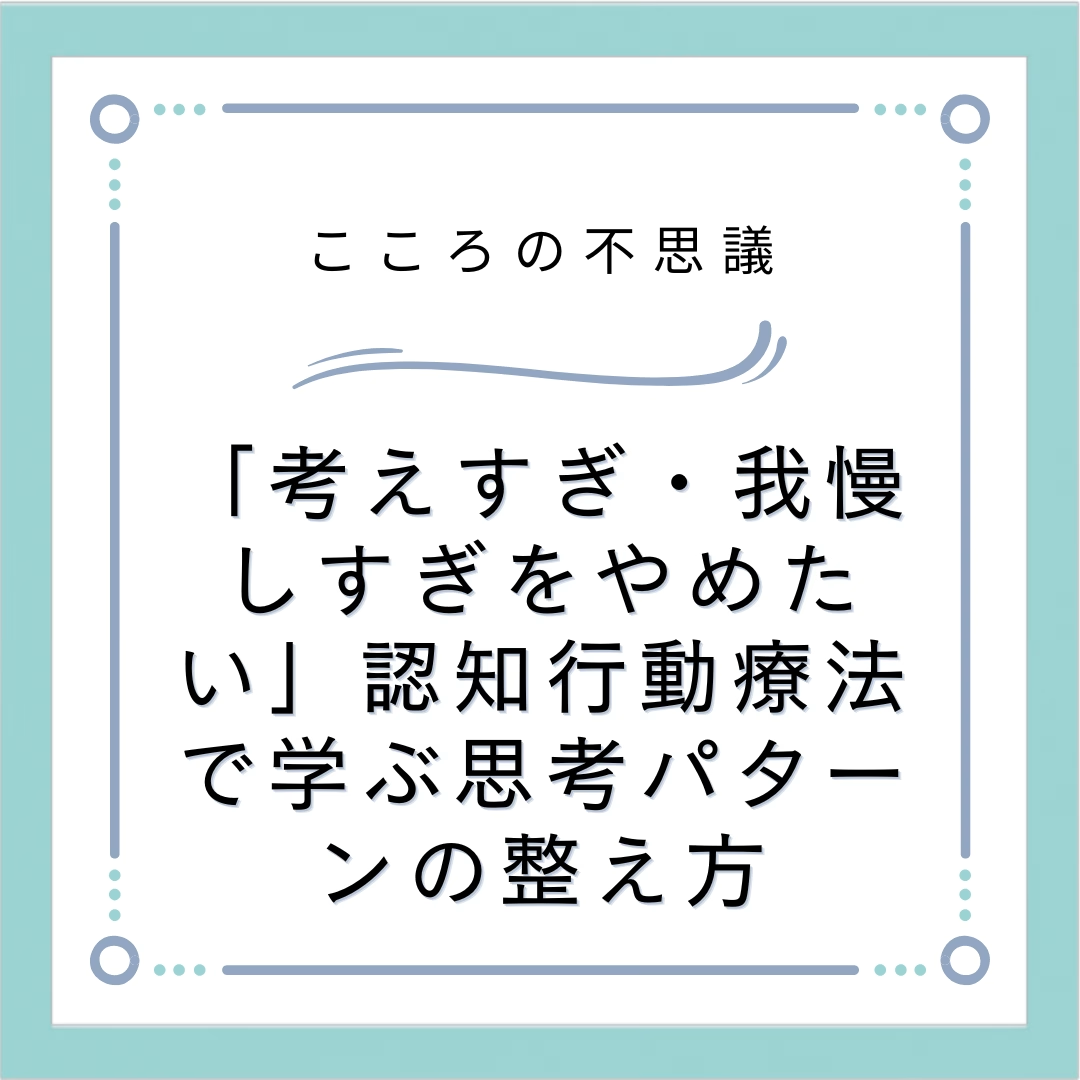
「つい考えすぎて眠れなくなる」「本当は嫌なのに、波風を立てたくなくて我慢してしまう」。そんな自分に気づいても、どう変えればいいのか分からない——。多くの人がこのような悩みを抱えています。頭の中では「もっと気楽に考えればいい」と分かっていても、心がついていかない。いつの間にか、“考えすぎ”や“我慢しすぎ”が習慣化してしまい、ストレスや不安を感じやすくなっているのです。
こうした思考のクセは、生まれ持った性格というより、これまでの経験や人間関係の中で形づくられた「認知パターン」が影響しています。例えば、「人に迷惑をかけてはいけない」「完璧にやらなければ認められない」といった無意識の思い込みが、行動や感情の幅を狭めていることもあります。
認知行動療法(CBT)は、そんな“自動的な思考の癖”を客観的に見つめ直し、より現実的で優しい考え方に整えていく心理療法です。考えすぎを止めようと無理に抑えるのではなく、「なぜ考えすぎてしまうのか」を丁寧にほどいていくアプローチ。この記事では、認知行動療法の視点から「考えすぎ」「我慢しすぎ」の背景を整理し、心に余裕を取り戻すためのヒントを紹介します。
この記事でつかめる心のヒント
- 考えすぎや我慢しすぎを改善する方法: 自分の思考パターンを客観的に見つめ直し、もっと現実的で優しい考え方に変えることが大切。認知行動療法(CBT)を使えば、無理なく心の余裕を取り戻せるよ。
- 認知行動療法(CBT)って何?どう役立つの?: CBTは、自動的な思考の癖を見直し、もっと穏やかで現実的な考え方に変える心理療法。これを利用すれば、ストレスや不安を軽減できるよ。
- 無意識の思い込みとは何?それがどう影響してる?: 無意識の思い込みは、「迷惑をかけてはいけない」や「完璧じゃないと認められない」などの考え。これらが行動や感情を狭め、考えすぎや我慢しすぎを引き起こすんだ。
- 考えすぎや我慢しすぎが習慣になる理由: これらの思考パターンは、長く繰り返すことで無意識に癖づき、自然と心の習慣になってしまうからだよ。
- 心に余裕を持たせるにはどうしたらいい?: 自分の思考や感情を客観的に見つめ直すことや、日常の中でリラックスする工夫を続けるのがおすすめ。認知行動療法の考え方も役立つよ。
電話カウンセリングのリ・ハートに訪れる方の主な検索キーワード
投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー
-
【経歴】
・キャリアカウンセラー15年
・心理カウンセラー10年
※相談件数10,000件以上
【主な相談内容】
1.ストレス管理とメンタルケア
・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。
・仕事や家庭でのストレス解消法。
2.自己理解と自己成長
・自己肯定感を高めたい。
・自分の強みや価値観を明確にしたい。
3.人間関係の悩み
・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。
・対人関係における不安や緊張感への対処法。
4.不安や恐怖の克服
・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。
・パニック障害や全般性不安障害のケア。
5.うつ症状や気分の浮き沈み
・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。
・抑うつ状態から抜け出したい。
6.人生の転機や変化への対応
・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。
・新しい環境への不安や戸惑い。
7.恋愛や夫婦関係の悩み
・パートナーシップの問題解決。
・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。
8.自己批判やネガティブ思考の改善
・自分を責めすぎる傾向を変えたい。
・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。
9.家族関係や親子間の問題
・子育ての悩み。
・親や家族との関係性の見直し。
10.生きる意味や自己実現の探求
・人生の目的を再確認したい。
・自分らしい生き方を見つけるサポート。
【アプローチ方法】
1.傾聴を重視したカウンセリング
・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。
・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。
2.クライアント中心療法
・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。
・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。
3.認知行動療法(CBT)
・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。
・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。
4.ナラティブセラピー
・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。
・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。
5.対話を通じた柔軟なサポート
・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。
・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。
最新の投稿
目次
- ○ 考えすぎ・我慢しすぎがつらい理由
- ・1. 「失敗したくない」という完璧主義の影響
- ・2. 「人に嫌われたくない」という承認欲求の罠
- ・3. 「我慢が美徳」という思い込みの根強さ
- ○ 認知行動療法で見直す「思考のクセ」
- ・1. 「出来事・思考・感情・行動」のつながりを整理する
- ・2. 「自動思考」を書き出してみる
- ・3. 「現実的で優しい思考」に置き換える
- ○ 柔軟な考え方を育てる練習
- ・1. 「別の視点」を探してみる練習
- ・2. 「完璧でなくていい」を口ぐせにする
- ・3. 「我慢する」より「伝える」を選ぶ勇気
- ○ 思考のバランスを整えて、心に余白を取り戻す
- ・1. 「考えすぎても大丈夫」と受け入れてみる
- ・2. 小さな「自分優先」を積み重ねる
- ・3. 「完璧な自分」ではなく「等身大の自分」と生きる
- ○ 「自分を責めない生き方」――認知行動療法で“心の整理”を始めてみませんか?
考えすぎ・我慢しすぎがつらい理由
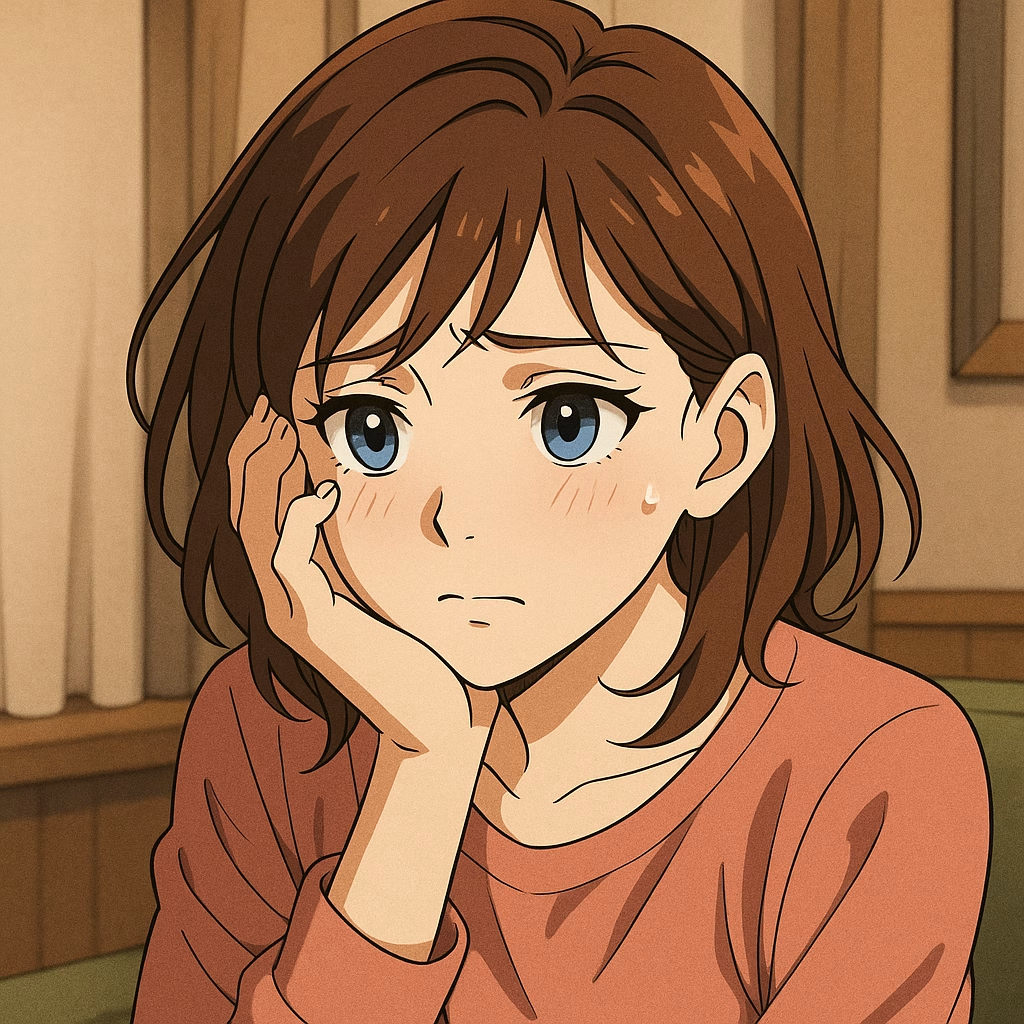
「どうして自分ばかり気を使ってしまうんだろう」「もう少し気楽に考えたいのに、つい深刻に考えてしまう」——そんな思いを抱えている人は少なくありません。実は、“考えすぎ”も“我慢しすぎ”も、心が弱いからではなく、「人に迷惑をかけたくない」「嫌われたくない」という思いやりや優しさの裏返しなのです。
しかし、その優しさが過剰になると、自分の気持ちを押し殺してしまい、ストレスが積もっていきます。相手を気づかうほどに、自分の中の本音が置き去りになり、「自分でも何を感じているのか分からない」と混乱してしまうことも。考えすぎて疲れ、我慢しすぎて心がすり減る。そんな状態を続けていると、心身のバランスが崩れ、イライラや無気力、さらには不安症状として現れることもあります。
つまり、「考えすぎ」「我慢しすぎ」はただの性格ではなく、**“自分を守るために覚えた生き方”**なのです。ここでは、その背景にある心理を少しずつ見ていきましょう。
1. 「失敗したくない」という完璧主義の影響
多くの人が考えすぎるのは、「間違えたくない」「悪く思われたくない」という完璧主義的な思考が根底にあるからです。完璧を目指すこと自体は悪いことではありませんが、常に“正しい答え”を探し続けると、心は休まる暇を失います。
たとえば、仕事でメールを送るときに「この言い方で失礼じゃないかな?」「もっといい表現があったかも」と悩み、送信後も何度も見返してしまう。そんな経験、ありませんか? これは、「失敗を避けたい」という気持ちが強すぎるサインです。
認知行動療法の視点で見ると、このような思考は「〜すべき」「〜でなければならない」という“べき思考”と呼ばれます。自分を追い込みやすく、結果的にストレスや不安を増やしてしまう原因になります。まずは、「完璧じゃなくても大丈夫」という柔らかい基準を自分に許すことが、考えすぎを減らす第一歩です。
2. 「人に嫌われたくない」という承認欲求の罠
我慢しすぎてしまう人の多くは、**「人から好かれたい」「嫌われたくない」**という強い承認欲求を持っています。相手の期待に応えようと努力するあまり、自分の気持ちを後回しにしてしまうのです。
たとえば、頼まれごとを断れずに抱え込み、疲れていても「いいよ」と言ってしまう。相手を思う気持ちは素晴らしいことですが、それが続くと「自分の限界が分からない」「本音を出すのが怖い」と感じるようになります。
承認欲求は誰にでもある自然な感情です。しかし、他人の評価に自分の価値をゆだねてしまうと、心は常に不安定になります。認知行動療法では、自分の思考を「他人軸」から「自分軸」へ戻す練習を行います。少しずつ「本当はどう感じているか?」に耳を傾けることが、自分を守るための第一歩です。
3. 「我慢が美徳」という思い込みの根強さ
日本では、「我慢することがえらい」「耐えるのが大人」といった価値観が今も根強く残っています。もちろん、忍耐や努力は大切ですが、それが“自分の感情を押し殺すこと”と混同されてしまうと、苦しさに変わってしまいます。
「頑張るのが当たり前」「弱音を吐いたら負け」という考え方の中で育ってきた人ほど、無意識に我慢を選んでしまいます。けれども、感情を抑え込むことは、決して強さではありません。むしろ、自分の気持ちを正直に認めることこそが、真の強さだと言えるでしょう。
認知行動療法では、「我慢しない=わがまま」ではなく、「自分を大切にするための行動」として捉え直します。我慢しすぎの根にある“思い込み”を見直すことで、より健やかな心のバランスが取り戻せるのです。
認知行動療法で見直す「思考のクセ」
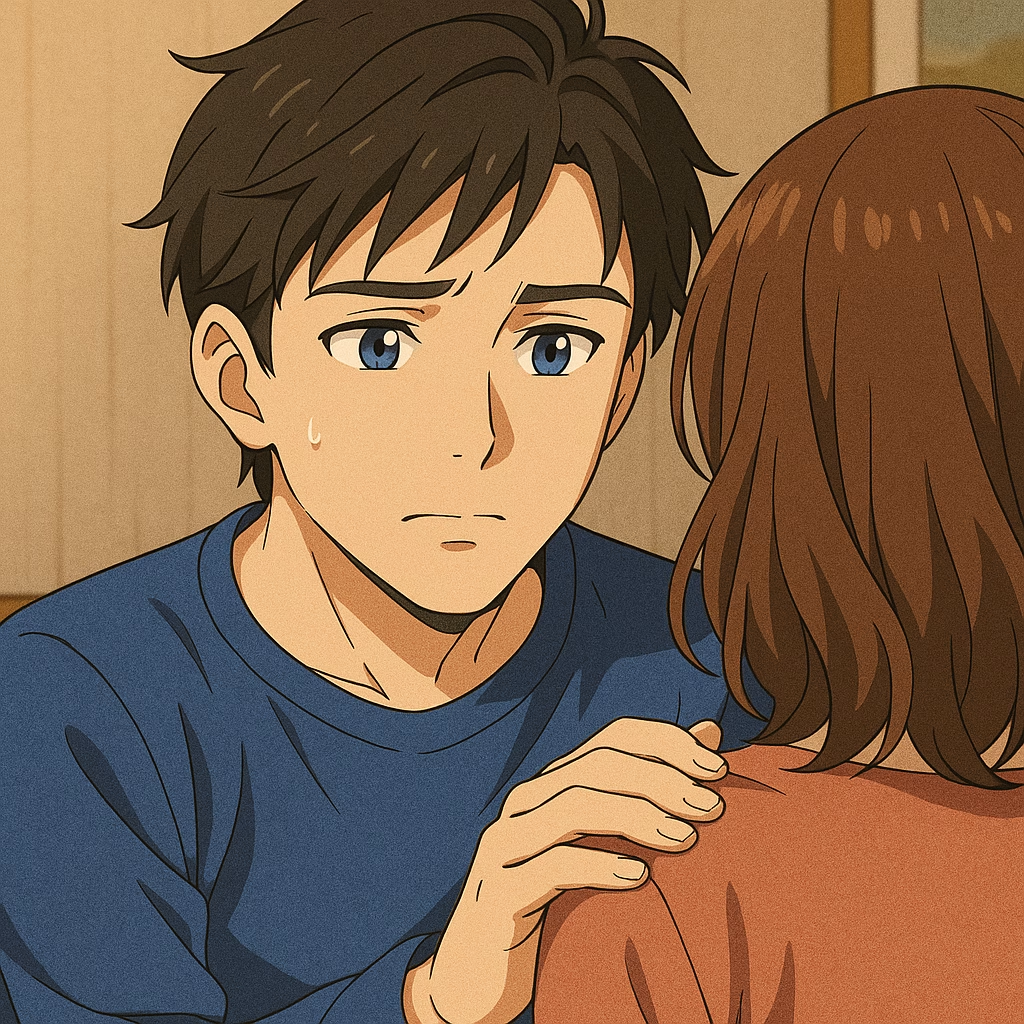
「考えすぎ」や「我慢しすぎ」の正体は、実は“心の中で自動的に浮かぶ思考のクセ”です。ある出来事が起きたとき、私たちは瞬間的に「自分のせいだ」「嫌われたかもしれない」と感じることがあります。このように、**出来事そのものよりも「どう受け取るか」**が感情や行動を左右します。認知行動療法(CBT)は、この“受け取り方=認知”を見直す心理療法です。
たとえば、友人からLINEの返信が遅れたときに「きっと嫌われた」と感じる人もいれば、「忙しいのかも」と受け流せる人もいます。起きている事実は同じなのに、感じ方が違うのは、思考のフィルターが異なるからです。CBTでは、このフィルターを丁寧に見つめ直し、「現実的で柔らかい思考」を取り戻していきます。ここからは、認知行動療法でどのように思考を整理し、心を軽くしていくのかを見ていきましょう。
1. 「出来事・思考・感情・行動」のつながりを整理する
認知行動療法の基本は、「出来事 → 思考 → 感情 → 行動」という流れを理解することです。たとえば、上司に注意されたという出来事があったとします。ある人は「自分はダメな人間だ」と思い落ち込み、別の人は「次は気をつけよう」と前向きに受け止めます。違いは“出来事そのもの”ではなく、“その人の考え方”です。
この流れを整理すると、自分の感情がどのように生まれているのかが見えてきます。感情は勝手にわき起こるように感じますが、実は「思考」というフィルターを通して感じているのです。自分の思考パターンを客観的に見つめることで、「私はいつも自分を責める方向に考えているな」「他人の機嫌を気にしてばかりだな」と気づけるようになります。これがCBTの第一歩です。
2. 「自動思考」を書き出してみる
認知行動療法では、自分の中に浮かぶ「自動思考」を見つけ出す練習をします。自動思考とは、出来事が起きた瞬間に無意識で浮かぶ言葉のこと。たとえば、
・「失敗した。もう終わりだ」
・「怒っている顔を見た。嫌われたかも」
・「自分なんてどうせダメだ」
といった、瞬間的な心のつぶやきです。
これらをノートに書き出すことで、自分の心がどんな場面でネガティブに反応しているのかが見えてきます。最初は「そんなこと書いても意味あるの?」と感じるかもしれませんが、書き出すことで“考え”と“自分”を切り離すことができます。考えが目に見える形になると、それを冷静に眺められるようになり、「これは本当かな?」「別の考え方はある?」と検証できるようになります。
3. 「現実的で優しい思考」に置き換える
自動思考を見つけたら、次はそれを少しずつ“現実的で優しい考え”に置き換えていきます。ここで大切なのは、無理にポジティブに変えることではなく、「もう少し柔らかい見方を探す」ことです。
たとえば、「失敗した。自分はダメだ」→「今回はうまくいかなかったけど、次に活かせることがあるかも」と置き換えてみる。
「断ったら嫌われる」→「相手もきっと忙しいことを分かってくれるはず」と視点をずらしてみる。
こうした小さな修正を繰り返すうちに、脳は“極端な考え”から離れ、バランスの取れた思考を選べるようになります。CBTは“考え方の筋トレ”のようなもの。毎日少しずつ、自分に優しい言葉を選び直すことで、心が少しずつしなやかに回復していくのです。
柔軟な考え方を育てる練習
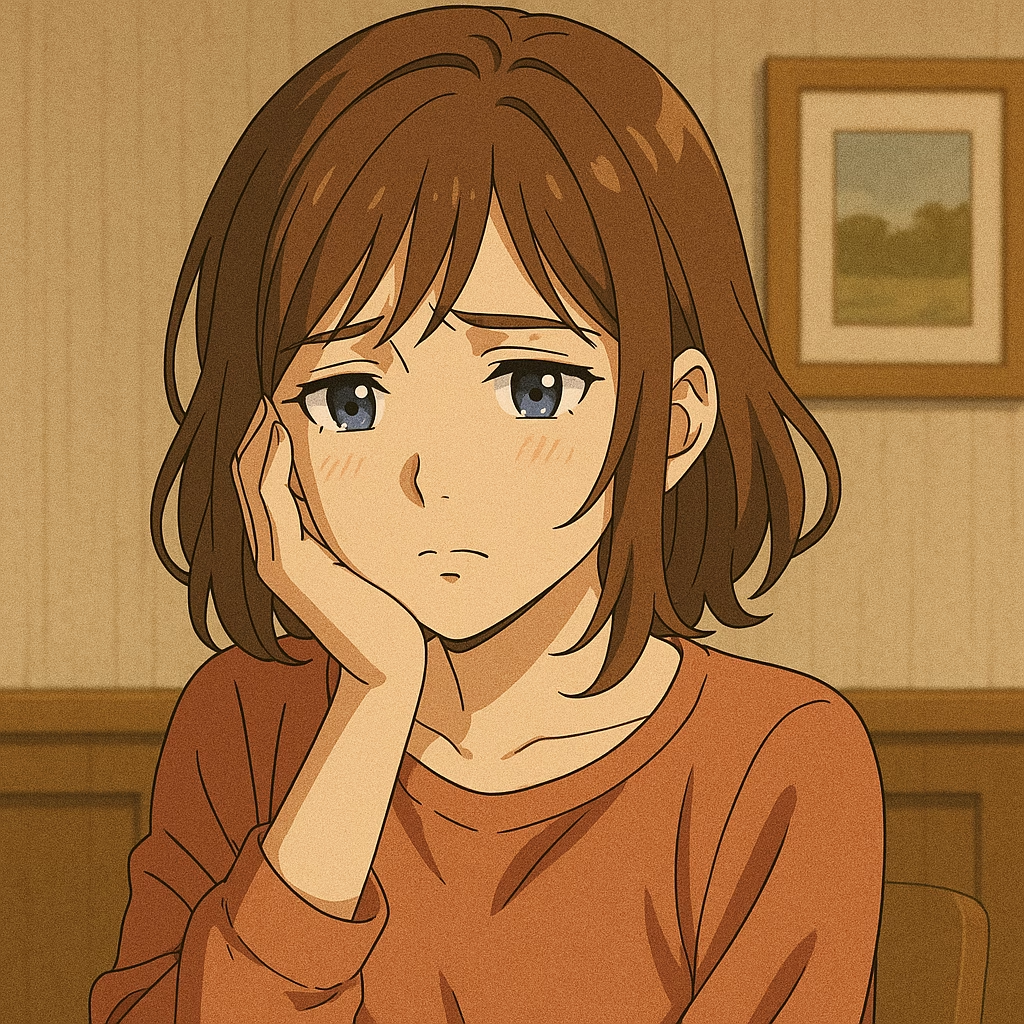
認知行動療法で自分の思考パターンを見つめ直すと、「どうしてこんなに自分を責めてしまうのか」「なぜ人の反応に過敏なのか」という理由が少しずつ見えてきます。ここからは、ただ気づくだけでなく、**“新しい考え方を試してみる段階”**に進みます。つまり、「考えすぎ」「我慢しすぎ」から少し離れて、もう少し柔らかい思考の習慣を育てていく練習です。
柔軟な思考とは、ポジティブになることではなく、“白か黒か”で決めつけないこと。たとえば、「ダメだった」ではなく「うまくいかなかった部分もあるけど、できたところもある」と捉えるようにします。そうすると、心に余裕が生まれ、他人の言葉や出来事に過剰に振り回されにくくなります。ここでは、そのための3つのステップを紹介します。
1. 「別の視点」を探してみる練習
ひとつの出来事に対して、私たちはつい“自分の見方だけ”に偏りがちです。たとえば、同僚が挨拶を返してくれなかったとき、「嫌われたかも」と思う人もいれば、「今日は疲れてるのかも」と思う人もいます。どちらも間違いではありませんが、「別の視点もある」と気づけることが柔軟な考え方の第一歩です。
認知行動療法では、この練習を“リフレーミング”と呼びます。枠(フレーム)を変えて物事を見るという意味です。ネガティブな出来事も、見方を少し変えるだけで意味が変わることがあります。たとえば、「ミスをして恥ずかしい」→「今のうちに学べてよかった」と捉え直す。これを繰り返すうちに、感情の波が穏やかになり、自分を責めすぎる癖が薄れていきます。
2. 「完璧でなくていい」を口ぐせにする
柔らかい考え方を身につけるには、“完璧主義”を少し緩めることが欠かせません。「ちゃんとしなきゃ」「ミスしたら終わり」という思考は、自分を守るつもりで、実は自分を苦しめています。人間は誰でもミスをするし、気分が落ちる日もあります。それを“ダメなこと”と決めつけず、「そんな日もある」と受け入れることが心の柔軟性につながります。
実際に効果的なのは、「まあいっか」「次は少し変えてみよう」といった“ゆるい口ぐせ”を意識して使うこと。こうした言葉は、自分の脳に“リラックスしてもいい”というメッセージを送ります。完璧を目指すよりも、ほどよく力を抜いた方が結果的にうまくいくことも多いのです。自分をゆるめる言葉を持つことは、ストレス社会を生き抜く大事なスキルです。
3. 「我慢する」より「伝える」を選ぶ勇気
柔軟な考え方を持つ上で忘れてはいけないのが、“自分の気持ちを伝える練習”です。我慢しすぎる人は、相手との関係を壊さないために感情を飲み込んでしまいがちですが、言葉にしないことがストレスの原因になっていることもあります。
伝えるときは、相手を責めず、「私はこう感じた」と自分の気持ちを主語にして話すのがポイントです。たとえば、「なんで連絡くれなかったの?」ではなく、「連絡がなかったとき、少し不安だった」と伝える。これは“アサーティブコミュニケーション”という表現法で、認知行動療法でもよく使われます。
自分の気持ちを言葉にすることは、わがままではなく、心の健康を守る行為です。少しずつ練習するうちに、「我慢」ではなく「対話」で関係を築けるようになり、心の負担も軽くなっていきます。
思考のバランスを整えて、心に余白を取り戻す
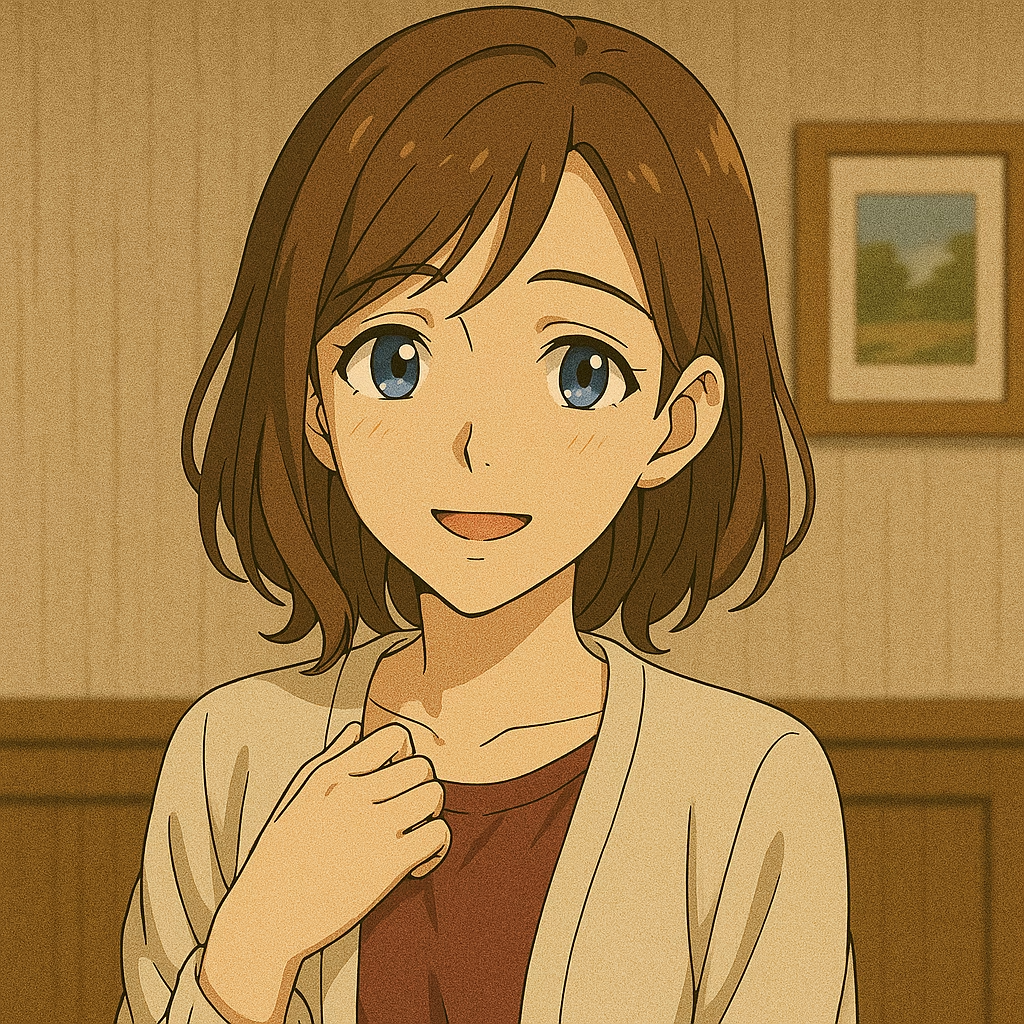
「考えすぎ」「我慢しすぎ」を直そうとすると、多くの人が“考えないようにしよう”“我慢しないようにしよう”と頑張ってしまいます。でも実は、それがまた新しいストレスを生み出してしまうのです。認知行動療法が教えてくれるのは、「やめること」ではなく「整えること」。つまり、自分の中にある思考や感情を否定せずに、ちょうどいいバランスを探すことです。
考えることにも、我慢することにも、それぞれ意味があります。考える力は問題解決に役立ち、我慢する力は人間関係を円滑にします。ただし、それが“行きすぎる”と苦しさに変わる。だからこそ、自分の心の状態を観察し、少しずつ「今の自分にはどんな考え方がちょうどいいのか」を見つけていくことが大切です。ここでは、そのバランスを整えていくための3つのヒントを紹介します。
1. 「考えすぎても大丈夫」と受け入れてみる
考えすぎる人ほど、「考えすぎる自分を責めてしまう」傾向があります。けれど、それではいつまでも心が休まりません。まずは、「今の自分は不安だから、たくさん考えてしまうんだな」と、その状態を受け入れるところから始めましょう。
受け入れるとは、諦めることではなく、**“今の自分を理解してあげること”**です。頭の中でぐるぐるしているときに、「どうして私はこうなんだろう」と責める代わりに、「不安を感じているんだね」と心の声に寄り添う。そうすることで、思考の嵐はいったん落ち着き始めます。
認知行動療法では、このような自己理解を“メタ認知”と呼びます。自分を客観的に眺めることで、感情に飲み込まれにくくなり、考えすぎの悪循環から少しずつ抜け出せるようになります。
2. 小さな「自分優先」を積み重ねる
我慢しすぎる人は、いつも他人を優先してしまいがちです。相手の都合を考えることは優しさですが、自分を犠牲にしてまで続けると、心のエネルギーが枯れてしまいます。
「今日は疲れたから早く寝よう」「無理なお願いは断ってもいい」といった小さな“自分優先”を日常に取り入れてみましょう。最初は罪悪感を感じるかもしれませんが、それは「人を優先することが正しい」と思い込んできた証拠です。その思い込みを少しずつ緩めながら、「自分の機嫌を自分で取る」練習をしていくのです。
小さな自己尊重の積み重ねが、自分への信頼感を育てます。結果的に、周りに対しても穏やかに接することができるようになります。自分を大切にすることは、他人を大切にすることと矛盾しません。むしろその逆です。
3. 「完璧な自分」ではなく「等身大の自分」と生きる
最後に伝えたいのは、**人は誰でも“未完成のままでいい”**ということです。完璧を求めて自分を責め続けるより、できていない部分も含めて「これが今の自分」と受け入れる方が、ずっと健やかに生きられます。
等身大の自分を受け入れるとは、理想を手放すことではなく、「今ここにいる自分を否定しない」こと。失敗も、弱さも、感情の波も、全部その人らしさの一部です。認知行動療法で思考のクセを整えるのは、そんな“ありのままの自分”を守るためでもあります。
完璧である必要はありません。少しずつ、自分のペースで心を整えていけばいい。思考のバランスを取り戻すことは、最終的に「自分を安心させる力」を取り戻すことなのです。
「自分を責めない生き方」――認知行動療法で“心の整理”を始めてみませんか?
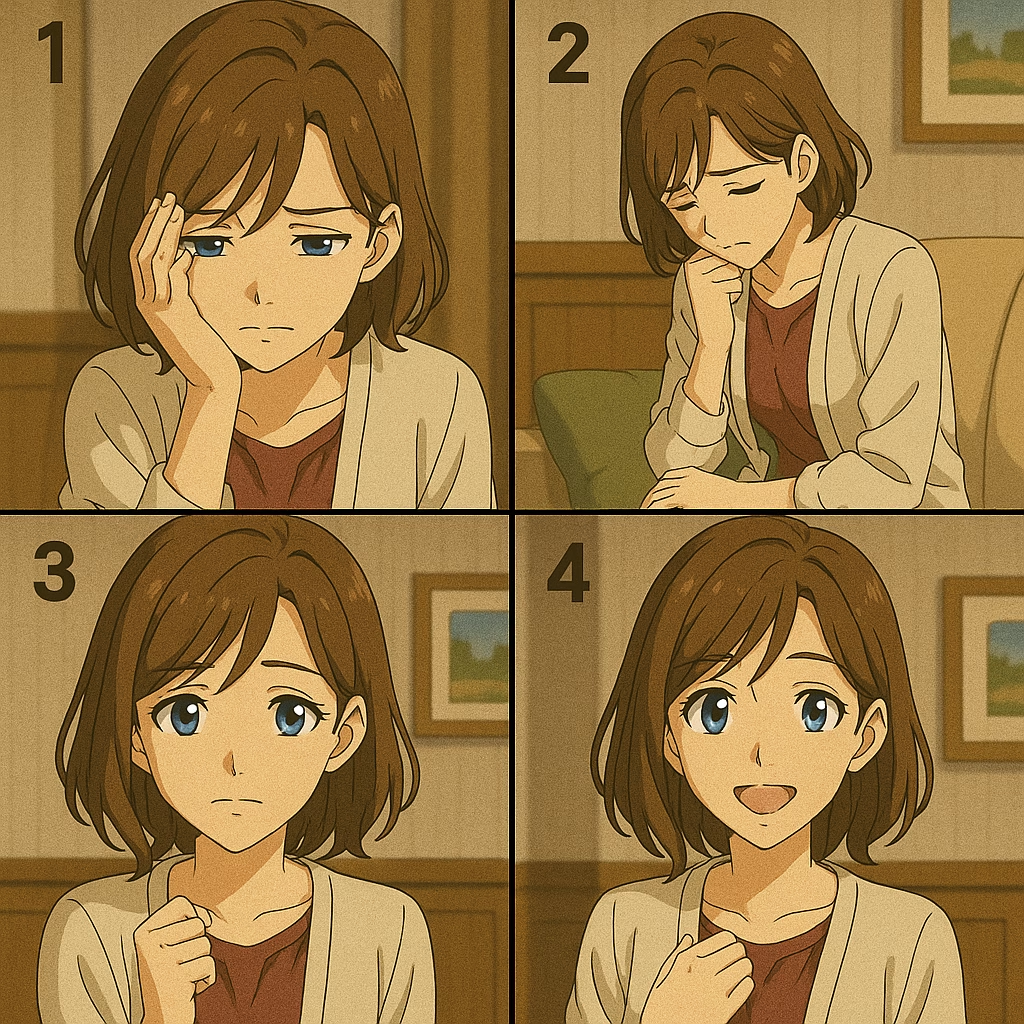
ここまで読んで、「あ、自分も当てはまるかも」と感じた方もいるかもしれません。
考えすぎるのも、我慢しすぎるのも、もともとは「うまくやりたい」「人を大事にしたい」という優しさの表れです。けれど、その優しさが続きすぎると、いつの間にか心が悲鳴を上げてしまうことがあります。
認知行動療法(CBT)は、そんな心の疲れを整理するための実践的な方法です。思考や感情のパターンを見つけ直し、少しずつ“現実的で優しい考え方”へ整えていく。そのプロセスの中で、「自分を責める」から「自分を理解する」へと視点が変わっていきます。
カウンセリングでは、こうした“思考の整理”を一緒に行っていきます。
ひとりでは気づけない考え方のクセを、専門家と一緒に丁寧にほどいていくことで、頭の中のモヤモヤが少しずつ言葉に変わり、感情も軽くなっていくのです。
心のクセは、直すものではなく「気づくもの」。
気づくことから、変化は静かに始まります。
もし今、「考えすぎて疲れた」「我慢してばかりで苦しい」と感じているなら、カウンセリングという時間を、自分の心に“余白”を取り戻すためのひとつの選択肢にしてみてください。
あなたのペースで、少しずつ“ラクな考え方”を見つけていけるよう、一緒に寄り添います。


を軽くする方法-150x150.avif)


