自己否定グセにサヨナラ!認知行動療法で始める自分ほめ習慣【2】
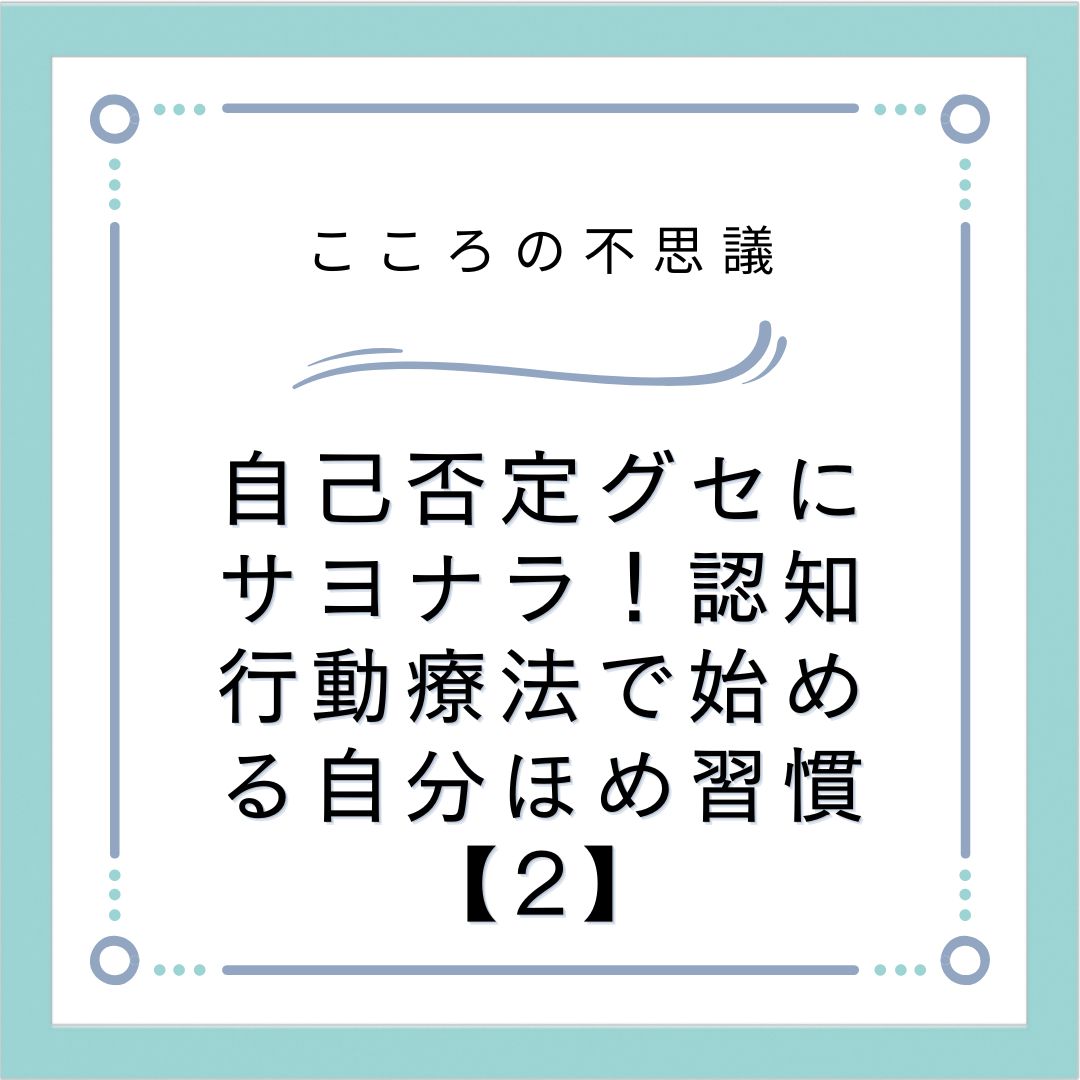
「もっと頑張らなきゃ」「こんな自分じゃダメだ」――そんなふうに、自分を責めてしまうクセがついていませんか?でも実は、その“厳しさ”が心の疲れを積み重ねていることもあるんです。この記事では、認知行動療法をベースにした“自分をほめる習慣”を始めるためのヒントをご紹介します。無理にポジティブになる必要はありません。小さな一歩を認めてあげることから、少しずつ心はやわらかく変化していきますよ。
投稿者プロフィール

- 心理カウンセラー
-
【経歴】
・キャリアカウンセラー15年
・心理カウンセラー10年
※相談件数10,000件以上
【主な相談内容】
1.ストレス管理とメンタルケア
・日々のストレスやプレッシャーにどう対応すれば良いか。
・仕事や家庭でのストレス解消法。
2.自己理解と自己成長
・自己肯定感を高めたい。
・自分の強みや価値観を明確にしたい。
3.人間関係の悩み
・職場や家庭でのコミュニケーションの改善。
・対人関係における不安や緊張感への対処法。
4.不安や恐怖の克服
・予期不安や強い緊張感に悩んでいる。
・パニック障害や全般性不安障害のケア。
5.うつ症状や気分の浮き沈み
・やる気が出ない、気分が落ち込みがち。
・抑うつ状態から抜け出したい。
6.人生の転機や変化への対応
・キャリアチェンジや子育てなど、ライフイベントへの適応。
・新しい環境への不安や戸惑い。
7.恋愛や夫婦関係の悩み
・パートナーシップの問題解決。
・自分の感情や価値観をどう伝えるべきか。
8.自己批判やネガティブ思考の改善
・自分を責めすぎる傾向を変えたい。
・過去のトラウマや後悔にとらわれず前向きに生きる方法。
9.家族関係や親子間の問題
・子育ての悩み。
・親や家族との関係性の見直し。
10.生きる意味や自己実現の探求
・人生の目的を再確認したい。
・自分らしい生き方を見つけるサポート。
【アプローチ方法】
1.傾聴を重視したカウンセリング
・クライアントの気持ちや考えを尊重し、安心して話せる場を提供します。
・言葉だけでなく表情や態度も大切に、深いレベルで共感することを心がけています。
2.クライアント中心療法
・クライアント自身の中にある解決の糸口を引き出すサポートを行います。
・「どうしたいか」「何を感じているか」を一緒に探るプロセスを大切にします。
3.認知行動療法(CBT)
・ネガティブな思考や行動パターンを明確にし、それを建設的なものに変えるお手伝いをします。
・小さな行動目標を設定し、実際の生活に役立つ具体的な変化を目指します。
4.ナラティブセラピー
・クライアント自身のストーリーを紡ぎ直し、ポジティブな視点で捉え直すプロセスを支援します。
・過去の経験を成長や学びとして活用する力を引き出します。
5.対話を通じた柔軟なサポート
・一人ひとりのニーズに合わせて柔軟にアプローチを変えます。
・言葉だけでなく非言語的な表現(声のトーンや間合い、表情やしぐさなど)にも焦点を当てる場合があります。
最新の投稿
目次
- ○ 「どうせ私なんて…」が口癖になっていませんか?
- ・「どうせ私なんて…」が生まれる心の仕組み
- ・否定的な言葉が引き起こす影響
- ・その口癖をやさしく手放すためにできること
- ○ 自己否定の悪循環に気づこう
- ・自己否定の悪循環とは?
- ・悪循環が続くとどうなるのか?
- ・悪循環を抜け出すためにできること
「どうせ私なんて…」が口癖になっていませんか?

「どうせ私なんて…」と自分を否定する言葉が、いつの間にか口癖のようになっていませんか?自己否定の思いが強いと、何かうまくいかないときや自信をなくした瞬間に、ついそうつぶやいてしまうことがあるかもしれません。自分を卑下するこの言葉を繰り返すたび、心のどこかがさらに傷ついてしまうように感じることもあるでしょう。実はその裏には、自分の心を守ろうとする無意識の働きが隠れているのかもしれません。
本当は自分が一番傷ついてしまう言葉なのに、なかなかやめられない――それは、長年の経験や心のクセが関係している可能性があります。「どうせ私なんて…」という口癖を持つ人は決して少なくありません。それほど辛い思いを抱えているからこそ、同じ言葉を繰り返してしまうのです。まずは、そんな自分を責めずに、なぜそう感じてしまうのかを一緒に見つめてみませんか?
この記事では、なぜ私たちはそのように「どうせ私なんて…」と思ってしまうのか、その心の仕組みをやさしくひもときます。また、否定的な言葉が心にどんな影響を及ぼすのかを考え、最後にその口癖を少しずつ手放していくためにできることを探ってみましょう。
「どうせ私なんて…」が生まれる心の仕組み
誰も最初から「どうせ私なんて…」と思いたいわけではありません。それでもふとしたときにそう感じてしまうのは、心に染み付いた思考パターンが影響しています。認知行動療法(CBT)では、こうした否定的な考えは「自動思考」と呼ばれ、無意識のうちに湧き上がるクセのようなものだと考えます。例えば、一度失敗しただけで「自分は何をやってもダメだ」と極端に考えてしまう(認知のゆがみ)と、その延長で「どうせ私なんて…」という結論に至りやすくなります。心の中にいつの間にか「自分には価値がない」という思い込みが根付いていると、何かあるたびに自動的に自分を否定する考えが出てきてしまうのです。
こうした否定的な自己イメージや思考のクセは、多くの場合、過去の経験から形作られます。幼い頃の環境や親との関係(愛着)の中で十分に認めてもらえなかったり、周囲と比べられて「もっと頑張らなきゃダメ」と言われ続けたりすると、子ども心に「自分はそのままでは価値がないのかもしれない」と感じてしまうことがあります。そのとき受けた心の傷は、大人になった今も潜在意識に残り、自己否定的な信念として根付いてしまうのです。例えば、学生時代の挫折や人間関係での深い傷がきっかけで、「どうせ私なんて何をしても報われない」という思いを抱え始める人もいるでしょう。
そして、心の奥には当時傷ついたままの子どもの部分(インナーチャイルド)が存在していて、今のあなたが挫折しそうなときや不安を感じたとき、「また傷つく前にあきらめてしまおう」とするかのように「どうせ私なんて…」という言葉をつぶやかせることがあります。これは、自分自身を守るために身につけた心理的な防衛反応と言えます。本来は傷つかないようにするための策ですが、前向きな気持ちまで押さえ込んでしまうため、自己成長の機会を奪ってしまう面もあるのです。ただ、重要なのは、こうした心の仕組みは決してあなたの「弱さ」ではなく、過去の環境に適応する中で形成されたものだという点です。
否定的な言葉が引き起こす影響
否定的な言葉を習慣的に自分に投げかけていると、知らず知らずのうちに様々な影響が現れます。例えば、何かに挑戦する前から「どうせ私なんてできない」と決めつけてしまえば、本当はできるかもしれないことにも最初から踏み出せなくなってしまいます。確かに何もしなければ失敗せずに済むかもしれませんが、同時に成功するチャンスも逃してしまいます。また、「どうせ私なんて愛されない」と感じていると、たとえあなたを大切に思ってくれる人がいても、その好意を素直に信じられず受け取れなくなってしまうかもしれません。こうして自己否定の言葉を繰り返すほど、周りからのポジティブな評価やサポートさえも届きにくくなってしまうのです。
さらに、否定的な言葉は自分の心に対して強い暗示のような役割を持ちます。繰り返すほどに「やっぱり自分はダメなんだ」という思い込み(信念)が強化され、自己肯定感は低下していきます。認知行動療法の観点でも、否定的な考えは否定的な感情や行動を引き起こし、それがまた否定的な考えを強めるという悪循環を招くとされています。例えば、「私には価値がない」という考えがあると落ち込みや無力感(感情)が生まれ、何も行動できなくなってしまう(行動)。その結果、さらに「ほら、やっぱり自分は何もできない」という否定的な考えが強まってしまう―このようにして負のループにはまり込んでしまうのです。一時的には「期待しなければ失望しなくて済む」と自分を守っているつもりでも、長期的に見ると心の元気を奪われ、より苦しさが増してしまうことがあります。
その口癖をやさしく手放すためにできること
では、この「どうせ私なんて…」という口癖を少しずつ手放すには、どのようなことができるでしょうか。急に考え方を変えるのは難しいかもしれませんが、次のようなアプローチを試してみることができます。
自分の考えに気づく:
まずは、自分が「どうせ私なんて…」と考えている瞬間に意識を向けてみましょう。落ち込んだとき、失敗したとき、あるいは誰かに褒められたときなど、自分がつい否定的な言葉を心の中でつぶやいていないか観察します。「また言ってしまったな」と気づくだけでも第一歩です。自分の心の動きを客観的に捉えることで、考え方のパターンに少しずつ目を向けられるようになります。
思考を書き出して見直す:
次に、自分の頭に浮かぶ否定的な考えを書き出してみましょう。紙に「どうせ私なんて〇〇だ」と感じた状況とその気持ちを書き留めてみるのです。その上で、その考えが事実に合っているか問いかけます。本当に自分は全くダメなのでしょうか?他の見方はないでしょうか?例えば、うまくできなかったことが一つあっても、それまでに努力してきた過程や、できた部分もあったはずです。書き出して客観的に見てみると、否定的な考えが絶対的な事実ではなく、感情に影響された一つの見方に過ぎないことに気づけるでしょう。
自分に優しい言葉をかける:
否定的な考えに気づいたら、それを打ち消すような優しい言葉を自分に投げかけてみます。最初は照れくさいかもしれませんが、自分が落ち込んでいるときに、親しい友人に声をかけるつもりで言葉を選んでみてください。例えば、「そんなに自分を責めなくていいんだよ」「うまくいかなくても、あなたには価値があるよ」といった言葉です。もしピンとくる言葉が見つからない場合は、心の中に傷ついたままの自分(インナーチャイルド)を思い浮かべて、その子に掛けてあげたい言葉を想像してみましょう。「大丈夫だよ」「よく頑張っているね」と優しく語りかけることで、少しずつ自己否定の感情を和らげることができます。
小さな成功体験を積む:
否定的な自己評価を変えるには、「自分にもできる」という実感を少しずつ積み重ねていくことも効果的です。最初はごく小さなことで構いません。例えば、「今日は書類を一つ片づけられた」「友人にメールを送ることができた」など、自分ができたことや達成できたことを日々振り返ってみましょう。どんなに些細なことでも構いません。それを自分で認めてあげる習慣を作ることで、「自分は何をやってもダメ」という思い込みを徐々に書き換えていくことができます。小さな成功体験の積み重ねが、自信と自己肯定感を育む土台となるのです。
信頼できる人に話してみる:
一人で抱え込まず、信頼できる友人や家族、あるいは専門のカウンセラーなどに自分の気持ちを話してみることも大切です。「実はいつも自分なんてダメだと思ってしまう」と打ち明けるだけでも、心が軽くなることがあります。他の人から見ると、あなたにはたくさんの良いところがあるはずです。第三者の視点から優しい言葉をかけてもらうことで、自分では気づけなかった長所や価値に目を向けられるようになるでしょう。また、専門家に相談すれば、認知行動療法などのアプローチでより体系的なサポートを受けることもできます。必要であれば遠慮なくそうした助けを借りてください。
これらの方法を実践する中で大切なのは、焦らず自分のペースで取り組むことです。長年染み付いた考え方は、一晩で変わるものではありません。時にはまた「どうせ私なんて…」と思ってしまうことがあっても、自分を責めず「今はそう感じているんだな」と受け止めて、また少しずつ練習を続けてみてください。あなたが自分に向ける目が少しずつ優しくなっていけば、その口癖も自然と手放せる日がきっと来るでしょう。
自己否定の悪循環に気づこう

多くの人が日々の生活の中で、つい自分を否定するような考えに陥ってしまうことがあります。何かうまくいかなかったときに「自分はダメだ」「どうせまた失敗する」と心の中でつぶやいてしまうことはないでしょうか。こうした自己否定の言葉は一時的な落ち込みを引き起こすだけでなく、その後の行動にも影響を与え、さらに状況を悪化させてしまうことがあります。例えば、些細なミスで「やっぱり自分は何をやってもダメだ」と思い込んでしまうと、自信を失い、新しい挑戦を避けるようになります。その結果、成長や成功の機会を逃し、「ほら、やっぱり自分には無理だ」と再び自己否定してしまう——このようにして**「自己否定の悪循環」**が生まれるのです。
この悪循環は、自分でも気づかないうちに繰り返され、心に深い影響を及ぼします。認知行動療法(CBT)という心理療法の視点から見ると、私たちの「考え方」は感情や行動と密接につながっており、ネガティブな考えはネガティブな感情と行動を生み、それがまたネガティブな考えを強めるというサイクルに陥ると考えられています。過去の経験で傷ついた記憶や、幼いころに受けた批判などが原因で自己肯定感が低くなっていると、このサイクルが生まれやすくなってしまいます。しかし、大切なのは**「まずその悪循環に気づくこと」**です。気づくことで初めて、その連鎖から抜け出す一歩を踏み出すことができます。
この記事では、自己否定の悪循環とは何か、その悪影響が続くと心と行動にどのような影響が出るのか、そしてその悪循環から抜け出すためにできる具体的なステップについて、認知行動療法の視点を中心にわかりやすく解説します。日常生活に取り入れやすいヒントも交えながら、過去の経験と自己肯定感との関係にも触れていきます。自分を責めがちな悪循環に心当たりのある方が、この記事を通じて少しでも「自分を大切にするきっかけ」を見つけられたら幸いです。
自己否定の悪循環とは?
まず、「自己否定」とは何でしょうか。これは、本来そこまで自分を責めなくても良いような場面でも、「自分なんてダメだ」「どうせうまくいかない」といった否定的な評価を自分自身に下してしまう考え方を指します。小さな失敗や、他人からの何気ない一言さえも、自分の欠点や無価値さの証拠のように感じてしまうことはないでしょうか。そのような否定的な解釈が一度生まれると、それに伴って落ち込みや不安といった感情が引き起こされます。そして、落ち込んだ気分のまま消極的な行動を取ってしまったり、さらにミスをしてしまったりすると、「ほらやっぱり自分はダメだ」という思いが強まり、また自己否定的な考えにとらわれてしまいます。このように、否定的な考え→不安な感情→消極的な行動→さらに否定的な考えというループが繰り返される状態が「自己否定の悪循環」です。
心理学では、こうした極端で偏った考え方の癖を「認知の歪み」と呼ぶことがあります。認知行動療法(CBT)の観点では、物事の受け取り方(認知)がネガティブになると、それに引きずられて感情も行動もネガティブになり、結果として状況が悪化して「ほら見たことか」という否定的な考えがさらに強まると説明します。例えば、一度の失敗で「もう何をやってもダメだ」と極端に考えてしまうような白黒思考や、物事の悪い面ばかりに目が行って自分を責めてしまうような思考パターンなどが代表的です。こうした認知の歪みに気づかずにいると、否定的な解釈がどんどん習慣化されてしまいます。
また、自己否定の悪循環の背景には、過去の経験から生まれた根深い「自己に対する信念」が影響していることも少なくありません。幼い頃に繰り返し否定されたり、学校や職場で失敗体験が積み重なったりすると、「自分は価値がない」「どうせ自分はうまくいかない」というネガティブな信念(コアビリーフ)が心に刻まれることがあります。そして、こうした自己イメージが傷ついた状態、すなわち自己肯定感が低い状態では、現在の出来事に対しても必要以上に否定的な解釈をしてしまいがちです。例えば、誰かに注意をされたときに「自分がダメだから叱られたんだ」と感じて落ち込むといった具合に、事実以上に自分を責めてしまう傾向が現れます。
つまり、自己否定の悪循環とは、過去から形成された「自分はダメだ」という思い込みが現在の思考・感情・行動にネガティブな影響を与え、その結果がまた「ほらやっぱり自分はダメだ」という思い込みを強化してしまう——そんな負のループを指すのです。このループに陥っていると、自分ではなかなか抜け出しにくいものですが、まずはその仕組みを知ることが、抜け出すための第一歩になります。
悪循環が続くとどうなるのか?
では、自己否定の悪循環に陥ったままでいると、私たちの心や行動にはどのような影響が現れるのでしょうか。
まず心(メンタル面)への影響としては、自己否定が続くことで自己肯定感はさらに低下し、自信や意欲が失われていきます。常に「どうせ自分なんて…」という思いが頭の片隅にある状態では、新しいことに挑戦する気力が湧かず、日々の喜びも感じにくくなってしまいます。自分の良いところや頑張っている部分が見えなくなり、どんなに努力しても「まだ足りない」「やっぱり自分はダメだ」と満足できなくなるかもしれません。このような状態が長く続くと、慢性的なストレスや不安感、落ち込みが蓄積し、やがては抑うつ状態(いわゆるうつ状態)に陥ってしまう可能性もあります。常に心が晴れない状態が続くのは、とてもつらいことですし、「自分なんて生きている価値がないのでは」と極端に感じてしまう危険性も否定できません。
次に行動への影響です。自己否定の悪循環下では、「どうせ自分にはできない」と考えてしまうために、新しいチャレンジや目標に一歩踏み出すことを恐れて避けてしまう傾向があります。その結果、成長の機会を自ら閉ざしてしまったり、本当はやってみたいことにも挑戦できずに終わってしまったりするかもしれません。また、失敗を恐れるあまり完璧主義になりすぎてしまうこともあります。完璧を求めて行動を始められず、締め切り間近になって慌ててしまったり、準備に時間をかけすぎてかえって疲れてしまったりすることもあるでしょう。あるいは、人間関係においても「自分なんて愛されるはずがない」と感じることで、親しい人に心を開けなかったり、相手の何気ない言葉を過剰にマイナスに受け取ってしまったりすることがあります。その結果、周囲から誤解されたり、ますます孤独感が深まるという悪影響も考えられます。
要するに、自己否定の悪循環が続くと、心は萎縮し、行動は消極的・過剰防衛的になり、人生の様々な場面で損失が生じてしまいます。自分に自信が持てないままだと、本来得られたはずのチャンスや喜びを逃してしまい、「やはり自分はダメだ」という思い込みをいっそう強めることにつながるのです。このようにして悪循環が深まる前に、できるだけ早く対策を取ることが大切です。「これではいけない」と頭では分かっていても、抜け出せないと感じるかもしれませんが、次のセクションではその悪循環を断ち切るための具体的な方法を見ていきましょう。
悪循環を抜け出すためにできること
自己否定の悪循環に気づいたら、少しずつそのループから抜け出す行動を始めてみましょう。ここでは、日常生活に取り入れやすい具体的なステップをいくつか紹介します。
ネガティブな思考パターンに気づく:
まずは、自分がどんなときにどんな否定的な考えをしているのかを意識することから始めます。落ち込んだり自己嫌悪に陥ったりする場面で、頭の中に浮かんだ言葉を書き留めてみましょう(この作業は「思考記録」とも呼ばれ、CBTの基本的な技法です)。例えば、「会議で意見をうまく言えなかった。自分はやっぱりダメだ」と感じたなら、その考えを紙に書いてみます。こうして書き出してみることで、自分の思考パターンに客観的に目を向けることができます。「またいつもの否定的な考えが出てきたな」と気づくだけでも、大きな第一歩です。
考え方を見直し、現実的な視点を取り戻す:
次に、書き出した否定的な考えに対して、「本当にそうだろうか?」と問いかけてみます。感情にまかせて自分を責めているときは、物事を極端に考えてしまっているかもしれません。先ほどの例で言えば、「意見をうまく言えなかった=自分はダメ」という結論になっていますが、それは飛躍しすぎた解釈かもしれません。本当は「今日はたまたまうまく話せなかったけれど、準備不足だったのかもしれない。次は少しメモを用意してみよう」など、もっと建設的な捉え方ができるはずです。事実と感情を切り分け、過去の経験から生まれた思い込みが入り込んでいないかチェックしてみましょう。信頼できる友人に自分の考えを聞いてもらい、客観的な意見をもらうのも有効です。自分一人では「絶対そうに違いない」と思っていたことも、他の視点から見ると「そんなことはないよ」と気づける場合があります。認知行動療法では、このプロセスを通じて否定的な認知の歪みを修正し、より現実的でバランスの取れた考え方に置き換えていく練習をします。
小さな成功体験を積み、自分を肯定する:
否定的な考え方を修正したら、次は実際の行動で自分に「できる」という感覚を取り戻していきましょう。いきなり大きな目標に挑む必要はありません。まずは日常の中で手の届く小さな目標を設定し、それを達成してみることから始めます。たとえば、「今日は書類を一つ片付ける」「誰かにありがとうを伝える」といった簡単なことで構いません。達成できたら、「自分にもできた」「一歩前進できた」と、その小さな成功をしっかり自分で認めてあげてください。そうした小さな成功体験の積み重ねが、少しずつ自己肯定感を高めていきます。自分を褒めることに最初は抵抗があるかもしれませんが、誰だって成果を出したときには認められるべきですし、自分自身からの承認は想像以上に心の支えになります。もし途中で失敗しても、「またダメだった」と決めつけずに、「今回はうまくいかなかったけど次はこうしてみよう」と前向きに捉えてみましょう。うまくいかなかった経験も学びの一つです。そして時には、信頼できる人に気持ちを話したり、専門家の助けを借りたりすることも検討してください。周囲の支えを得ることは決して甘えではなく、悪循環を断ち切るための賢い戦略です。
以上のステップを繰り返し試していくことで、少しずつ思考の癖や行動パターンに変化が生まれてきます。大切なのは、焦らず、自分を労わりながら少しずつ継続することです。最初はうまくいかなくても、自分を責めないでください。長年かけて身についてしまった考え方の習慣を変えるには時間がかかりますが、一歩ずつ練習を重ねることで必ず変化は訪れます。悪循環に気づき、抜け出そうとするその意識自体が、前向きな一歩を踏み出している証拠です。自分を否定する声に負けず、少しずつでも自分を認め、大切にする習慣を築いていきましょう。
自己否定グセにサヨナラ!認知行動療法で始める自分ほめ習慣【1】
自己否定グセにサヨナラ!認知行動療法で始める自分ほめ習慣【3】


を軽くする方法-150x150.avif)


